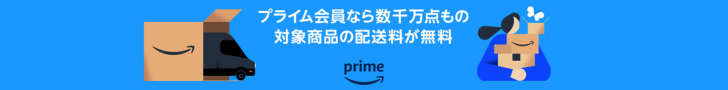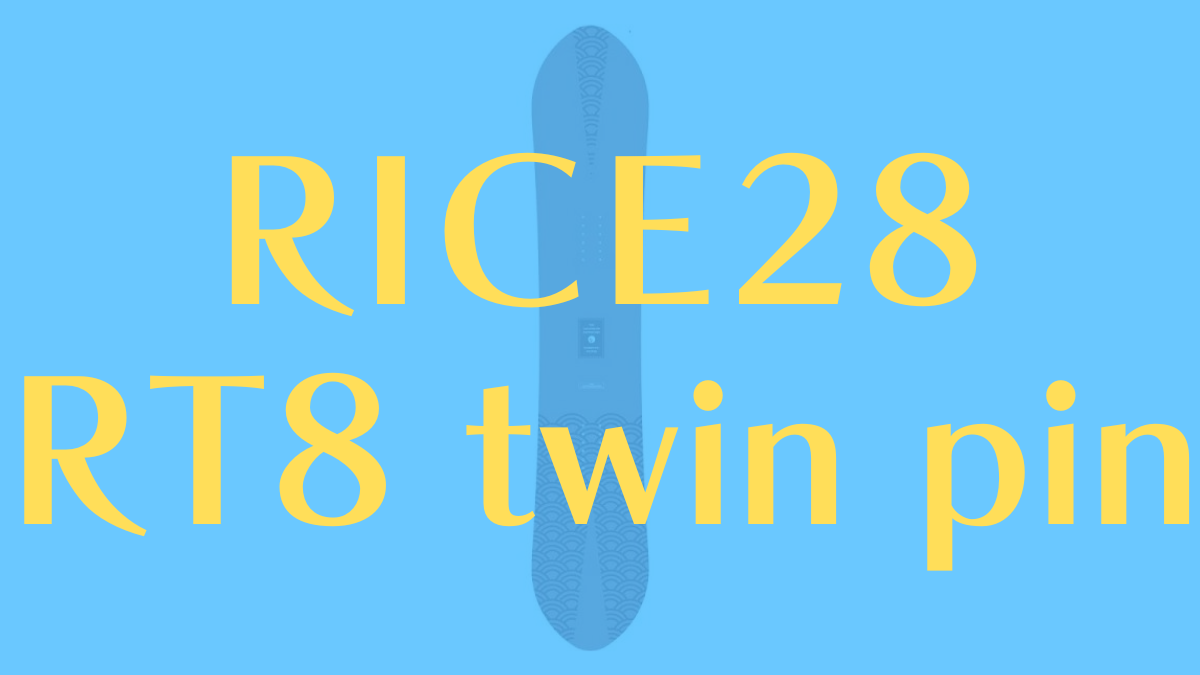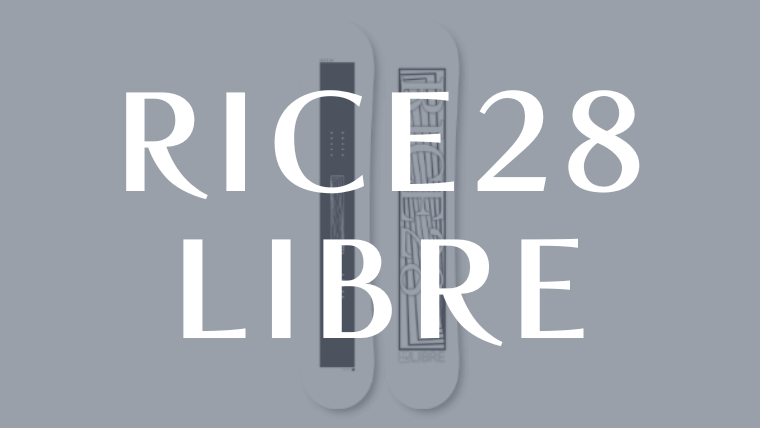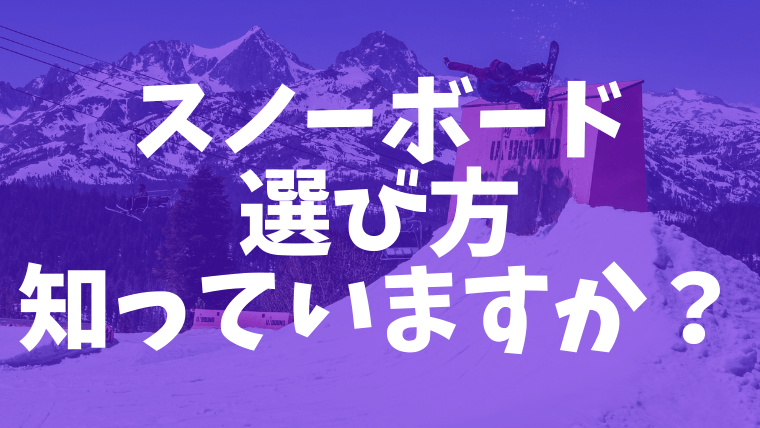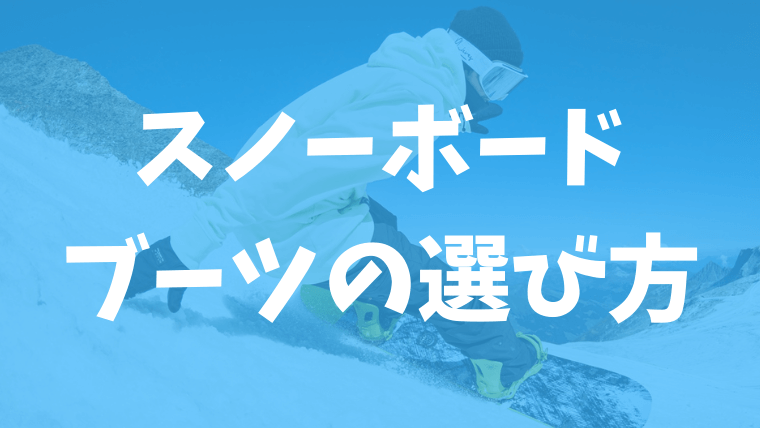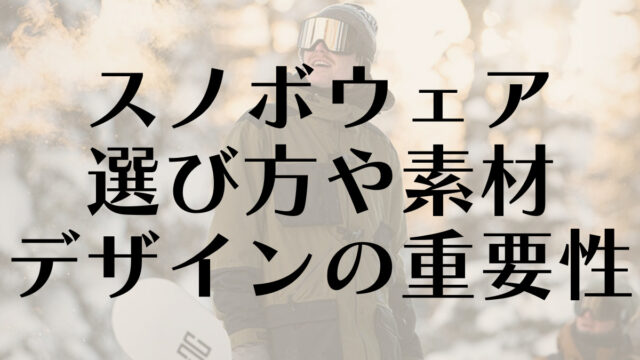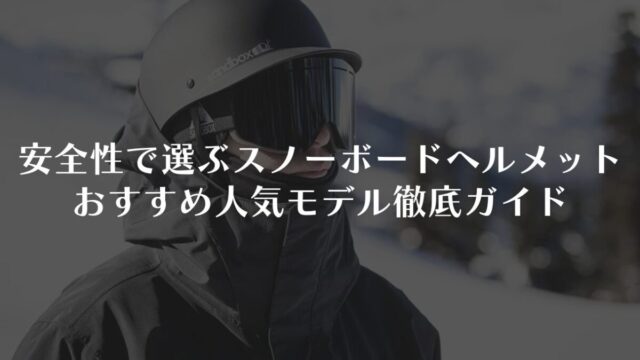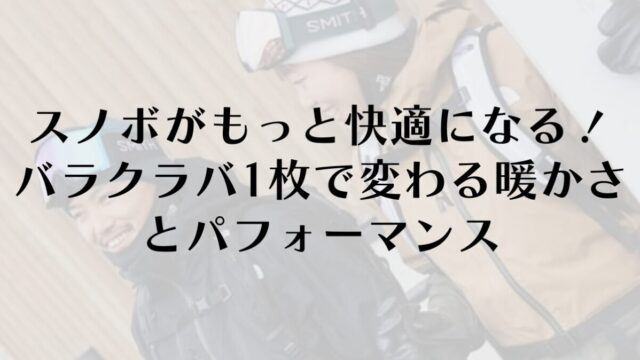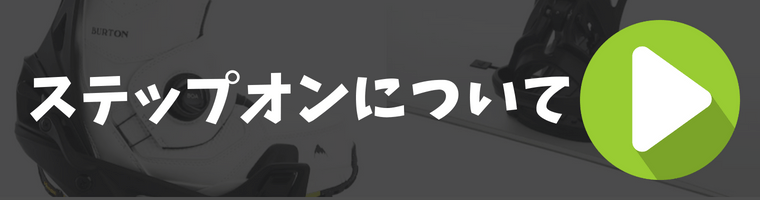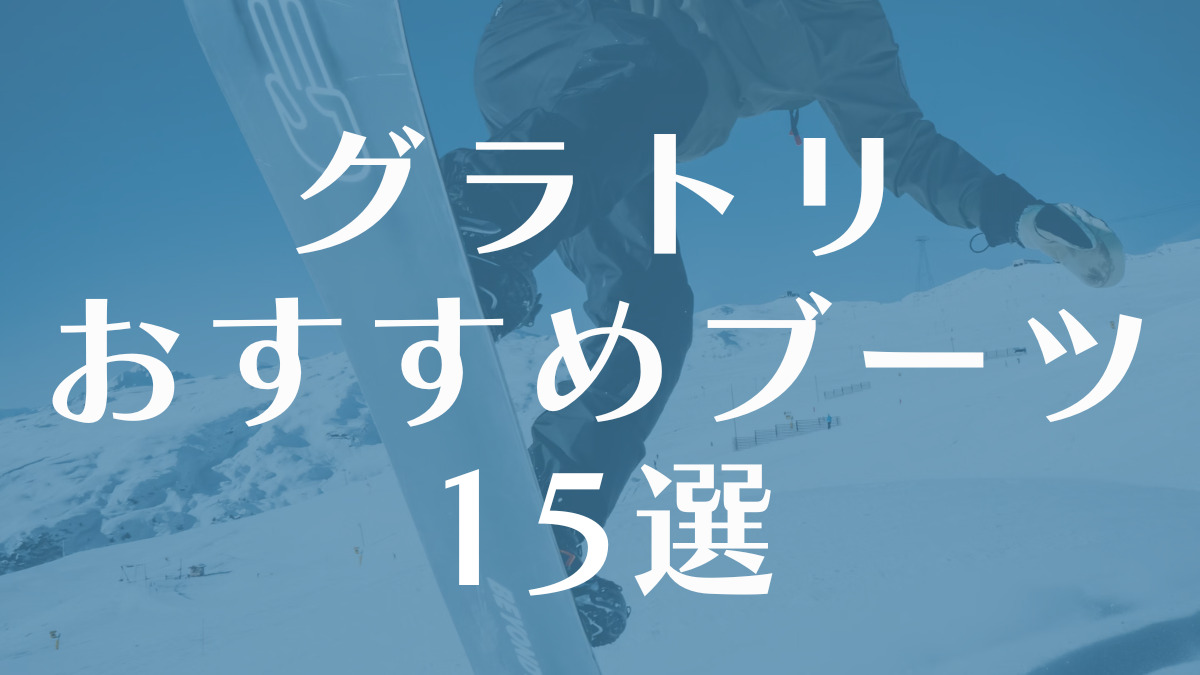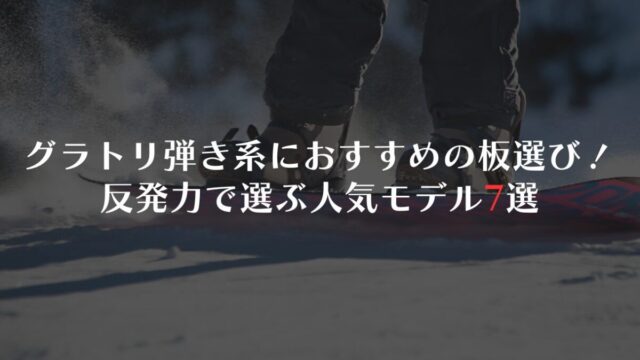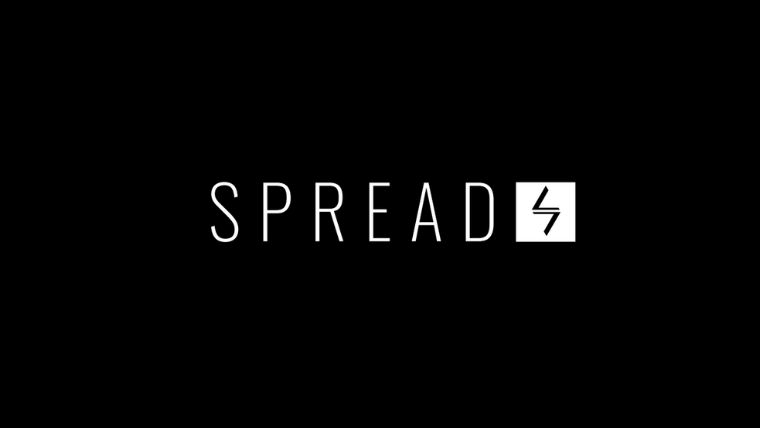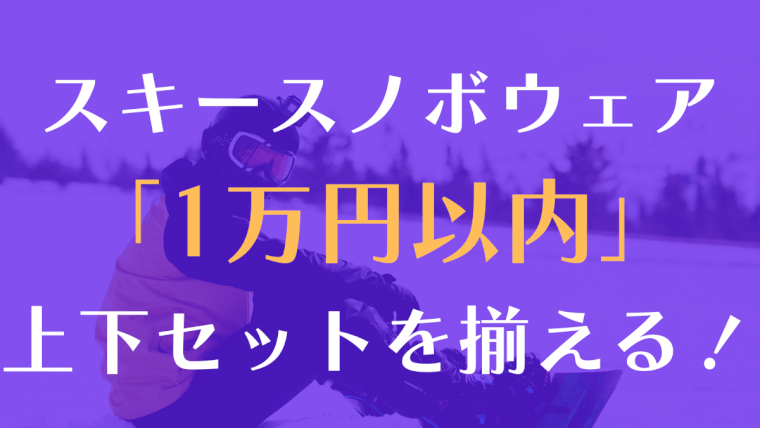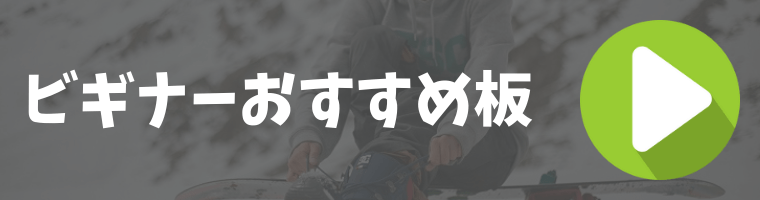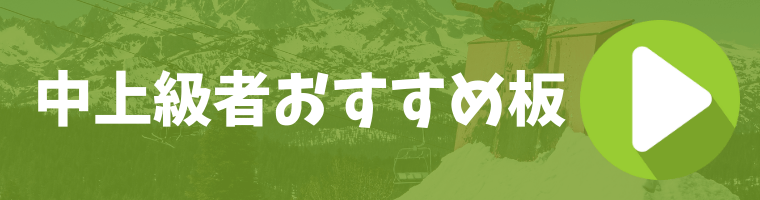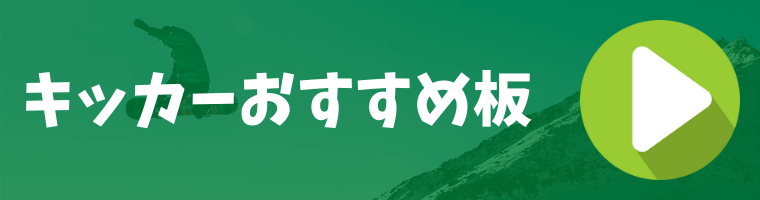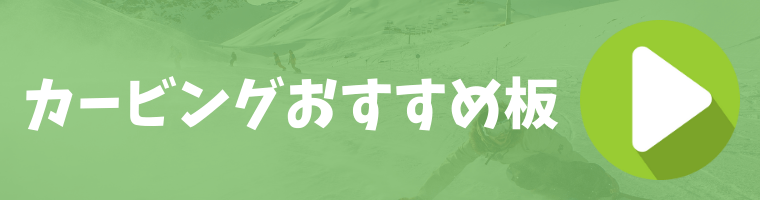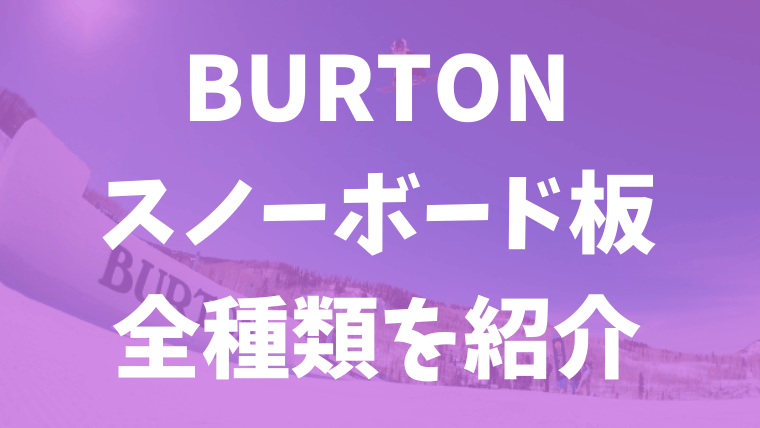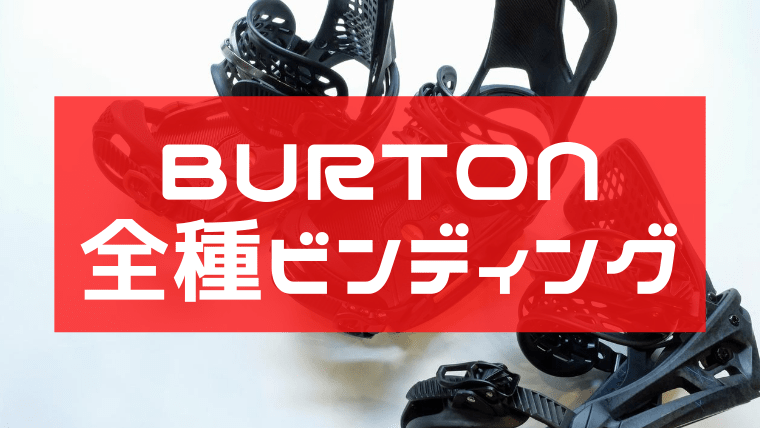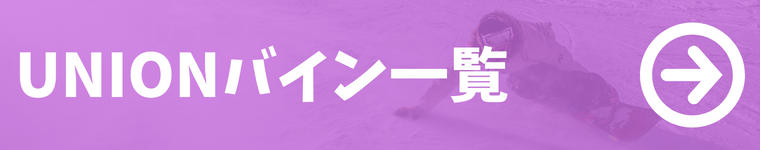【RICE28】RT7とRT9を比較!違いを知って最適な1本を選ぼう

「次の板はRICE28にしたいけれど、RT7とRT9のどちらを選べばいいのか分からない」と悩んでいませんか。 決して安くない買い物だからこそ、自分のスタイルに合った最適な一本を選びたいですよね。
この記事では、国産スノーボードブランドとして絶大な人気を誇るRICE28の看板モデル、RT7とRT9の違いについて詳しく解説します。
グラトリやカービング、ラントリといったそれぞれのスタイルにおける適性や、硬さ、反発力の違いなどを比較しながら、あなたにぴったりのボード選びをサポートします。
- RT7とRT9のスペック上の明確な違いとそれぞれの特性
- 自分の滑りのスタイルに合っているのがどちらのモデルか
- 低速での遊びやすさと高速域での安定感の違いについて
- 購入前に知っておくべきサイズ選びや推奨レベルの目安
RICE28のRT7とRT9の比較と違い:スペック編
- 結論:RT7はしなやかでRT9は高反発
- キャンバー形状と有効エッジの特性
- フレックスの違いとトーションの操作性
- 搭載されるプレートや補強材の特徴
- 滑走性能を左右するソールの素材
- 重量の違いとスイングウエイトの軽さ
結論:RT7はしなやかでRT9は高反発
RICE28のRT7とRT9における比較や違いを理解する上で、まず押さえておきたいのがそれぞれの基本的な性格です。
一言で表現するならば、RT7は「しなやかで粘りのあるボード」、RT9は「高反発でハリのあるボード」と定義できます。
RT7は、RICE28の中でも歴史ある定番モデルとして知られ、柔らかめのフレックス設定により、板をしならせる動作が非常にやりやすいのが特徴です。
そのため、プレスの維持や低速での細かいトリック操作において抜群の扱いやすさを発揮します。
一方でRT9は、RT7よりも硬めのフレックス設定になっており、強い反発力と高速域での安定感を持っています。 自ら板を踏み込んで強い反発を得る滑りや、スピードに乗った状態でのトリックに適していると言えます。
まずは、この「しなやかさ重視のRT7」と「反発力重視のRT9」という大枠のイメージを持つことが、選び方の第一歩となります。
キャンバー形状と有効エッジの特性
スノーボードの乗り味を大きく左右するキャンバー形状ですが、RT7とRT9はどちらも「フルキャンバー」を採用しています。
フルキャンバーは、ノーズとテールの接雪点付近にしっかりと圧がかかるため、雪面を捉えるグリップ力が強く、ターンやオーリーでの反発を得やすい形状です。
ただし、同じフルキャンバーでも、その味付けにはモデルごとのコンセプトが反映されています。
RT7は、接雪長や有効エッジのバランスが操作性を重視して設計されており、キャンバー特有のエッジの引っ掛かりを軽減しつつ、グリップ力を維持する工夫がなされています。
対してRT9は、有効エッジを最大限に活かしてカービングの切れ味や高さを出すための設計がなされていると考えられます。
スペック表を見比べると有効エッジの数値に大きな差はない場合が多いですが、実際に乗った時の感覚としては、RT9の方が雪面を長く捉えているような安定感を感じやすい傾向にあります。
フレックスの違いとトーションの操作性
板の硬さを表すフレックスと、ねじれの硬さを表すトーションは、RT7とRT9で明確に異なります。 以下の表に、一般的な感覚値としての比較をまとめました。
| 項目 | RT7 (アールティーセブン) | RT9 (アールティーナイン) |
|---|---|---|
| フレックス | 柔らかめ~ミドル | ミドル~やや硬め |
| トーション | 扱いやすく捻じれやすい | ハリがあり戻りが速い |
| 操作感 | 少ない力でも板が反応する | 踏み込むことで強い力が返る |
RT7は、センターフレックス(足と足の間の硬さ)が柔らかめに設定されているため、脚力に自信がない方や、板をねじって操作するトーションを使った動きを覚えたい方でも扱いやすいのが魅力です。
前述の通り、RT9は全体的にハリがあるため、トーションを使うにはある程度の入力が必要になります。
しかし、その分だけねじれから復元しようとする力が強く、クイックな切り返しや鋭い反発を生み出すことが可能です。
このトーションの特性の違いが、操作性の「オートマチック感(RT7)」と「マニュアル感(RT9)」の差につながっていると言えます。
搭載されるプレートや補強材の特徴
RICE28のボードには、足元の強度や反応を高めるためのプレートや、反発力を補助する補強材(リボン)が組み込まれています。
RT7には「HV2プレート」と呼ばれる、足元の角付けをサポートしつつも柔軟性を損なわないプレートが採用されることが多いです。
また、補強材として「G.D.R(G-Double Ribbon)」などが搭載され、しなやかな粘りを生み出しています。
一方、RT9には「グリップカービングプレート」のような、よりカービングや高速安定性を意識したプレートが搭載される傾向があります。
補強材についても、RT9にはカーボンリボンなどがセンターに配置され、板の反発速度と強度を高める役割を果たしています。
これらの内部構造の違いが、RT7の「粘り」とRT9の「弾き」という乗り味の決定的な差を生み出しているのです。
滑走性能を左右するソールの素材
滑走面の素材についても、モデルによってグレードや仕上げが異なる場合があります。
一般的に、RT9には「マイクログラファイト」などの高品質な素材が使用されていることが多く、静電気を抑えて春先の汚れた雪や湿雪でも高い滑走性を維持できるよう設計されています。
RT7も十分に滑走性の高いシンタードベースなどが採用されていますが、RT9は「高速域でのライディング」を想定しているため、より滑走速度に直結するハイスペックなソール材が奢られているケースが見受けられます。
もちろん、どちらのモデルも定期的なホットワックスなどのメンテナンスを行うことで、国産ボードならではの素晴らしい走りを体感できることは間違いありません。ソールの良さは、アプローチでの加速や緩斜面でのストレス軽減に大きく貢献します。
重量の違いとスイングウエイトの軽さ
RICE28のボードは、オガサカ工場で生産されており、非常に軽量であることで有名です。 RT7とRT9に関しても、どちらも業界トップクラスの軽さを誇りますが、乗り味としての「重さの感じ方」には微妙な違いがあります。
RT7はフレックスが柔らかいため、取り回しが非常に軽く感じられ、スイングウエイト(板を回転させた時に感じる重さ)も極めて軽い印象を受けます。 まるで板を履いていないかのような軽快さは、長時間のグラトリ練習でも疲れにくいというメリットにつながります。
対してRT9は、RT7に比べると若干のしっかり感があるため、手で持った時の重量差以上に、滑走時には「安定感のある重み」を感じるかもしれません。 とはいえ、他メーカーの同等スペックの板と比較すれば圧倒的に軽量です。
この軽さは、高回転スピンを狙う際のアドバンテージとなるだけでなく、リフト乗車時の足への負担軽減にも役立ちます。
RICE28のRT7とRT9の比較と違い:スタイル編
低速でのプレスやバター系のやりやすさ
スノーボードの遊び方として人気の高い、低速域でのプレスやバター系のトリックに関しては、RT7に軍配が上がります。
RT7のしなやかなフレックスは、体重移動だけでノーズやテールを簡単に持ち上げることができ、その状態をキープする「粘り」が強いためです。
RT9でもプレスやバターは可能ですが、板の反発が強いため、押さえ込むのに相応の技術と脚力が必要になります。油断すると板が元の形状に戻ろうとして、プレスが弾かれてしまうことがあるかもしれません。
したがって、低速でねっとりとした動きを楽しみたい、あるいはマニュアル系のトリックを極めたいという方には、RT7の特性が非常にマッチすると考えられます。
グラトリでの弾き系と乗り系の相性
グラトリ(グラウンドトリック)といっても、そのスタイルは多様です。 板の反発を使って高く飛ぶ「弾き系」と、板をしならせて回る「乗り系(ソネなど)」で相性が分かれます。
RT7は、乗り系トリックとの相性が抜群です。 板のセンターが柔らかいため、ドライブスピンやソネなどのねじれを利用する動きがスムーズに行えます。
また、ノーリー720などの高回転も可能ですが、タイミングを取りやすい「粘る反発」なので、弾くタイミングをつかむ練習にも最適です。
一方、RT9は弾き系トリックに特化した性能を持っています。 「パンッ」と弾けるような強い反発力があるため、タイミングさえ合えばRT7よりも高さのあるトリックが可能です。
ただし、乗り系の動きをする際は、しっかりと板を制御しないとエッジが抜けたり、板が暴れたりする可能性があるため注意が必要です。
高速ラントリやカービングの安定感
ゲレンデを高速で流しながらトリックを入れる「ラントリ」や、キレのあるターンを楽しむ「カービング」においては、RT9の性能が光ります。
RT9の張り強めのフレックスと足元のプレートは、スピードが出ても板がバタつきにくく、雪面をしっかりと捉え続けます。
そのため、安心してエッジに体重を預けることができ、切れ味鋭いターンからのトリックへの移行がスムーズに行えます。
前述の通り、RT7は柔らかめの設定であるため、超高速域や荒れたバーンでは板が叩かれてしまうことがあります。
もちろんRT7でもカービングは楽しめますが、速度域が上がれば上がるほど、RT9の持つ剛性と安定感が大きなアドバンテージとなってくるでしょう。
キレのあるライディングを目指すなら、RT9のポテンシャルが頼もしい味方になります。
高回転スピンに必要な反発力の差
スノーボードで540(5回転半)や720(7回転)といった高回転スピンを目指す場合、滞空時間と回転力を生み出す「反発力」が鍵となります。この点において、RT9が持つ高反発な特性は非常に有利です。
カーボンリボンなどの補強材が生み出す爆発的な反発は、スピンの初速を上げ、回転数を稼ぐのを助けてくれます。
RT7もしっかりとしたキャンバーボードなので高回転は可能ですが、RT9に比べると反発の返りがマイルドです。そのため、RT7で高回転を回すには、ライダー自身の先行動作や引き付けの技術がより重要になります。
RT9は、板の反発そのものが強いため、正しいタイミングで弾くことができれば、驚くほど楽に回れる感覚を味わえるかもしれません。
キッカーやパークでの着地性能
キッカー(ジャンプ台)やジブアイテムなどが設置されたパークでの使用を考える場合、着地(ランディング)の安定性も考慮すべき点です。
RT9はフレックスに張りがあるため、着地で多少バランスを崩しても、板の強さで耐えられる許容範囲が広い傾向にあります。
特にキッカーでの着地においては、このしっかりとした剛性が転倒を防ぐ助けとなります。
RT7は着地の衝撃を吸収しやすい柔らかさがありますが、大きなキッカーや高い位置からの着地では、板が潰れすぎてしまい、リカバリーが難しくなる場面があるかもしれません。
とはいえ、RT7は操作性が高いため、アプローチでの微調整やジブアイテムへの入りやすさは抜群です。 ビッグキッカーを攻めるならRT9、中級以下のキッカーやジブを流すならRT7といった使い分けも一つの考え方です。
初心者から上級者への推奨レベル
これまでの比較を踏まえると、それぞれのモデルが推奨するレベル感やターゲット層が見えてきます。
RT7は、スノーボードを始めたばかりの初心者から、グラトリを極めたい上級者まで、非常に幅広い層におすすめできるボードです。 「初心者が乗れば上達を助け、上級者が乗ればスタイルが出せる」と言われるほど、懐の深いモデルです。
一方、RT9は、ある程度滑れるようになった中級者から上級者の方に、特におすすめしたいモデルです。「もっと高く飛びたい」「もっと速く滑りたい」というステップアップの欲求に、その高性能で応えてくれます。
初心者がいきなりRT9に乗ると、その硬さと反発の速さに戸惑うこともあるかもしれませんが、最初から良い道具で練習したいという向上心のある方であれば、決して扱えないわけではありません。
まとめ:RICE28のRT7とRT9の比較と違い
- RT7は「しなやかで粘りがある」のが最大の特徴
- RT9は「高反発でハリがある」乗り味が魅力
- プレスやバター系トリックを重視するならRT7
- 高速ラントリや高回転スピンを目指すならRT9
- RT7は初心者から上級者まで扱いやすい
- RT9は中級者以上のステップアップに最適
- どちらもフルキャンバー形状でグリップ力は高い
- RT7は足元の操作性が高くねじりやすい
- RT9はカービングでの安定感が抜群に高い
- 重量はどちらも非常に軽量で疲れにくい
- RT9の方がソール素材のグレードが高い場合がある
- RT7は短めを選んで遊ぶスタイルにも合う
- RT9は適正サイズで性能を引き出すのがおすすめ
- グラトリのスタイル(乗り系or弾き系)で選ぶ
- 自分の目指す滑りに合わせて最適なモデルを決めよう