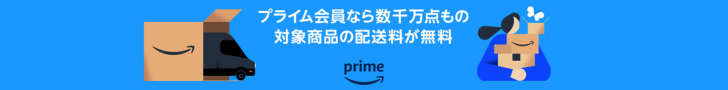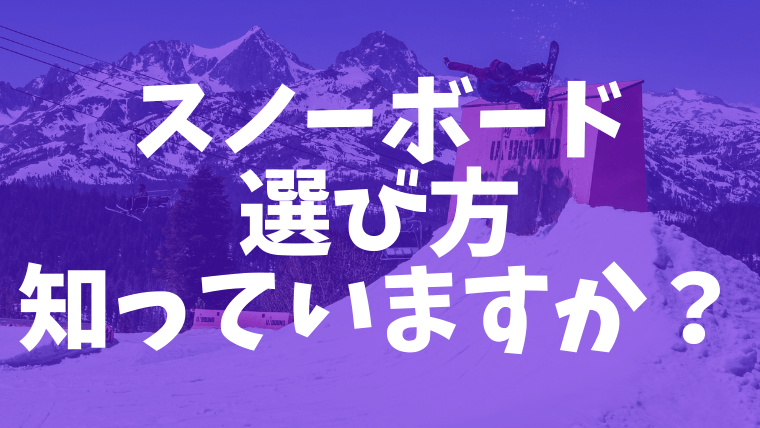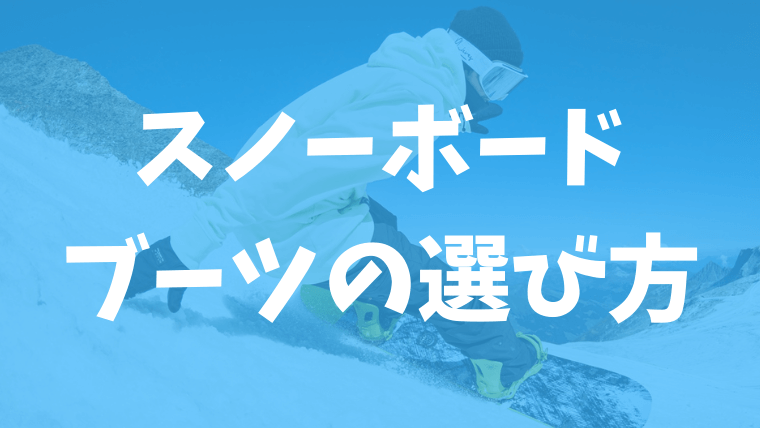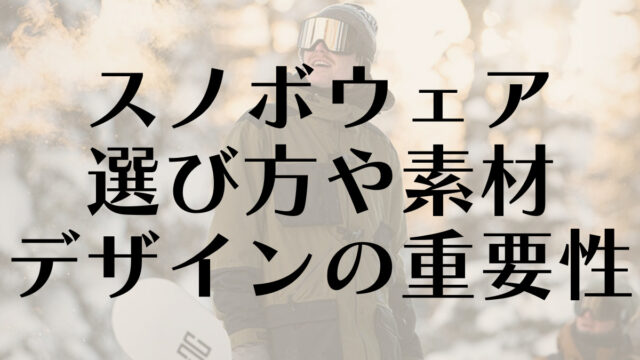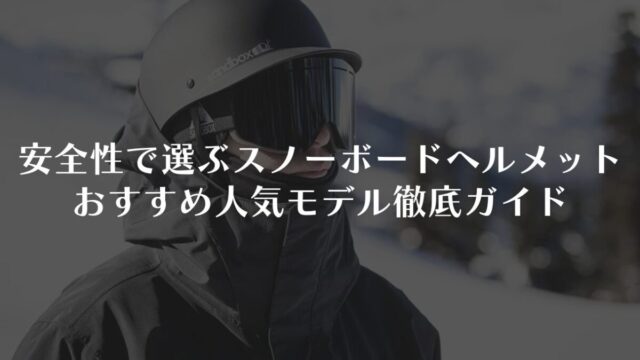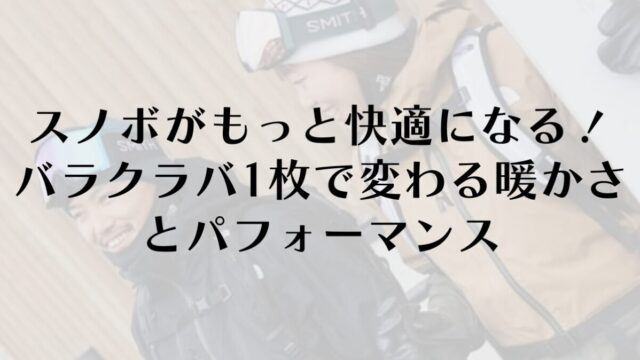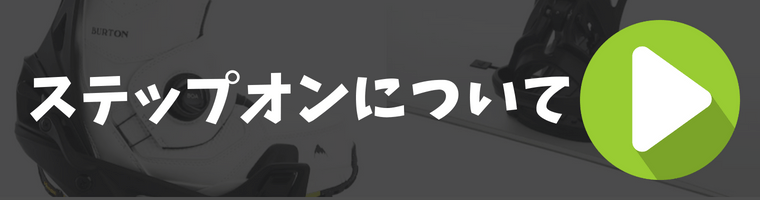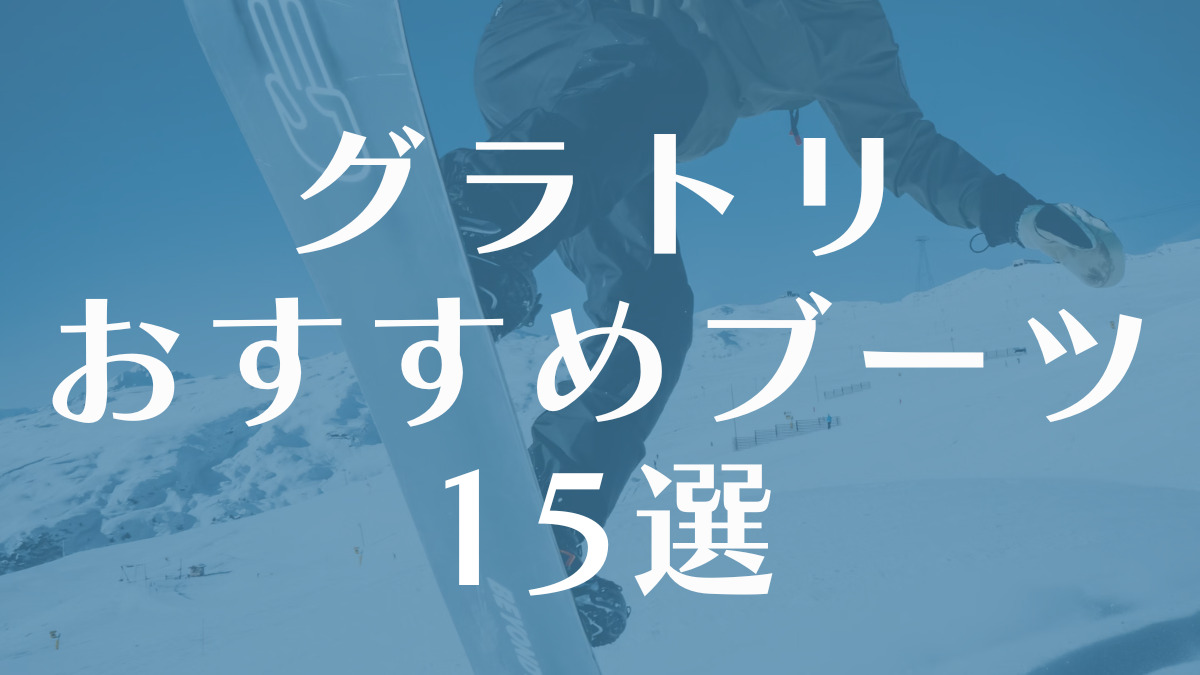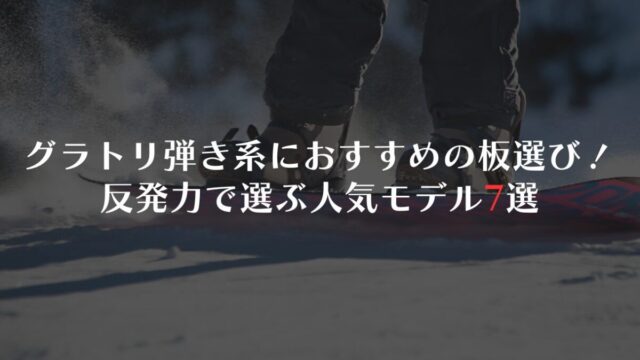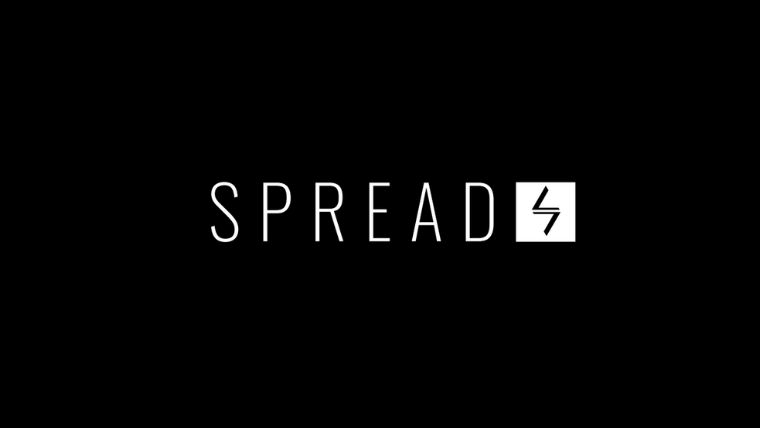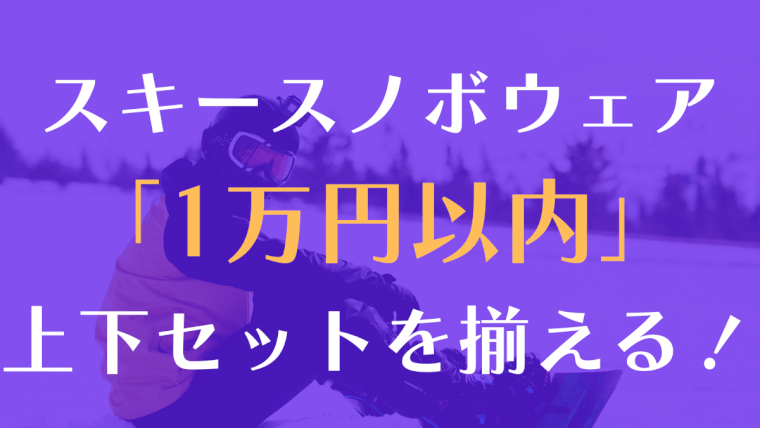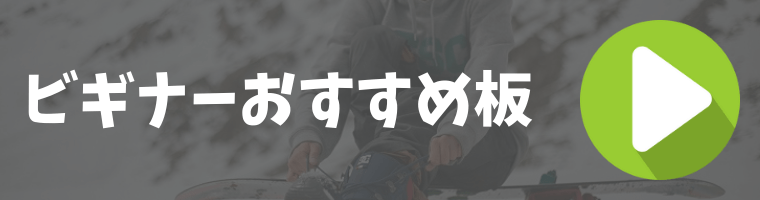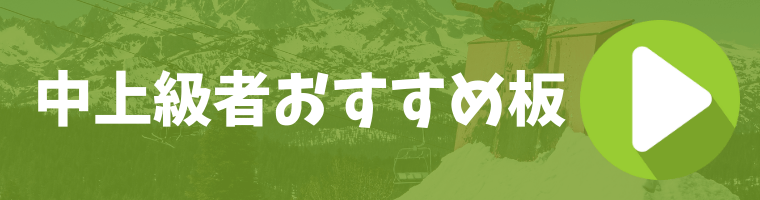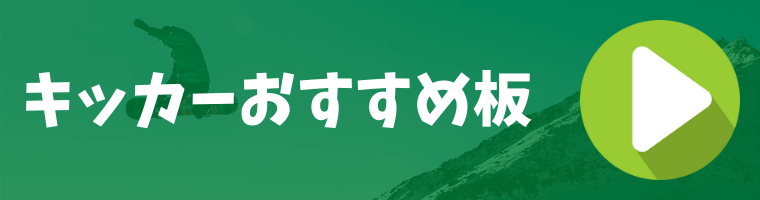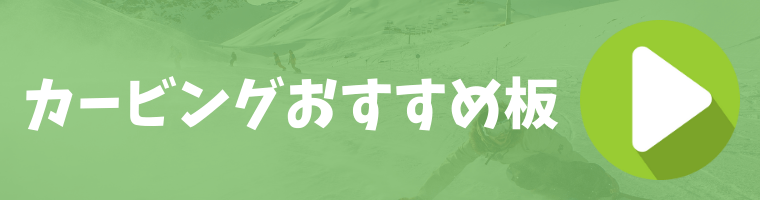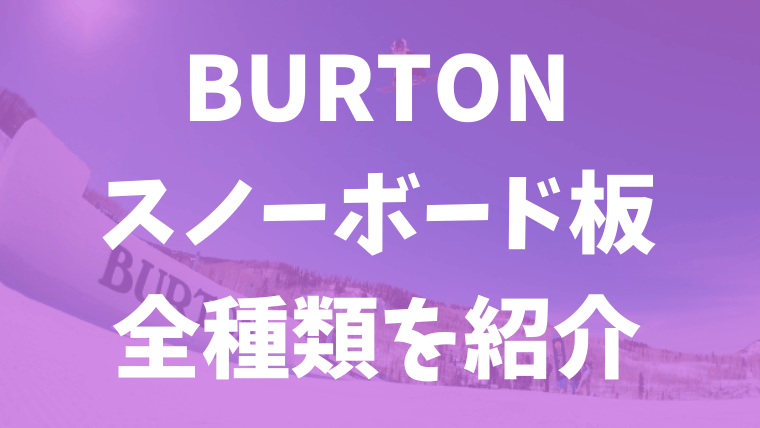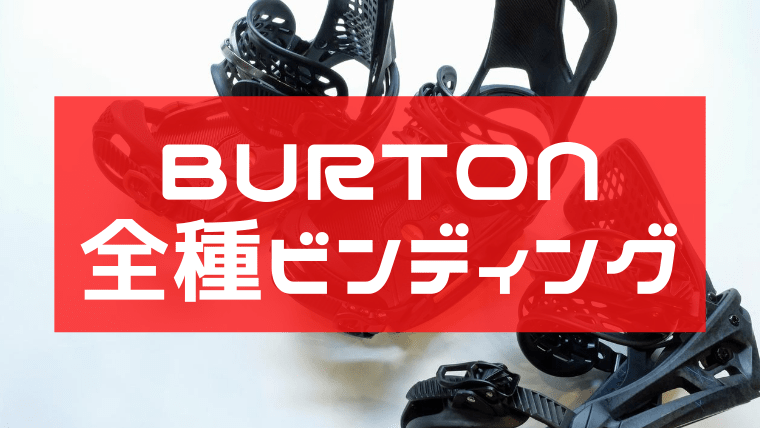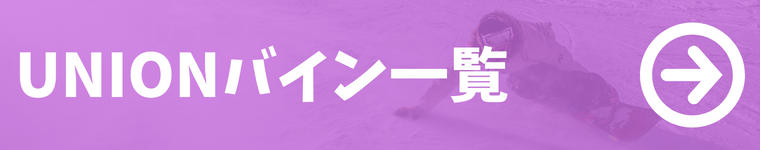【総まとめ】バックカントリー必須装備一覧!三種の神器からウェアまで完全網羅

バックカントリーの壮大な景色の中を滑走する、あの特別な体験に憧れを抱いている方も多いのではないでしょうか。しかし、管理されたスキー場とは異なり、手つかずの雪山には特有のリスクが潜んでいます。
そのため、安全に楽しむためには、適切なバックカントリーのギア装備を準備することが絶対に必要です。特に初心者の方は、何から揃えれば良いのか、その選び方に迷うこともあるかもしれません。
この記事では、バックカントリーに必須の装備を一覧でご紹介し、それぞれの役割や重要性を分かりやすく解説します。
雪山での安全を確保し、リスクを管理するための知識を深めていきましょう。この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- バックカントリーに必須となる全ての装備
- 各ギアが持つ具体的な役割と基本的な選び方のポイント
- 雪山での安全確保に最低限必要なアイテム
- 初心者が見落としがちな装備の重要性
バックカントリーで命を守る!最重要のアバランチギア
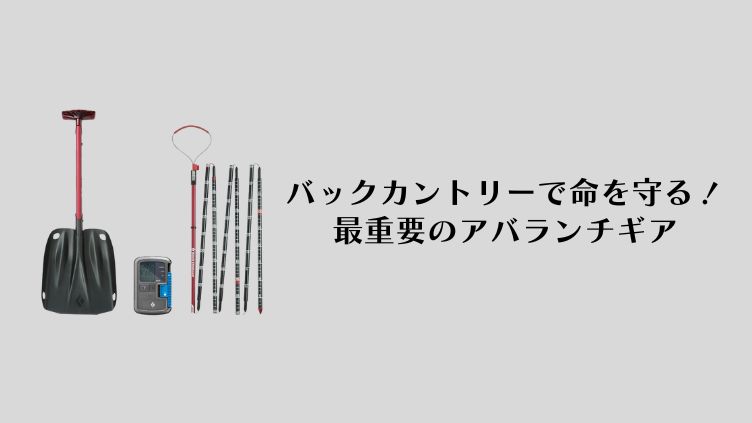
- 命を守るアバランチギア三種の神器
- 雪崩の捜索に不可欠なビーコン
- 救出作業に必須のショベル(プローブ)
命を守るアバランチギア三種の神器
バックカントリーエリアへ足を踏み入れる際に、絶対に携帯しなければならない装備が「アバランチギア三種の神器」と呼ばれる3つのアイテムです。
具体的には、ビーコン、ショベル(スノーショベル)、プローブ(ゾンデ棒)を指します。これらは、万が一雪崩に巻き込まれた際に、仲間を捜索し、救出するために不可欠な装備となります。
これらのギアを持たずにバックカントリーに入ることは、自分自身だけでなく、同行する仲間をも危険に晒す行為です。
例えば、雪崩に埋まった人間が生存できる時間は、埋没後15分までが約90%とされていますが、それを過ぎると急激に生存率が低下するというデータがあります。
このため、迅速な捜索と救出活動が求められ、三種の神器はそのための生命線と言えるでしょう。
もちろん、これらの装備を持っているだけで安全が保証されるわけではありません。いざという時に迅速かつ的確に使いこなせるよう、日頃から使用方法を繰り返し練習しておくことが極めて大切です。
雪崩の捜索に不可欠なビーコン
ビーコン(アバランチトランシーバー)は、雪崩に埋没した人の位置を特定するための小型の電波送受信機です。
バックカントリーに入る際は、全員がビーコンの電源を入れ、送信(Send)モードに設定して体に装着します。こうすることで、常に自身の位置を示す電波を発信し続ける状態になります。
万が一、仲間が雪崩に巻き込まれた場合、救助者は自身のビーコンを受信(Search/Receive)モードに切り替えます。
すると、埋没者が発信している電波を捉え、画面に表示される距離や方向の指示に従って埋没地点へと近づくことができます。
ビーコン選びのポイント
現在の主流は、複数のアンテナを内蔵したデジタル方式のビーコンです。アナログ方式に比べて捜索範囲が広く、方向や距離の精度も高いため、特別な理由がない限りデジタル方式を選ぶべきでしょう。
また、複数の埋没者がいる場合に、一人目の信号を一時的に無視して次の埋没者を捜索できる「マーキング機能」が付いていると、より迅速な救助活動につながります。
購入後は、必ず使い方を熟知し、出発前には仲間同士で送受信の動作確認を行う習慣をつけましょう。
救出作業に必須のショベル(プローブ)
ビーコンで埋没者の位置を絞り込んだ後、正確な埋没深度と位置を特定するためにプローブを使用し、最終的に雪を掘り起こして救出するためにショベルを用います。これら二つは、救出作業の最終段階で決定的な役割を果たします。
プローブ(ゾンデ棒)の役割と選び方
プローブは、折りたたみ式の長い棒で、これを雪に突き刺して埋没者を探し当てます。ビーコンで示されたエリアにプローブを刺し込み、人に当たった感触で位置を特定するのです。
素材はアルミ製とカーボン製があり、カーボン製の方が軽量ですが高価な傾向にあります。長さは240cmから320cm程度のものが一般的で、日本の雪の深さを考えると、270cm以上の長さがあると安心感が高まります。
ショベルの役割と選び方
ショベルは、雪崩で固まった雪を掘り出すために使用します。雪崩のデブリ(雪塊)は非常に硬く締まっているため、プラスチック製ではなく、強度のある金属製のブレード(刃)を持つショベルが必須です。
また、柄(シャフト)が伸縮し、握りやすいグリップが付いているモデルは、効率的に力を伝えることができ、迅速な掘り出し作業を可能にします。バックパックへの収納性も考慮し、分解してコンパクトになるモデルを選ぶのが一般的です。
滑走と登攀の要!バックカントリー関連ギア

- 全ての装備を収納するバックパック
- 滑走の主役、スキー・スノーボード
- 歩行と滑走を支えるブーツ
- 登攀に必須の滑り止めシール
- 硬い斜面で使うクトー(スキーアイゼン)
- 推進力とバランスを補助するストック
全ての装備を収納するバックパック
バックカントリー用のバックパックは、前述のアバランチギア三種の神器をはじめ、ウェア、水分、食料など、行動に必要な全ての装備を収納するための重要なアイテムです。
単に荷物を運ぶだけでなく、スキーやスノーボードを取り付けて持ち運ぶ機能や、雪山での使いやすさを考慮した様々な工夫が凝らされています。
容量は、日帰りの場合は30〜40リットル程度が一般的です。容量が小さすぎると必要な装備が収まらず、大きすぎると余分な重さで体力を消耗してしまいます。
バックカントリー用バックパックの主な機能
- アバランチツールポケット: ショベルやプローブを素早く取り出せるように、専用の収納スペースが設けられています。
- スキー/スノーボードキャリー: スキーやスノーボードをバックパックに固定して持ち運ぶためのストラップやアタッチメントが付いています。スキーはAフレームやダイアゴナル(斜めがけ)、スノーボードは縦に取り付けるタイプが主流です。
- 背面アクセス: バックパックを雪の上に置いた際に、背面側からメインの荷室にアクセスできる機能です。荷物が濡れにくく、取り出しやすいメリットがあります。
- アバランチエアバッグシステム: 近年注目されている安全装備で、雪崩に巻き込まれた際にハンドルを引くと、バックパックに内蔵されたエアバッグが展開します。これにより、雪の表面に浮き上がりやすくなり、完全埋没のリスクを低減させる効果が期待されます。(参照:BCA Japan公式サイト)
滑走の主役、スキー・スノーボード
バックカントリーで使用するスキーやスノーボードは、ゲレンデ用とは異なる特徴を持っています。主に、深雪での浮力を得るための形状や、登攀(とうはん)に対応するためのビンディング(バインディング)システムが挙げられます。
バックカントリースキー
スキーの場合は、ゲレンデ用よりも幅が広く、ロッカー形状(板の先端や後端が反り上がっている形状)が採用されているモデルが主流です。
これにより、パウダースノーでの浮力が得られ、快適な滑走が可能になります。
ビンディングは、登る際にはかかとが上がる「ウォークモード」に切り替えられるツアービンディングが必須です。
バックカントリー用スノーボード(スプリットボード)
スノーボードの場合は、登攀時に板を縦に二分割し、スキーのようにして使用できるスプリットボードが一般的です。
分割した板の裏にシールを貼り、専用のビンディングをウォークモードにすることで、スキーと同様に雪の上を歩いて登ることができます。
滑走時には再び板を一つに結合し、通常のスノーボードとして使用します。
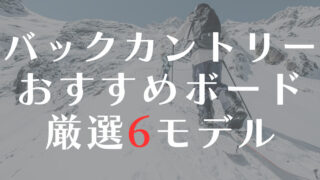


歩行と滑走を支えるブーツ
バックカントリー用のブーツも、滑走性能と歩行性能を両立させるための特別な機能を備えています。
スキーブーツは、足首の可動域を広げるための「ウォークモード」機能が搭載されています。登攀時にはこのモードに切り替えることで、足首がスムーズに動き、長時間のハイクアップでも疲れにくくなります。滑走時には再びスキーモードに戻し、足首をしっかりと固定します。
スノーボードブーツは、スプリットボードでの使用を想定し、一般的なフリースタイル用のブーツよりも硬めで、アイゼン(クランポン)の装着に対応しているモデルが多く見られます。
長時間の歩行でも快適性を損なわないよう、フィット感や防水性も重要な選択基準となります。
登攀に必須の滑り止めシール
シールは、スキーやスプリットボードの滑走面に貼り付ける滑り止めです。素材の表面がスキーが進む方向には滑り、逆方向には抵抗が生まれるように加工されており、これにより雪の斜面を後ろに滑ることなく登っていくことが可能になります。
素材は主にナイロン製、モヘア製、そして両者の混合タイプの3種類があります。
| 素材の種類 | グリップ力 | 滑走性 | 耐久性 |
|---|---|---|---|
| ナイロン | 高い | やや劣る | 高い |
| モヘア | やや劣る | 高い | やや劣る |
| 混合 | バランス型 | バランス型 | バランス型 |
初心者の方は、グリップ力と耐久性に優れるナイロン製か、バランスの取れた混合タイプから始めると扱いやすいでしょう。自分の板の形状に合わせてカットして使用するのが一般的です。
硬い斜面で使うクトー(スキーアイゼン)
クトーは、スキー用のアイゼンで、ツアービンディングに取り付けて使用します。シールだけではグリップが効かなくなるような、硬く凍った雪面(アイスバーン)や急斜面を登る際に絶大な効果を発揮します。
ビンディングのかかとを上げるヒールリフターと連動して雪面に食い込む仕組みになっており、これにより安全かつ効率的に登高を続けることができます。春先のザラメ雪が凍結した斜面などでは、クトーがなければ進めない状況も少なくありません。
クトーには様々な幅があるため、自分のスキーのウエスト幅に合ったサイズを選ぶ必要があります。これもまた、安全マージンを確保するための重要な装備の一つと考えられます。
推進力とバランスを補助するストック
ストック(ポール)は、登りでの推進力を生み出し、体のバランスを保つために重要な役割を果たします。特に、急な斜面や不整地での安定性を高める効果は大きいでしょう。
バックカントリー用としては、長さを調整できる伸縮式のストックが一般的です。登りの際は少し長めに、滑走時やトラバース(斜面を横切ること)の際は短めに調整することで、様々な状況に対応できます。
また、深雪に対応できるよう、大きめのバスケット(リング)が付いているモデルを選ぶのがおすすめです。スプリットボーダーも、登攀時には必ずストックを使用します。
バックカントリーで快適性と安全性を高めるウェアとアクセサリー

- レイヤリングが基本のウェア
- 体温を維持するインサレーション(防寒着)
- 頭部を守るヘルメットの重要性
- 視界を確保するゴーグル
- 防水性と保温性に優れたグローブ
レイヤリングが基本のウェア
バックカントリーでは、行動中に大量の汗をかき、休憩中には急激に体温が奪われるなど、体温の変化が激しくなります。
そのため、ウェアはレイヤリング(重ね着)によって、こまめに体温調節を行うのが基本です。
主に、ベースレイヤー、ミドルレイヤー、アウターレイヤー(シェル)の3層で構成されます。
| レイヤーの種類 | 主な役割 | 素材の例 |
|---|---|---|
| ベースレイヤー | 汗を素早く吸収し、肌面をドライに保つ | 化繊(ポリエステルなど)、ウール |
| ミドルレイヤー | 体温を保持し、暖かさを確保する | フリース、薄手のダウン、化繊中綿 |
| アウターレイヤー | 雪や風、雨から体を守る | 防水透湿性素材(ゴアテックスなど) |
各レイヤーのポイント
- ベースレイヤー: 汗冷えを防ぐ最も重要な層です。コットン(綿)は乾きが遅く体を冷やす原因になるため、絶対に避け、速乾性に優れた化繊や、濡れても保温性を失いにくいウール素材を選びましょう。
- ミドルレイヤー: 行動中の気温や運動量に応じて、フリースやインサレーション(化繊中綿ジャケットなど)を使い分けます。複数枚を調整できるように準備すると良いでしょう。
- アウターレイヤー: 防水性、防風性、そして内部の湿気を外に逃がす透湿性を備えた素材が必須です。脇の下に換気のためのジッパー(ベンチレーション)が付いていると、さらに体温調節がしやすくなります。
体温を維持するインサレーション(防寒着)
インサレーションとは、ダウンや化繊の中綿を使用した保温着のことです。
前述のミドルレイヤーとして着用することもありますが、それとは別に、休憩中や天候の急変時、あるいは万が一のビバーク(野営)に備えて、より保温性の高いものをバックパックに必ず携行します。
行動中は暑くて着ていられなくても、立ち止まった瞬間に汗が冷え、一気に体温が奪われます。低体温症は命に関わる重大なリスクであり、それを防ぐためにインサレーションは不可欠です。
ダウンは軽量で保温性が高いですが、濡れると保温力が著しく低下するデメリットがあります。一方、化繊中綿は濡れに強く、手入れがしやすいというメリットを持つため、雪山での使用には化繊を選ぶ人も少なくありません。
頭部を守るヘルメットの重要性
バックカントリーでは、転倒による頭部への衝撃だけでなく、滑落、木や岩への衝突、雪や氷の塊の落下など、様々なリスクが潜んでいます。これらのリスクから頭部を保護するために、ヘルメットの着用は今や常識となっています。
ゲレンデ以上に危険が多い環境だからこそ、自分の身を守るための最低限の装備と考えるべきです。
選ぶ際は、スキー・スノーボード用に設計され、通気性や軽量性、ゴーグルとの相性などを考慮すると良いでしょう。また、登攀時の暑さを考慮して、ベンチレーション機能が充実しているモデルが快適です。
視界を確保するゴーグル
山での天候は非常に変わりやすく、吹雪や強い日差しなど、目まぐるしく状況が変化します。ゴーグルは、雪や風、そして紫外線から目を守り、いかなる状況でも良好な視界を確保するための必須アイテムです。
レンズの色によって、対応できる天候が異なります。例えば、オレンジ系やピンク系のレンズは、曇天や降雪時でも雪面の凹凸を認識しやすく、グレー系やミラー系のレンズは、晴天時の強い日差しを和らげる効果があります。
天候に合わせてレンズを交換できるモデルや、光の量に応じてレンズの明るさが自動で変化する調光レンズを搭載したモデルも人気です。予備のレンズを携行すると、より安心感が増すでしょう。
防水性と保温性に優れたグローブ
手は、体の中でも特に冷えやすい末端部分であり、一度かじかんでしまうと様々な作業に支障をきたします。そのため、グローブは防水性と保温性に優れたものを選ぶことが大切です。
行動中は汗をかきやすいため、透湿性を備えた素材が望ましいです。また、登攀時や細かい作業を行う際に使う薄手のグローブと、滑走時や休憩中に使う保温性の高いグローブを複数用意し、状況に応じて使い分けるのが一般的です。
予備のグローブを必ずバックパックに入れておくことも、濡れた際の交換用として、また紛失した際のリスク管理として非常に重要となります。
バックカントリーの万が一に備える!その他の重要装備
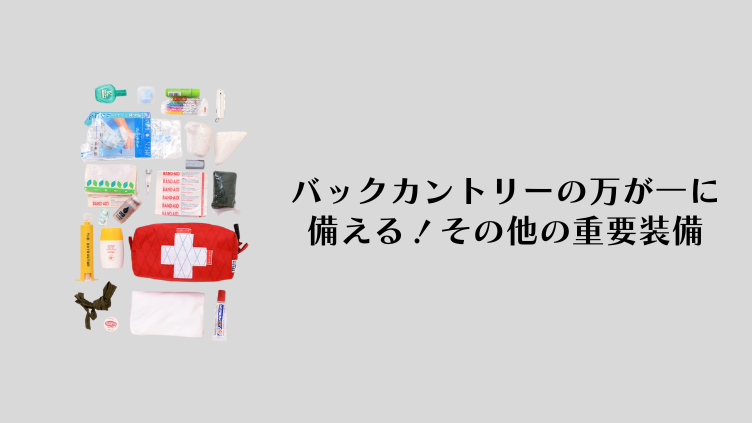
- 怪我に備えるファーストエイドキット
- ギアトラブルに対応するリペアキット
- 現在地を把握する地図・コンパス
- 日没に備えるヘッドライト
- 緊急時用のツェルト・エマージェンシーシート
- エネルギー補給のための行動食・飲み物
怪我に備えるファーストエイドキット
バックカントリーエリアでは、小さな切り傷や捻挫であっても、迅速な対応が求められます。救助隊がすぐに到着できる環境ではないため、自分たちで応急処置ができるように、ファーストエイドキットを必ず携行しましょう。
中身は、市販のキットをベースに、自分に必要なものを追加していくのがおすすめです。
ファーストエイドキットの内容例
- 絆創膏(各種サイズ)
- 滅菌ガーゼ、包帯
- テーピングテープ(伸縮・非伸縮)
- 消毒液、ウェットティッシュ
- 痛み止め、常備薬
- ポイズンリムーバー
- ハサミ、毛抜き
これらの内容に加えて、自身の医療知識やグループの構成に応じて内容をカスタマイズすることが望まれます。
ギアトラブルに対応するリペアキット
フィールドでビンディングのネジが緩んだり、ストラップが切れたりといったギアの故障は、時として行動不能につながる深刻な事態を引き起こします。そうした不測の事態に備え、簡易的な修理ができるリペアキットを携帯することが賢明です。
リペアキットの内容例
- マルチツール: ドライバーやレンチ、ナイフなどが一つになった工具。
- ダクトテープ: あらゆる補修に使える強力な粘着テープ。ストックなどに巻きつけておくと便利です。
- 結束バンド(タイラップ): 切れたストラップなどを応急的に固定できます。
- 予備のストラップやネジ: 自分の使っているギアに合ったもの。
これだけの準備があるだけで、多くのトラブルに対処でき、安全に下山できる可能性が高まります。
現在地を把握する地図・コンパス
スマートフォンやGPSデバイスの地図アプリは非常に便利ですが、電子機器はバッテリー切れや低温によるシャットダウン、故障のリスクが常に伴います。
そのため、アナログなナビゲーションツールである地形図とコンパスは、バックアップとして必ず携行し、使い方を習熟しておく必要があります。
ホワイトアウト(濃霧や吹雪で視界が真っ白になること)などで視界が効かなくなった場合、これらのアナログツールが唯一の頼りになることも少なくありません。
事前に地図読みの講習会に参加するなどして、基本的な使い方をマスターしておくことを強く推奨します。
日没に備えるヘッドライト
「日帰りの予定だからライトは不要」と考えるのは非常に危険です。天候の悪化や道迷い、怪我人の発生など、予期せぬトラブルによって下山が予定よりも大幅に遅れることは十分に考えられます。
日没後の山中では、ヘッドライトがなければ行動することはほぼ不可能です。軽量でコンパクトなモデルで構いませんので、必ずバックパックに入れ、予備の電池も忘れずに携行しましょう。これは、安全登山の基本中の基本と言えます。
緊急時用のツェルト・エマージェンシーシート
ツェルトやエマージェンシーシートは、万が一のビバークや、怪我で動けなくなった人の保温に使用する、軽量でコンパクトな緊急用装備です。
- エマージェンシーシート: 体から発する熱を反射して体温低下を防ぐ、薄いシート状のものです。非常に軽量でかさばらないため、必ず持っておきたいアイテムです。
- ツェルト: 簡易的なテントの役割を果たすもので、複数人が中に入って風雪をしのぐことができます。
これらの装備は、使う事態にならないことが一番ですが、持っているというだけで大きな安心感につながります。お守りとしてではなく、命を守るための重要な装備として携帯してください。
エネルギー補給のための行動食・飲み物
バックカントリーは非常に体力を消耗するアクティビティです。エネルギー切れ(ハンガーノック)を防ぐため、こまめにエネルギー補給ができる行動食と、十分な量の水分を準備することが不可欠です。
行動食のポイント
行動食は、休憩中に素早く食べられるもの、カロリーが高く、凍りにくいものが適しています。ナッツやドライフルーツ、エナジーバー、ジェルなどが一般的です。少し多めに持っていくことで、不測の事態にも備えることができます。
飲み物のポイント
水分補給は非常に重要です。冬でも行動中は大量の汗をかくため、1.5〜2リットル程度を目安に準備しましょう。
水筒(ボトル)は、凍結を防ぐために保温性の高い魔法瓶タイプがおすすめです。温かい飲み物を用意しておくと、体が温まり、精神的な安らぎにもつながります。
まとめ:適切なバックカントリーのギア装備で安全な山行を
この記事では、バックカントリーに挑戦する上で必要となる様々なギアや装備について解説してきました。最後に、安全な山行のために覚えておくべき重要なポイントをまとめます。
- アバランチギア三種の神器は絶対に携帯する
- ビーコンはデジタル方式を選び操作に習熟する
- ショベルとプローブは迅速な救助活動の要
- バックパックは30〜40リットルが目安で専用機能を確認する
- スキーやスノーボードは深雪に対応したモデルを選ぶ
- ブーツは歩行モード付きが登攀を楽にする
- シールは斜面を登るための必須アイテム
- クトーは硬い雪面での滑落を防ぐ
- ウェアは3層のレイヤリングで体温を調節する
- 汗冷えを防ぐためベースレイヤーは化繊かウールを選ぶ
- 休憩時の低体温症を防ぐインサレーションを携行する
- 頭部を保護するためヘルメットは必ず着用する
- ゴーグルは天候に応じた視界確保に不可欠
- 予備を含め複数のグローブを準備する
- ファーストエイドキットとリペアキットで万が一に備える
- 地図とコンパスは電子機器のバックアップとして習熟する
- ヘッドライトと予備電池は日帰りでも必ず携帯する
- ツェルトは緊急時のシェルターとして命を守る
- 行動食と温かい飲み物でエネルギーを維持する
- 全ての装備は使い方を理解し練習しておくことが最も大切