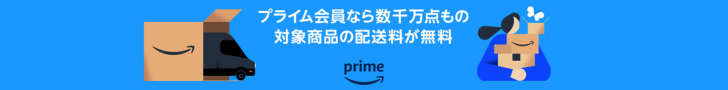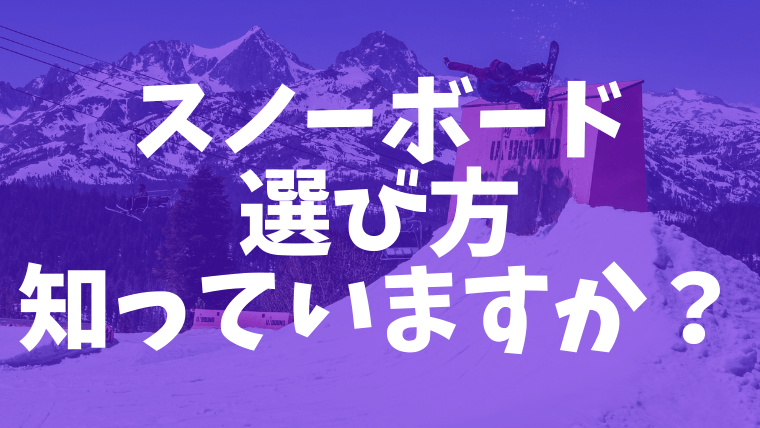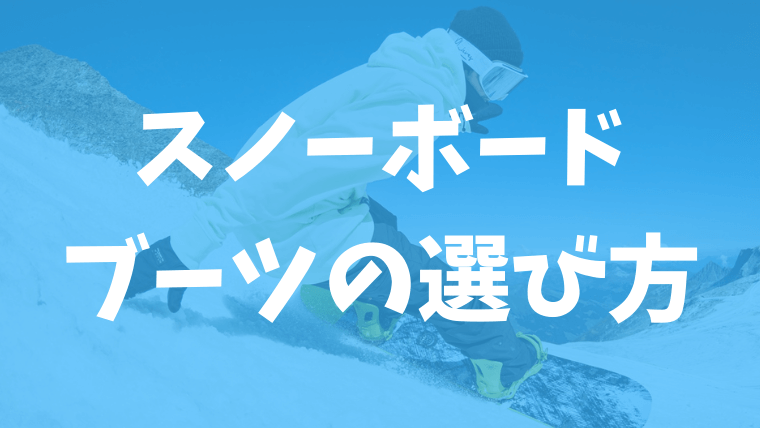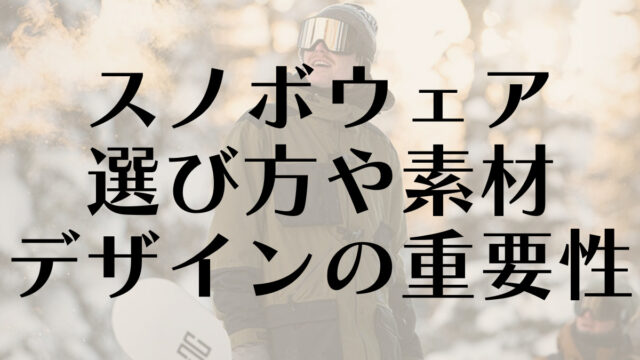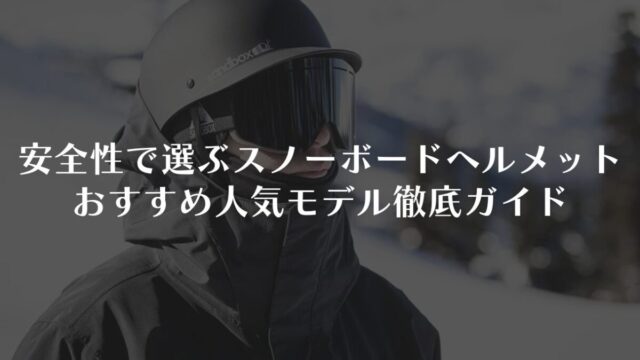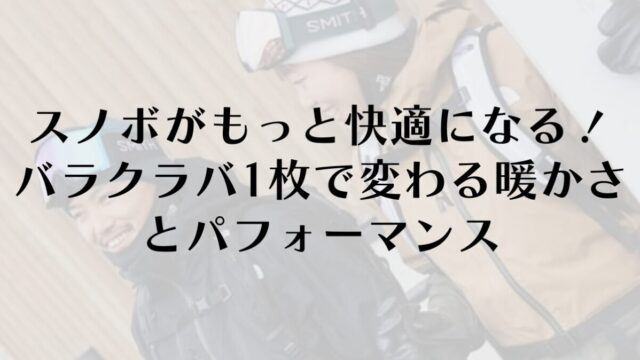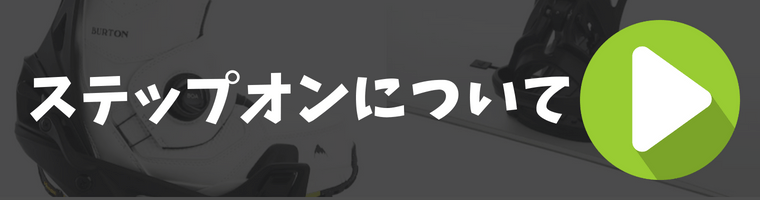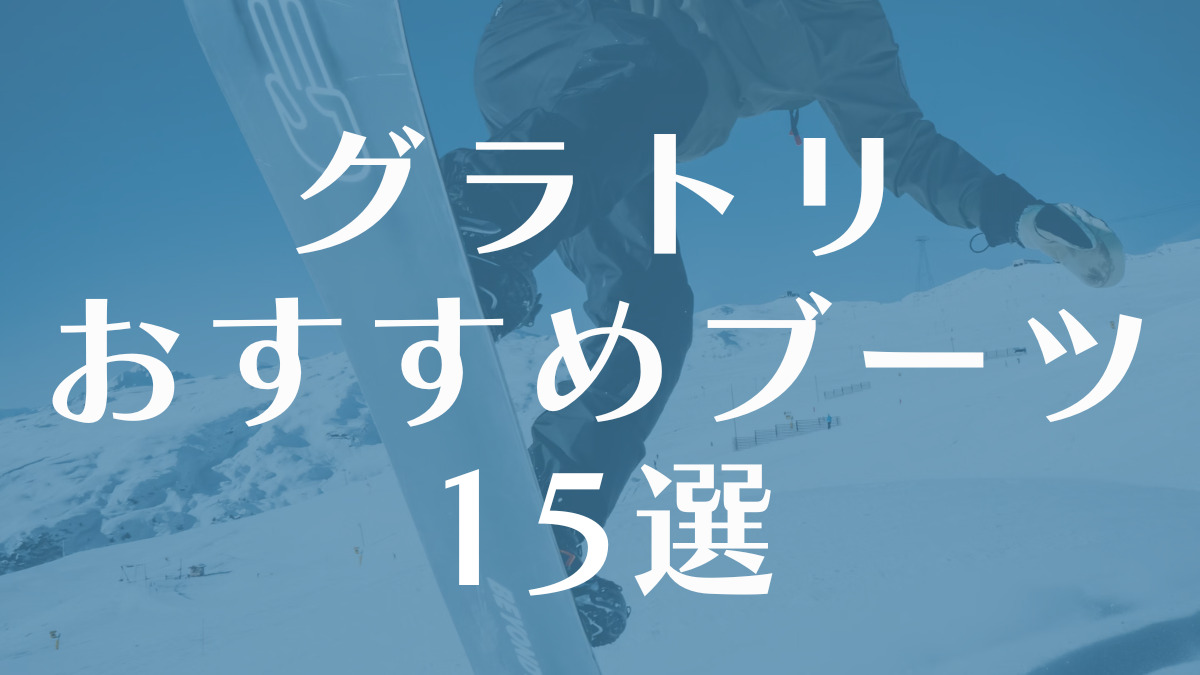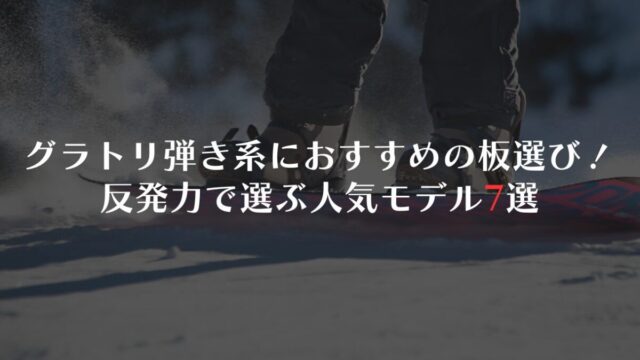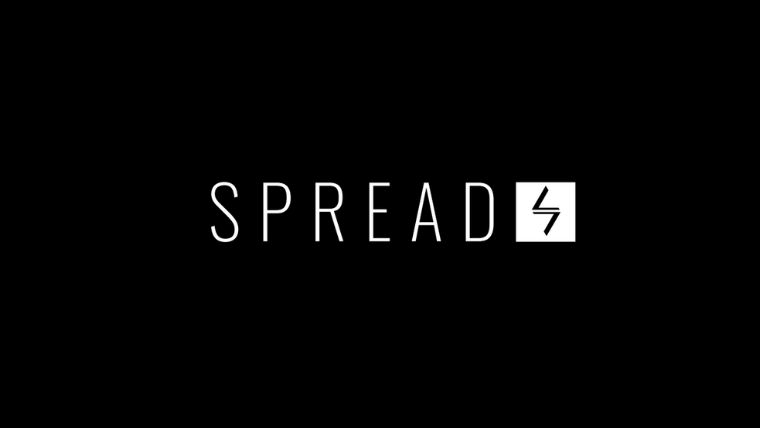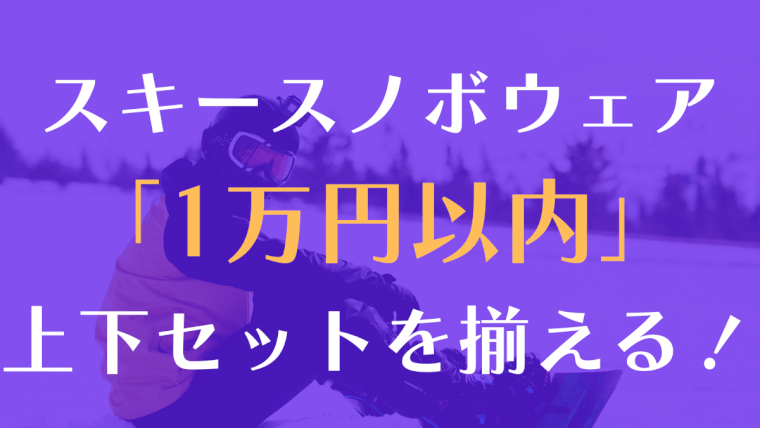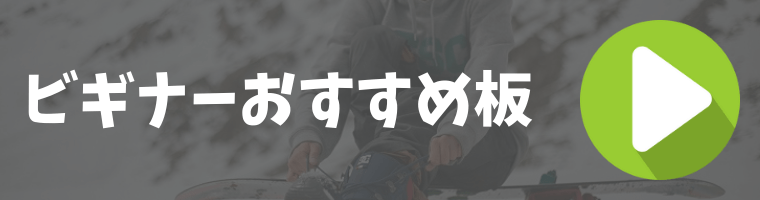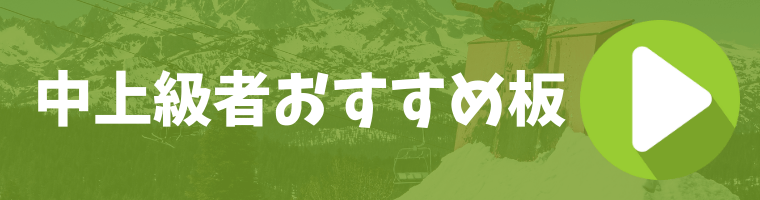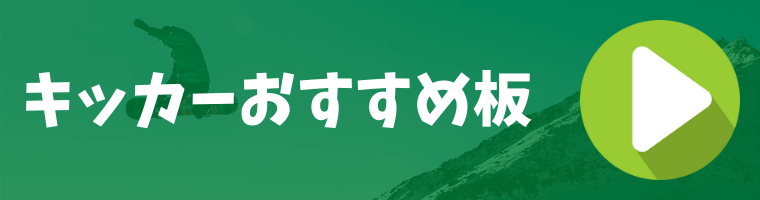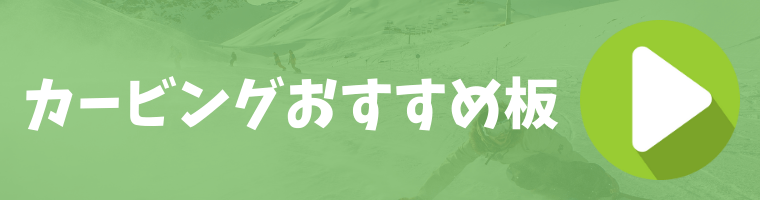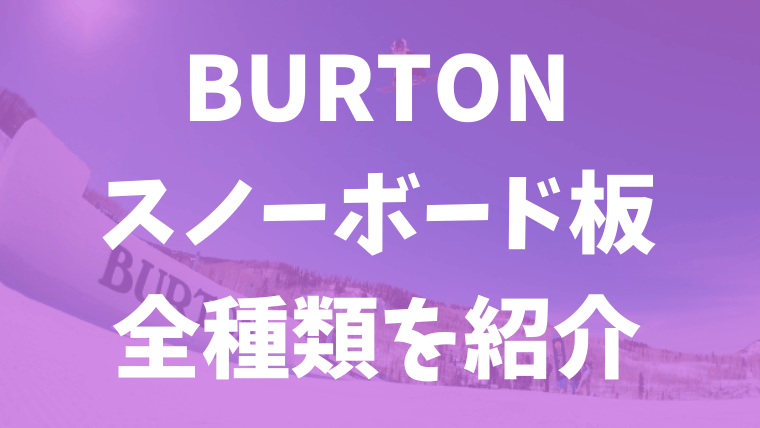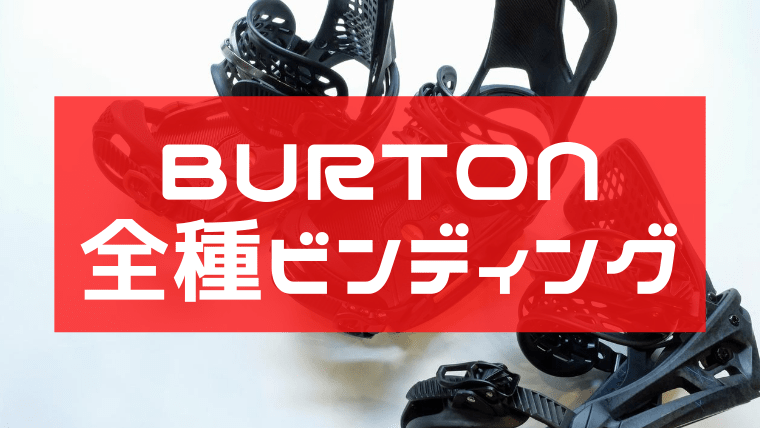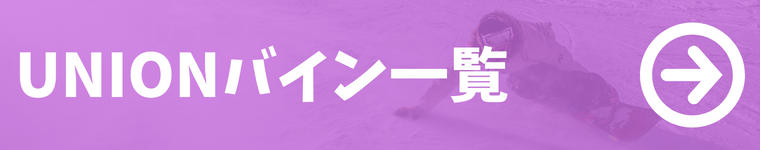ソリッドボードで始めるバックカントリー|装備や注意点を解説

手持ちのスノーボードで広大な自然の雪山を滑る、そんなバックカントリースノーボーディングに憧れを抱いている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ソリッドボードとスノーシューの組み合わせでバックカントリーを始めるために知っておきたい、スプリットボードとの違いから、必要な装備、登り方や滑り方の基本、そして最も重要な注意点まで、網羅的に解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。
- ソリッドボードでバックカントリーを始めるための基本知識
- 必要な装備の種類とそれぞれの選び方のポイント
- スノーシューを使った登り方や安全なルート選びのコツ
- 雪山に潜む危険性と、それらに対するリスクマネジメント
ソリッドボードでバックカントリーを始める基本知識

- スプリットボードとの根本的な違い
- ソリッドボードを選ぶメリットとデメリット
- 最低限必要な装備のチェックリスト
- バックカントリー用スノーシューの選び方
- ボードを背負うザックの選び方
- 重要なアバランチギア3点セット
スプリットボードとの根本的な違い
バックカントリーに挑戦する際、まず比較対象となるのがスプリットボードです。両者の最も大きな違いは、雪山を登る際の機動力と滑走時の構造にあります。
スプリットボードは、その名の通り滑走時には一枚のボードですが、登行時には左右2つに分割してスキーのように使用できる特殊なスノーボードです。
専用のシール(滑り止め)を板の裏に貼り付けることで、スキーのように板を雪面から大きく持ち上げることなく、滑らせるようにして効率的に登ることが可能です。
一方、ソリッドボードはゲレンデで使う一般的な一枚板のスノーボードを指します。ソリッドボードでバックカントリーの斜面を登るためには、スノーシューを足に装着し、スノーボード本体はザックに背負って運ぶのが基本スタイルとなります。
このように、登行スタイルに明確な違いがあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
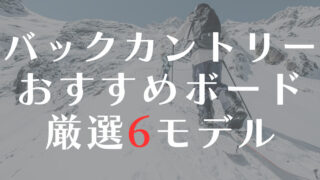
スプリットボードとソリッドボードの比較
| 項目 | スプリットボード | ソリッドボード |
|---|---|---|
| 登行方法 | ボードを2つに分割し、スキーのように登る | スノーシューを履き、ボードは背負って登る |
| 機動力 | 登行効率が高く、深い雪でも進みやすい | スノーシューの浮力に依存し、ラッセルが大変な場合がある |
| 滑走性能 | 分割構造のため、ややフレックスやトーションが硬く感じることがある | 一枚板ならではの一体感と本来の乗り味を楽しめる |
| 初期費用 | 高価(ボード、専用ビンディング、シールなどが必要) | 比較的安価(手持ちのボードを活用でき、スノーシューなどを追加購入) |
| 重量 | 登行時に足元が重くなる | 登行時に背中(ザック)が重くなる |
ソリッドボードを選ぶメリットとデメリット
ソリッドボードでバックカントリーを始めることには、魅力的な点と、理解しておくべき点の両方があります。
メリット
最大のメリットは、初期費用を抑えられることでしょう。すでに愛用しているスノーボードやビンディング、ブーツをそのまま活用できるため、新たに追加で購入するのはスノーシューや安全装備など、比較的少ないアイテムで済みます。
また、滑走性能においては、一枚板ならではの一体感とレスポンスの良さが挙げられます。
分割構造を持つスプリットボードと比較して、フレックスやトーションが自然であり、ゲレンデで滑るのと同じ感覚でパウダーライディングを存分に楽しむことが可能です。乗り慣れたボードで手つかずの斜面を滑る感覚は格別と言えます。
デメリット
一方で、デメリットとして最も大きいのは登行時の身体的な負担です。スノーボードをザックに背負って登るため、肩や腰への負荷が大きくなります。特に長時間のハイクアップでは、この重さが体力を消耗させる大きな要因となり得ます。
加えて、スプリットボードに比べて登行効率が劣る点も否めません。スノーシューは足を一歩ずつ持ち上げて進むため、スキーのように滑らせて登るスプリットボードよりもエネルギーを消費します。
深いパウダースノーでは、ラッセル(雪をかき分けて進むこと)の負担も大きくなる傾向があります。
最低限必要な装備のチェックリスト
バックカントリーは自己責任の世界です。ゲレンデとは異なり、コース管理やパトロールは存在しません。そのため、自分の身を守るための装備を万全に整えることが絶対条件となります。
スノーボーディングギア
| カテゴリ | 装備名 | 備考 |
|---|---|---|
| ボード類 | ソリッドボード、ビンディング、ブーツ | 普段使い慣れているもので問題ありませんが、パウダー向けのモデルが推奨されます |
| ウェア | アウター(ジャケット、パンツ)、ミドルレイヤー、ベースレイヤー | 防水透湿性に優れ、体温調節がしやすいレイヤリングが基本です |
| アクセサリー | ゴーグル、サングラス、ヘルメット、グローブ、ビーニー | 天候の変化に対応できるよう、予備のゴーグルやグローブがあると安心です |
バックカントリーギア
| カテゴリ | 装備名 | 備考 |
|---|---|---|
| 登行用具 | スノーシュー、ストック(ポール) | 伸縮可能で、大きなバスケットが付いたモデルが適しています |
| 安全装備 | ビーコン、ショベル、プローブ | アバランチギア3点セットと呼ばれ、絶対に携帯が必要です |
| ザック | バックカントリー用ザック | 30〜40L程度が一般的。ボードやスノーシューを取り付けられるものを選びます |
| その他 | 救急セット、ヘッドランプ、地図、コンパス/GPS、携帯電話(予備バッテリー) | 万が一の事態に備え、必ず携帯してください |
バックカントリー用スノーシューの選び方
ソリッドボードでのバックカントリーにおいて、スノーシューは登りの成否を左右する重要なパートナーです。選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
主な選択基準は、浮力、グリップ力、そしてバインディングの使いやすさです。 浮力はスノーシュー本体の大きさで決まります。自分の体重と荷物の総重量に対応したモデルを選ばないと、雪に深く沈み込み、無駄な体力を消耗することになります。
一般的に、新雪やパウダースノーを歩くことが多い場合は、より大きなサイズが推奨されます。
グリップ力は、スノーシューの裏側に付いているクランポン(爪)の性能に依存します。硬い雪面や氷化した斜面を登る際には、このクランポンの食い込みが安全に直結します。登坂性能を重視するならば、つま先だけでなく、側面にもクランポンが付いているモデルが安心です。
また、かかと部分を持ち上げて傾斜を楽に登るための「ヒールリフター」という機能が付いているかも確認しましょう。長時間の登りでは、この機能の有無が疲労度を大きく左右します。
ボードを背負うザックの選び方
バックカントリー用のザックは、単に荷物を運ぶだけでなく、スノーボードやスノーシューといった大きなギアを安全かつ快適に運搬する機能が求められます。
容量は日帰りであれば30〜40リットルが一般的です。アバランチギアや防寒着、食料などを収納するのに十分な大きさと言えます。
選ぶ上で最も大切なのは、スノーボードを確実に固定できるキャリーシステムを備えているかという点です。ボードを縦に取り付けるタイプと、横に取り付けるタイプがありますので、自分の使いやすい方を選びましょう。
さらに、アバランチギアを素早く取り出すための専用コンパートメントがあるかも重要なチェックポイントです。万が一、雪崩に仲間が埋没してしまった場合、1分1秒を争う救助活動において、ショベルやプローブをスムーズに取り出せるかどうかは生死を分ける可能性があります。
他にも、背面アクセス機能(ザックを雪の上に置いたまま荷物を取り出せる)や、ヘルメットホルダー、ゴーグルポケットなどの機能があると、より快適性が向上します。
重要なアバランチギア3点セット
バックカントリーにおける最大のリスクは雪崩です。自分や仲間の命を守るために、ビーコン、ショベル(スコップ)、プローブ(ゾンデ)の3つは「三種の神器」とも呼ばれ、携帯が義務付けられています。
ビーコン(アバランチェ・トランシーバー)
電波を発信・受信する小型の機械です。行動中は全員が「送信(Send)」モードにしておき、万が一雪崩に埋まった人が出た場合、他のメンバーが「受信(Search)」モードに切り替えて、埋没者の発する電波を頼りに位置を特定します。
プローブ(ゾンデ)
ビーコンで埋没者の位置を大まかに特定した後、雪の中に差し込んで正確な場所と深さを特定するための折りたたみ式の棒です。長さは240cm以上のものが推奨されます。
ショベル(スコップ)
プローブで埋没者を発見した後、雪を掘り出して救助するための道具です。雪崩で固まった雪は非常に硬く、素手やスノーボードで掘ることは不可能なため、金属製のブレードを持つ頑丈なショベルが必須となります。
これらの装備は、持っているだけでは意味がありません。いざという時に迅速かつ正確に使えるよう、事前のトレーニングを必ず積んでおくことが極めて大切です。
実践で役立つソリッドボードのバックカントリー術
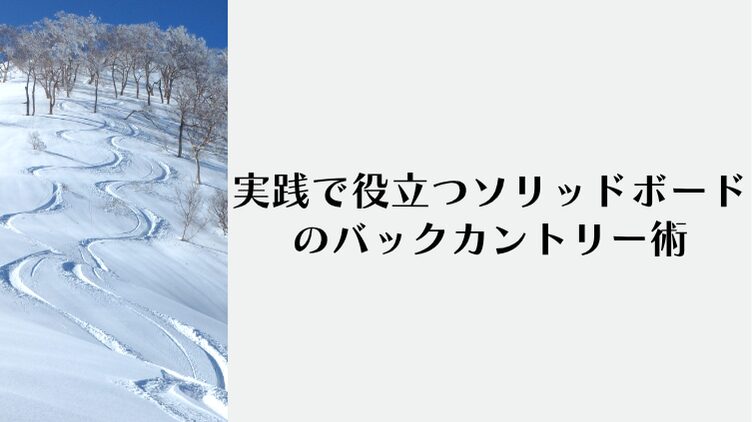
- スノーシューでの効率的な登り方のコツ
- 登りで注意したいハイクアップのルート
- 寒さから身を守るレイヤリングの基本
- 滑走準備(トランジション)の手順
- 雪崩ビーコンの操作方法と注意点
- 雪山の危険性とリスクマネジメント
スノーシューでの効率的な登り方のコツ
スノーシューでの歩行は、ただ闇雲に足を動かすだけではすぐに疲れてしまいます。効率的に登るためにはいくつかのコツがあります。
基本は、歩幅を小さく、一定のリズムで歩くことです。大股で歩くとバランスを崩しやすく、体力も消耗します。スキー場の圧雪された斜面とは違い、不均一な雪面を歩くことを意識してください。
急な斜面では、つま先を雪に蹴り込むようにして登る「キックステップ」が有効です。これにより、スノーシューのクランポンが雪面にしっかりと食い込み、安定した足場を作ることができます。
また、斜面を横切るように進む「トラバース」の際は、山側の足のエッジを意識的に利かせることが滑落防止につながります。
前述の通り、多くのバックカントリー用スノーシューには「ヒールリフター」という機能が備わっています。
これを立ち上げると、かかとが持ち上げられてふくらはぎの負担が軽減され、急登が格段に楽になります。地形に応じてこまめに活用するのがおすすめです。
登りで注意したいハイクアップのルート
バックカントリーにおいて、どこを登るかというルート選びは、滑り以上に重要であり、安全性に直結します。雪崩の危険性が最も低いルートを選択するのが大原則です。
一般的に、雪が溜まりやすい沢筋や、風下に大きな雪庇(せっぴ)ができているような場所は、雪崩のリスクが高いため避けるべきです。比較的安全とされるのは、木々が適度に生えている樹林帯や、風の影響を受けにくい尾根上です。
地形図を読み解き、等高線が密になっている急斜面や、上部に広大なオープンバーンが広がる斜面の直下などを避ける計画を立てることが求められます。
また、天候や気温の変化によって雪の状態は刻一刻と変わるため、常に周囲の状況を観察し、危険を感じたら引き返す勇気も必要です。経験豊富なガイドやリーダーと行動を共にすることが、安全なルート選びの第一歩となります。
寒さから身を守るレイヤリングの基本
バックカントリーでは、激しく汗をかくハイクアップと、風にさらされる稜線上での休憩や滑走時とで、体感温度が大きく変化します。この温度変化に効果的に対応するのが「レイヤリング」という考え方です。
レイヤリングは、機能の異なるウェアを3層に重ね着するのが基本となります。
- ベースレイヤー(肌着): 汗を素早く吸収し、肌面をドライに保つ役割を担います。汗冷えを防ぐために、速乾性に優れた化学繊維やウール素材のものが適しています。コットン(綿)は乾きにくく体を冷やすため、絶対に避けてください。
- ミドルレイヤー(中間着): 体温を保持し、暖かさを確保する保温層です。フリースや薄手のダウン、化繊インサレーションなどがこれにあたります。ハイクアップ中は脱いでおき、休憩時や滑走時に着用するなど、こまめに着脱して体温を調節します。
- アウターレイヤー(シェル): 雪や風、雨から体を守る最も外側の層です。防水性、防風性、そして内側の湿気を外に逃がす透湿性を備えていることが重要となります。
これらのレイヤーを状況に応じて脱ぎ着することで、常に体を快適な状態に保つことが、パフォーマンスの維持と低体温症などのリスク回避につながります。
滑走準備(トランジション)の手順
登り終えて滑走ポイントに到着したら、登行モードから滑走モードへと装備を転換する「トランジション」を行います。この作業をスムーズに行えるかどうかで、休憩時間を有効に使えるかが決まります。
手順は人によって多少前後しますが、一般的な流れは以下の通りです。
- ザックを下ろす: まずは背負っていたザックを安定した場所に下ろします。
- ボードの準備: ザックに固定していたスノーボードを外し、雪面に置きます。
- スノーシューを外す: ブーツからスノーシューを外し、ザックに収納または取り付けます。この際、ストック(ポール)も短く縮めてザックにしまいます。
- ウェアの調整: 必要であれば、ミドルレイヤーを着たり、アウターのベンチレーションを閉めたりして、滑走に備えた体温調節を行います。
- ビンディングの装着: ブーツにビンディングを装着します。パウダースノーの上では足元が不安定なため、落ち着いて確実に行うことが大切です。
これらの作業を効率よく行うためには、ザックの中のどこに何があるかを把握し、一連の動作を体に覚えさせておくことが有効です。仲間と協力し、手早く済ませることを心がけましょう。
雪崩ビーコンの操作方法と注意点
前述の通り、アバランチギアは正しく使えなければ意味を成しません。特にビーコンは、電気製品であるため、日頃からのメンテナンスと操作の習熟が不可欠です。
入山前には、必ず全員でビーコンの送受信チェック(グループチェック)を行います。これは、各々のビーコンが正常に作動しているか、またモードの切り替えを忘れている人がいないかを確認するための重要な手順です。
行動中は常に電源を入れ、体を覆うウェアの内側に、専用のハーネスでしっかりと装着します。ザックの中やポケットに入れていると、雪崩の衝撃で体から離れてしまう可能性があるためです。
万が一の捜索時には、まずリーダーの指示に従い、全員が落ち着いて受信モードに切り替えます。複数人で捜索する場合は、効率的に範囲をカバーするための捜索方法(シグナルサーチ、コースサーチなど)があり、これらは講習会などで専門的な知識と技術を学ぶ必要があります。
また、ビーコンの電池残量には常に気を配り、メーカーが推奨する残量を下回る前に交換することが大切です。スマートフォンや無線機などの電子機器は、ビーコンの電波に干渉する可能性があるため、使用時は20cm以上離すように心がけてください。(参照:日本雪崩ネットワーク)
雪山の危険性とリスクマネジメント
バックカントリーのフィールドには、雪崩以外にも様々な危険が潜んでいます。これらのリスクを事前に理解し、対策を立てておくことがリスクマネジメントの基本です。
主な危険性
- 天候の急変: 山の天気は変わりやすく、吹雪による視界不良や気温の急激な低下は、道迷いや低体温症を引き起こす原因となります。
- 道迷い(ホワイトアウト): 濃い霧や吹雪で周囲が真っ白になり、方向感覚を失う状態です。GPSやコンパス、地図を使いこなす技術が求められます。
- 低体温症・凍傷: 濡れたウェアや不十分な防寒対策により、体の深部体温が低下する危険な状態です。
- 地形のリスク: クリフ(崖)からの転落や、ツリーホール(木の根元の空洞)への落下など、滑走中にも危険は伴います。
これらのリスクを管理するためには、事前の情報収集と計画が最も重要です。信頼できる天気予報や雪崩情報を確認し、参加メンバーのレベルや体力に見合った無理のないルートを選びます。
また、計画通りに進まなかった場合に備え、複数のエスケープルート(下山ルート)を想定しておくことも大切です。
まとめ:安全に楽しむソリッドボードでバックカントリー
この記事では、ソリッドボードでバックカントリーを始めるための様々な情報をお伝えしてきました。最後に、安全に楽しむための重要なポイントをまとめます。
- ソリッドボードは初期費用を抑えて始められる
- 滑走性能は一枚板ならではの魅力がある
- 登行時はボードを背負うため身体的な負担が大きい
- アバランチギア3点セットは必須装備
- ビーコン、ショベル、プローブの正しい使い方を習得する
- 自分の体重に合った浮力を持つスノーシューを選ぶ
- ボードを運べるバックカントリー用ザックが必要
- 登りは小さな歩幅で一定のリズムを保つ
- ルート選びでは雪崩のリスクが低い尾根などを選ぶ
- レイヤリングでこまめに体温調節を行う
- 入山前には必ずビーコンのグループチェックを実施する
- 天候の急変や道迷いなど雪崩以外のリスクも理解する
- 事前の情報収集と無理のない計画が安全の鍵
- 単独での行動は絶対に避ける
- 経験豊富なガイドや上級者と共に行動することが強く推奨される