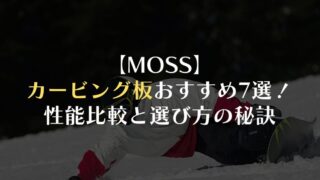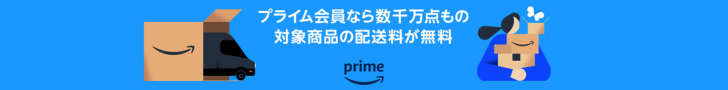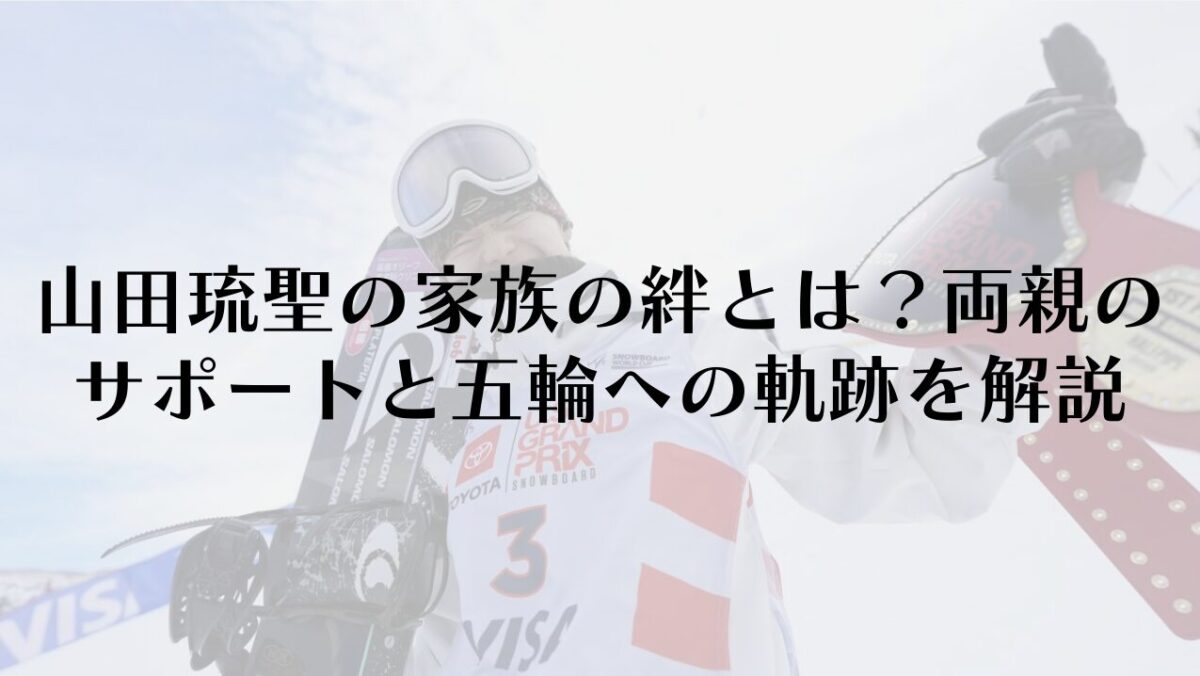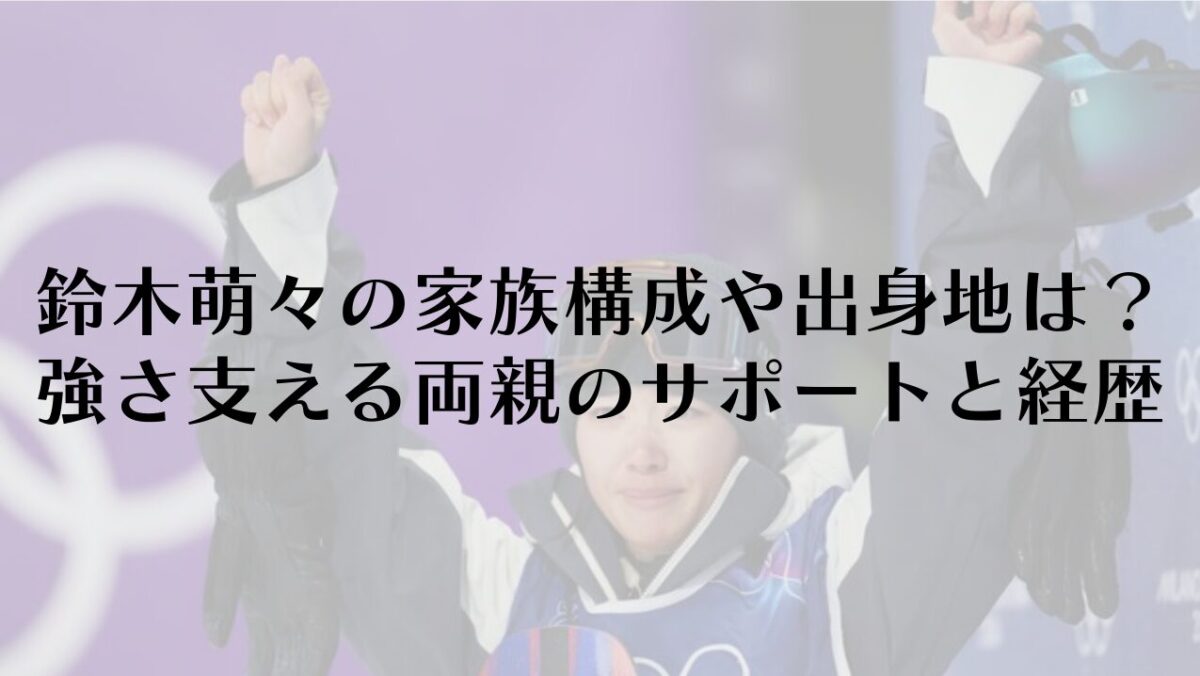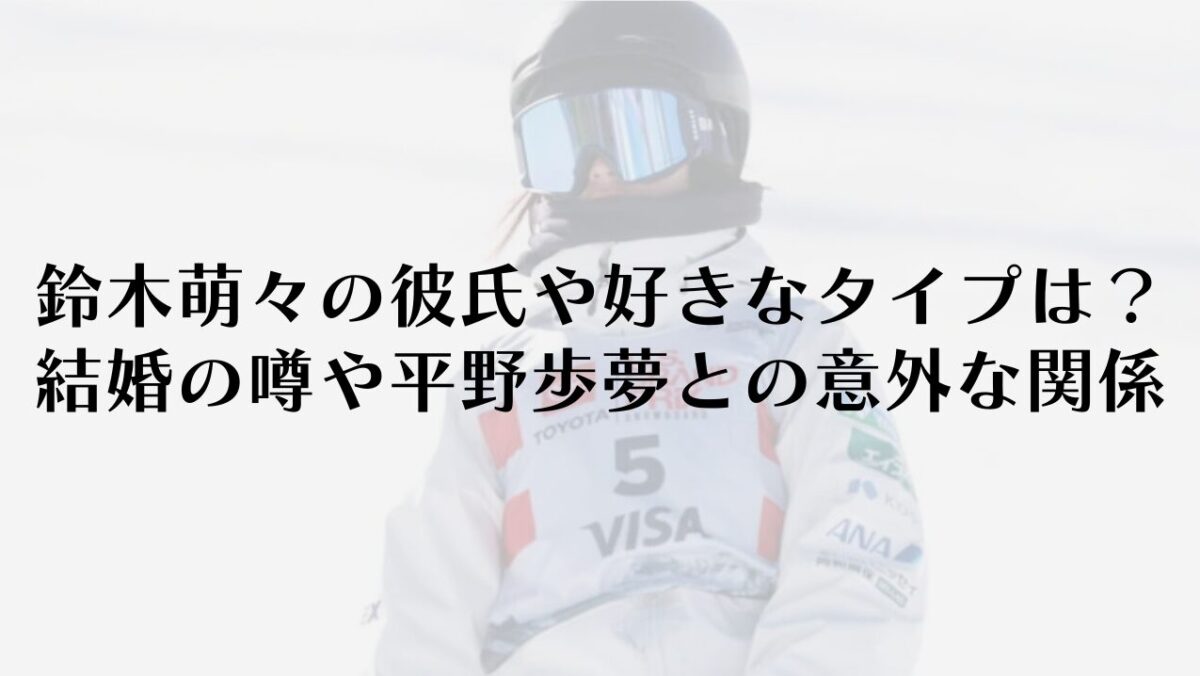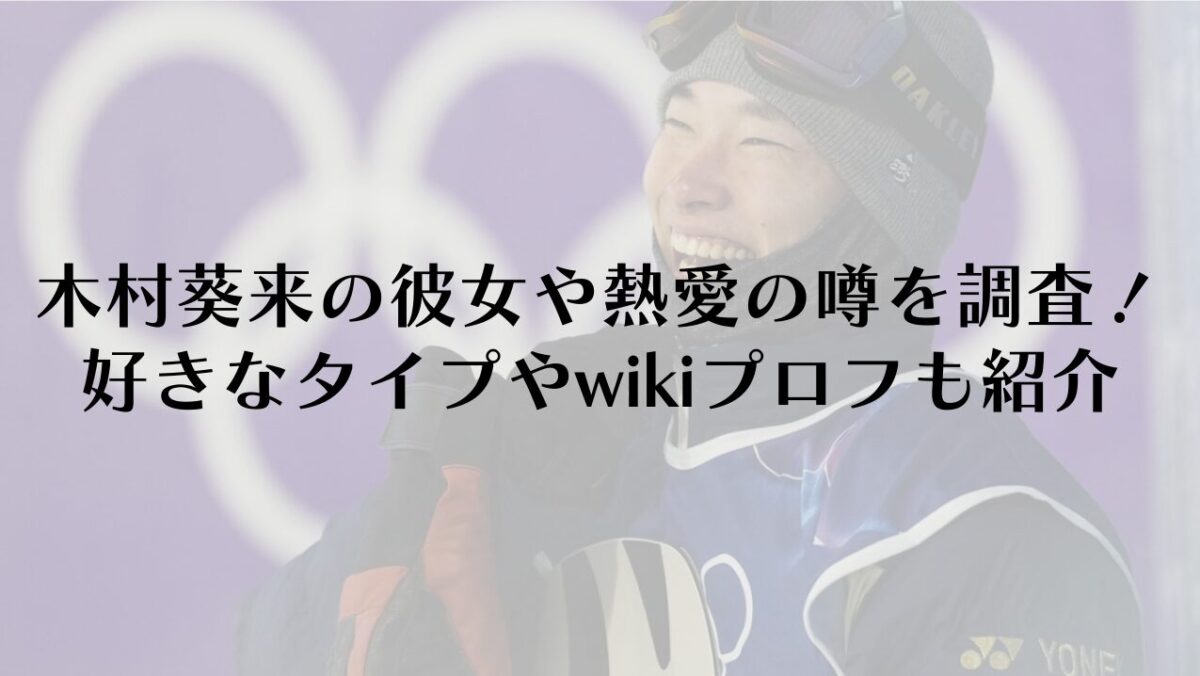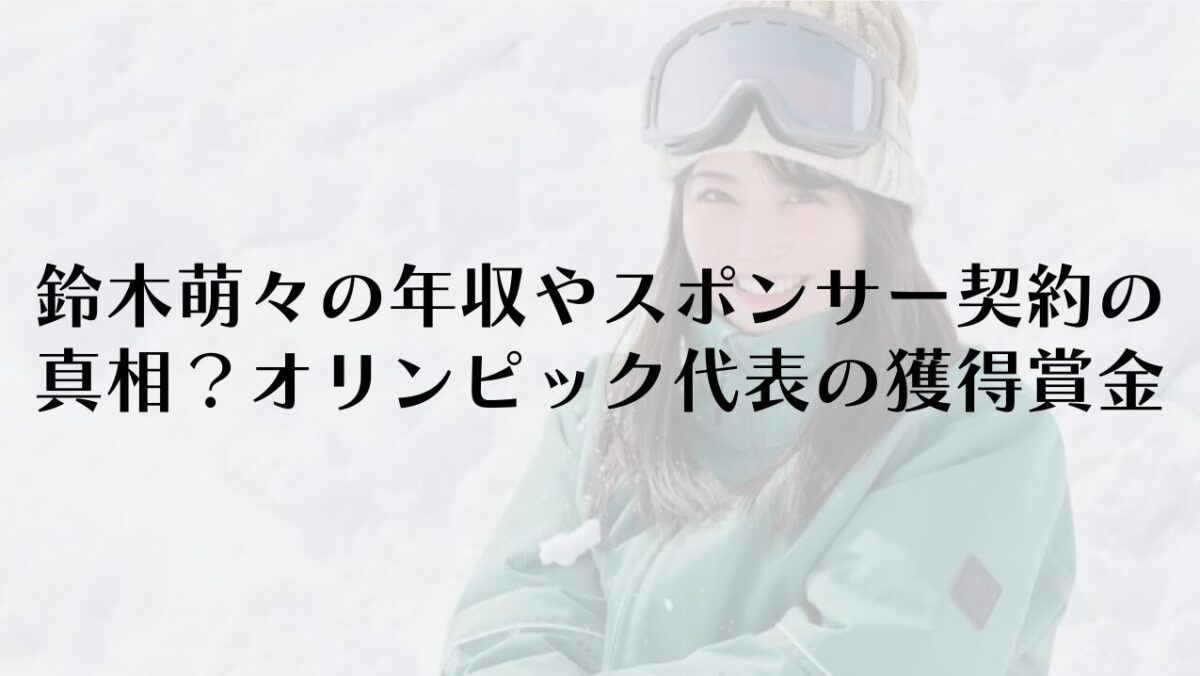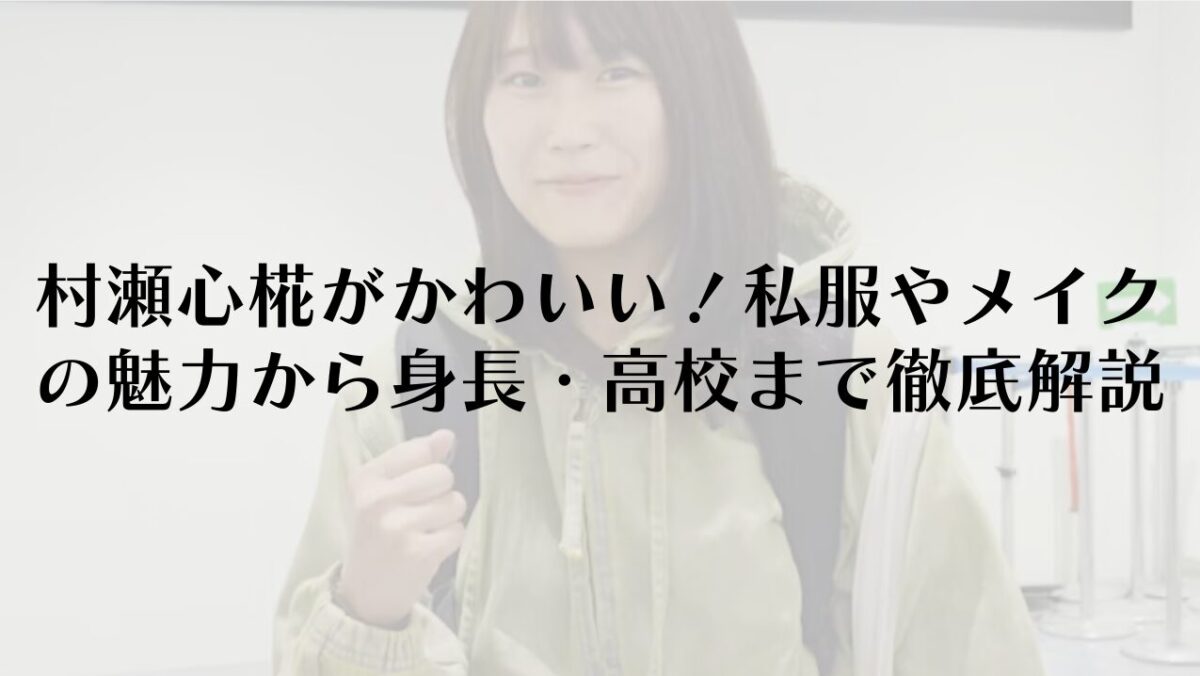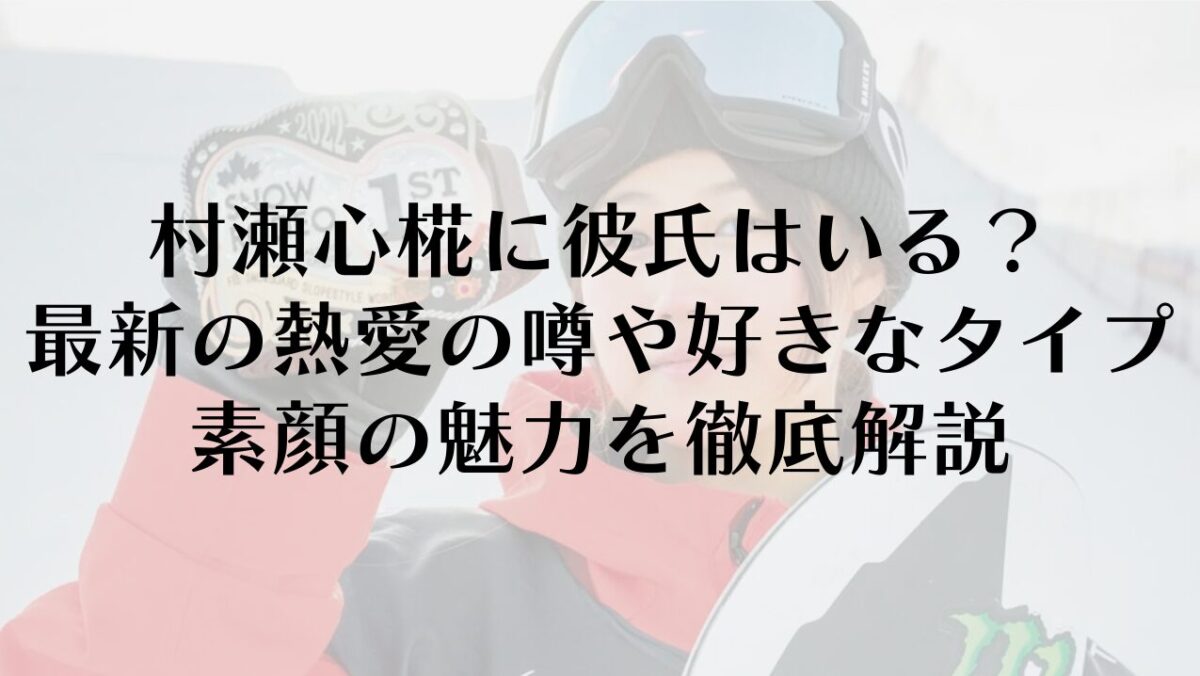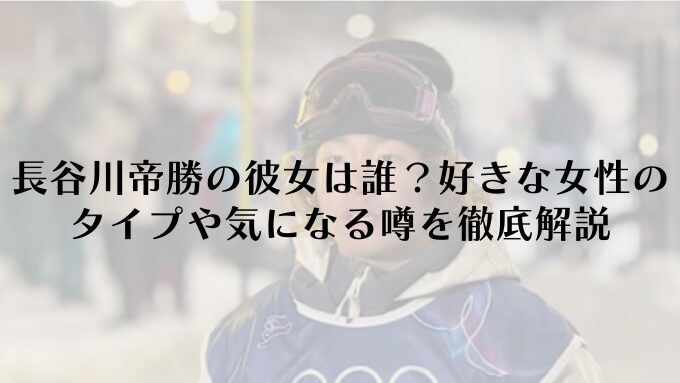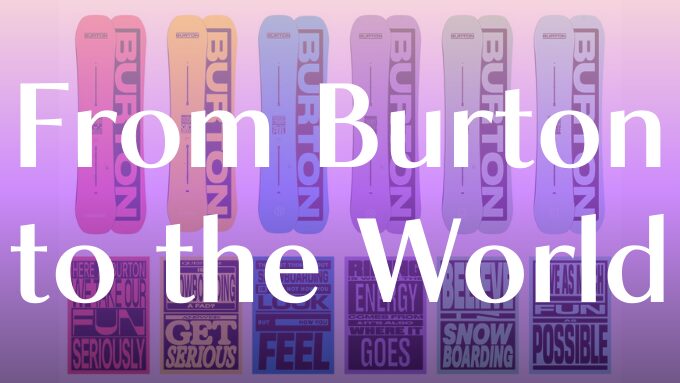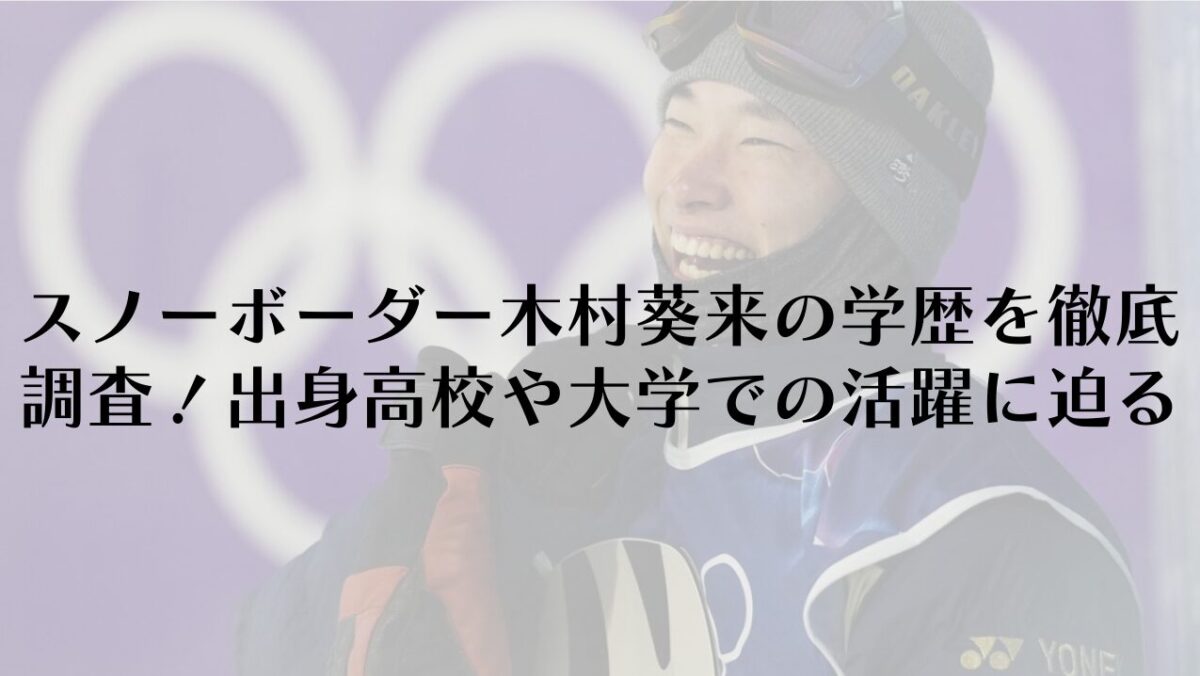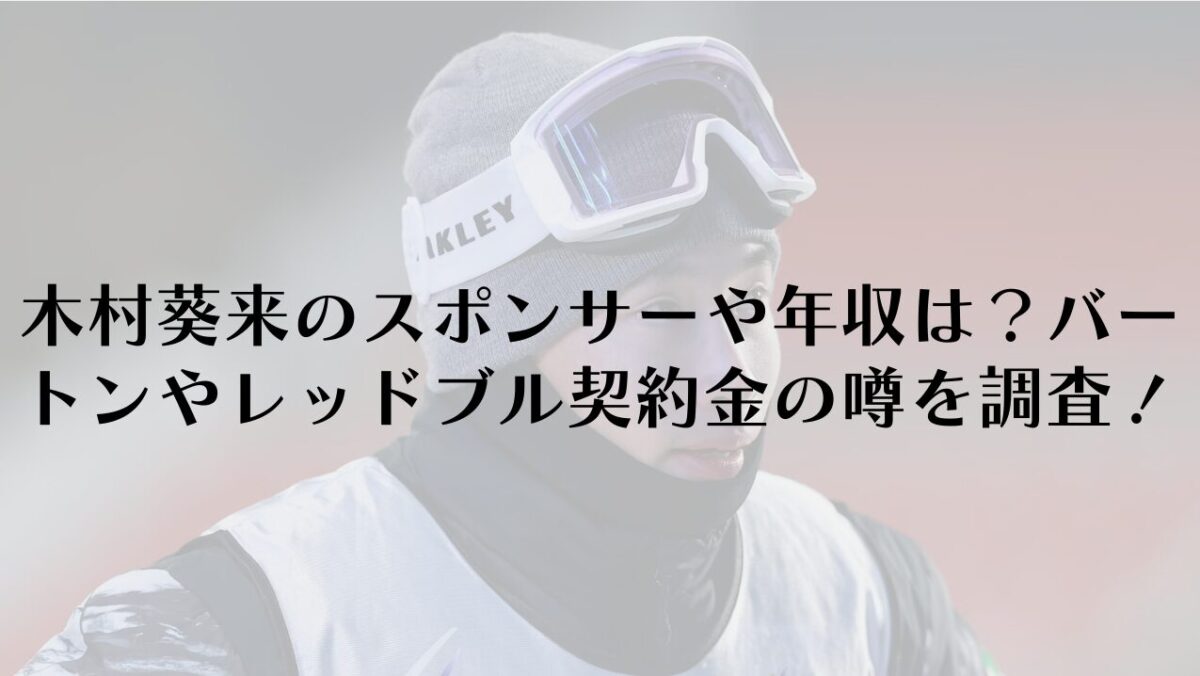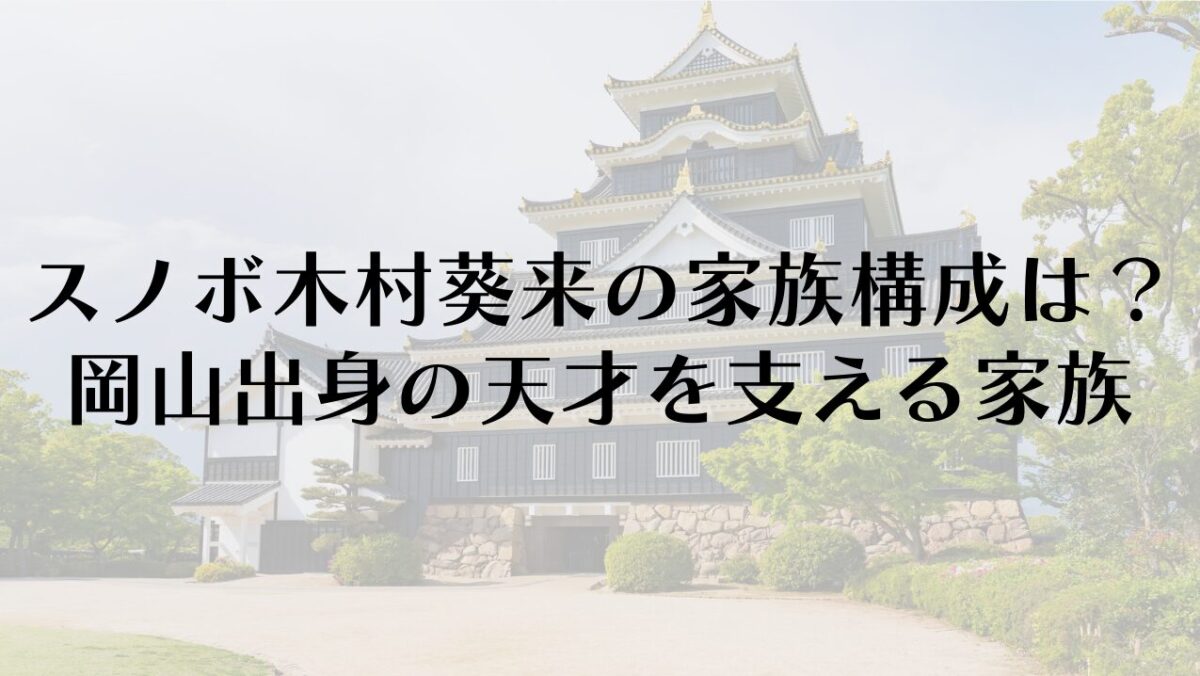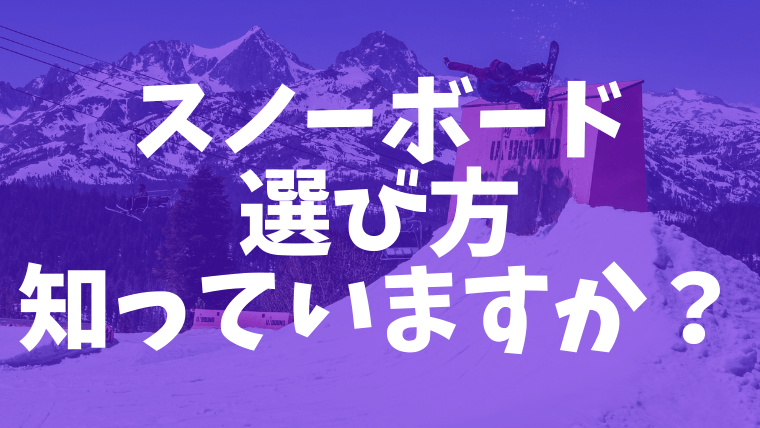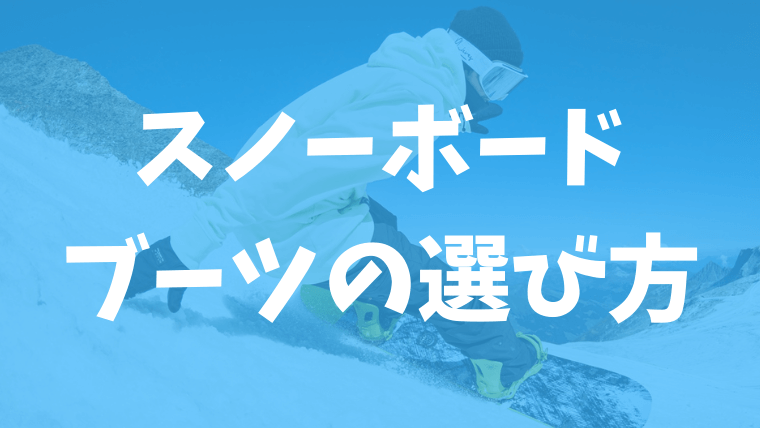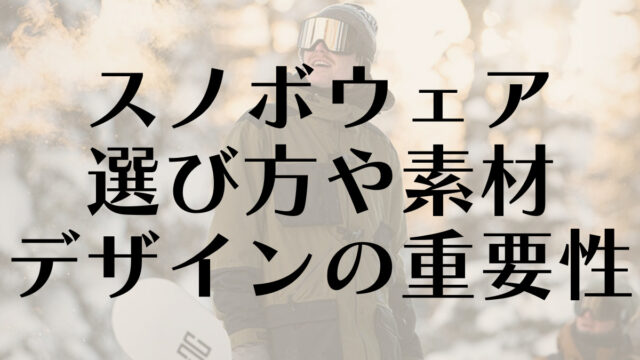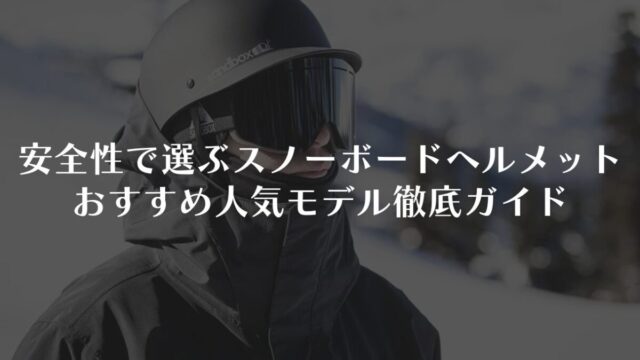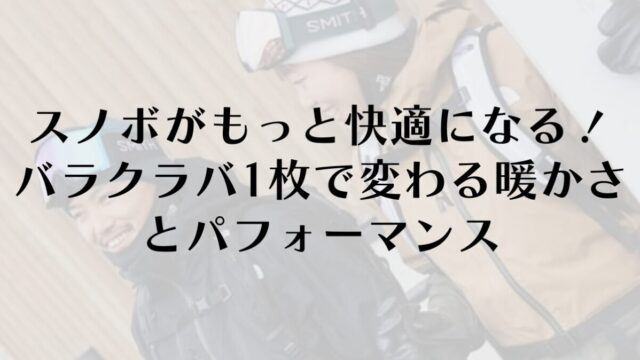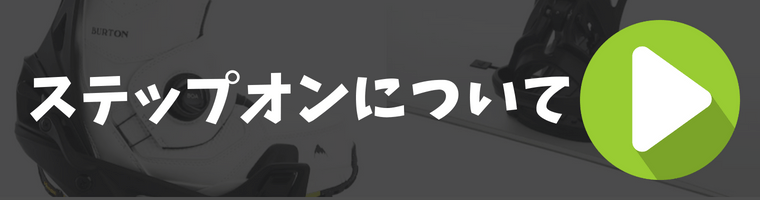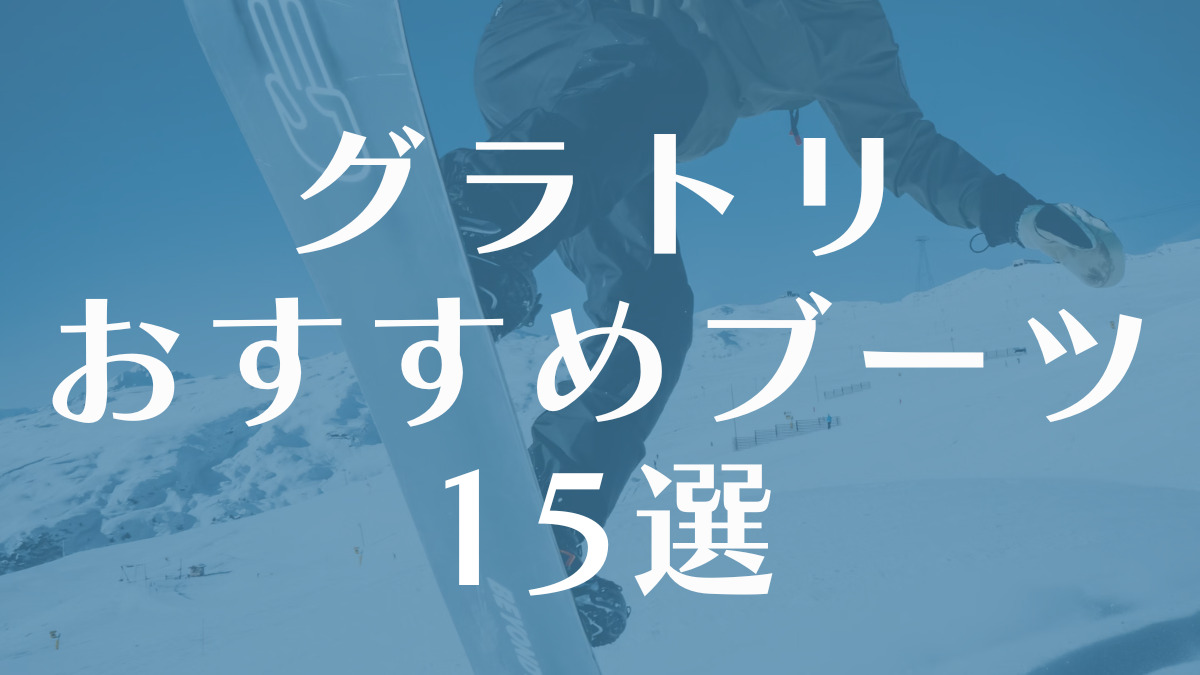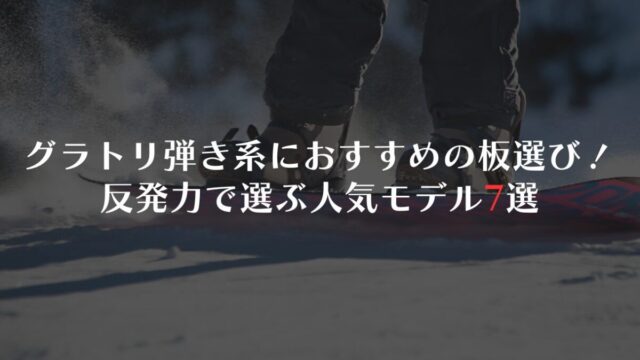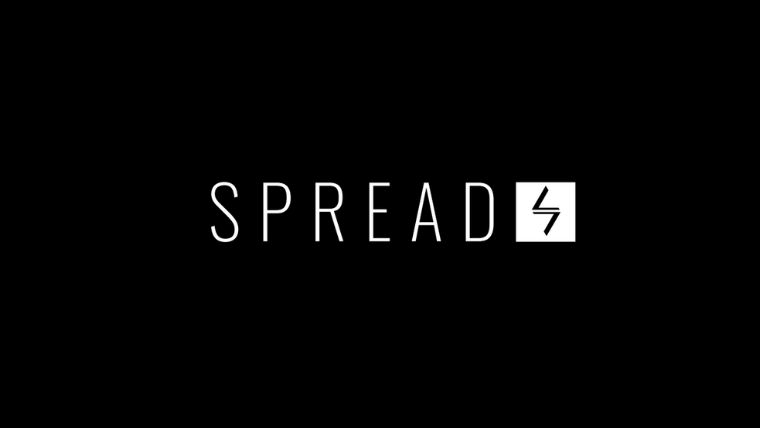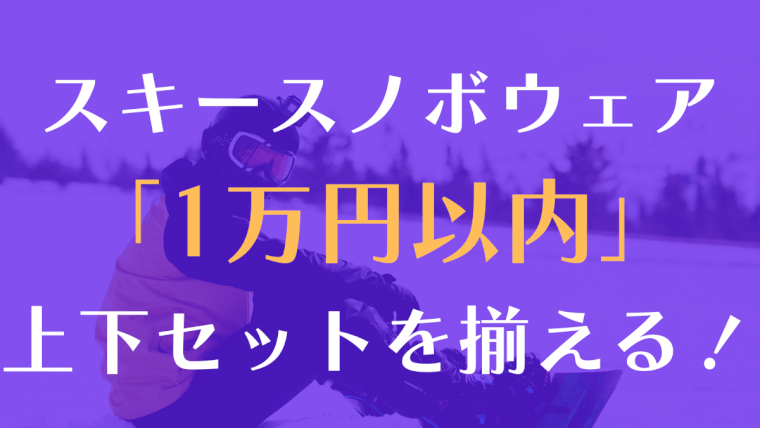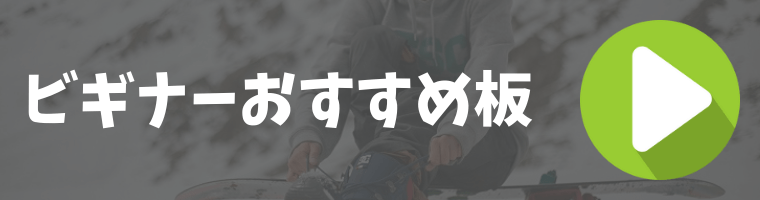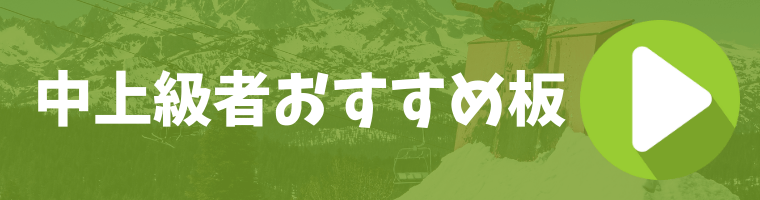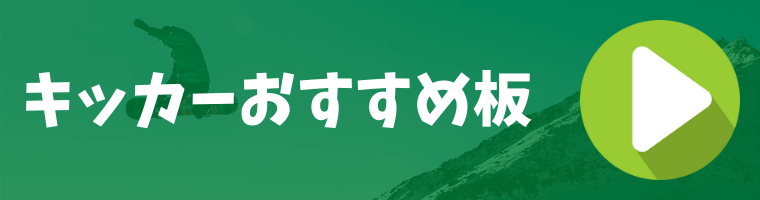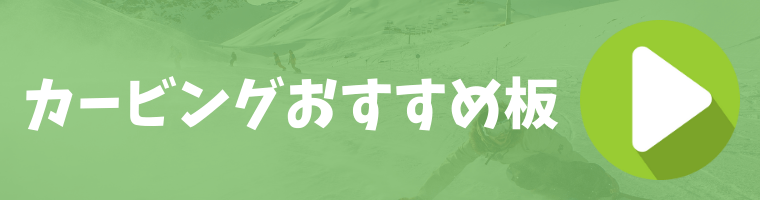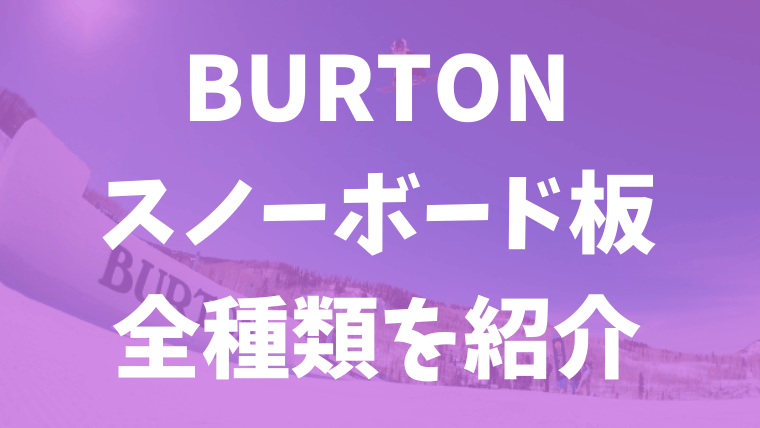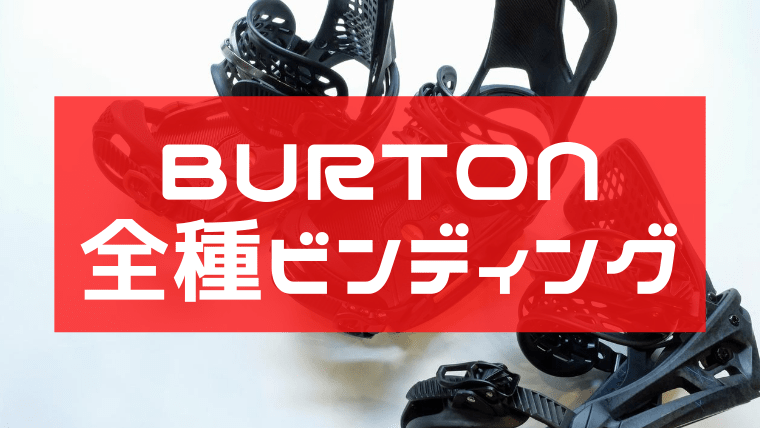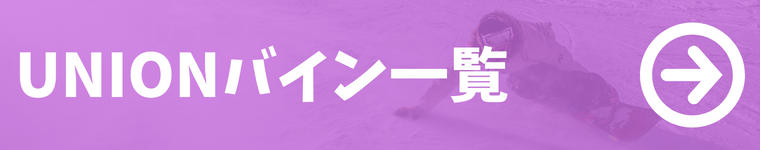【MOSS】RRの評価は?中級者で以上でキレるターンとスムーズな導入を求むライダーへ
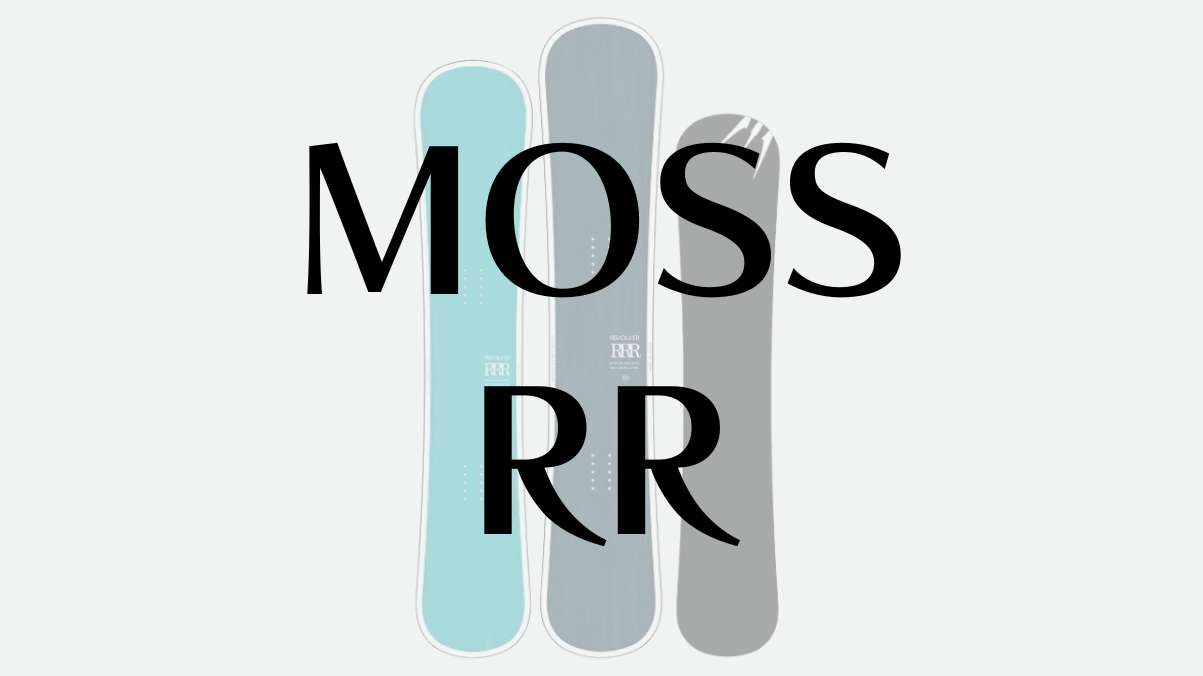
MOSS RRは国産老舗ブランドMOSSの中でも、その独特な乗り味や高い反発性能について多くの注目を集めています。
実際の重さや、フレックスとトーションのバランスがどうなっているのか、気になるところだと思います。特にカービング性能に優れるという評判ですが、パウダーでの滑走性も知りたいという、あなたの参考になれば嬉しいです!
この記事では、MOSS RRのスペックから得意ジャンルまで、客観的な情報を詳しく解説していきます。この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- MOSS RRの基本的なスペックと構造的な特徴
- カービングや圧雪バーンでの具体的な性能評価
- パウダーや地形遊びなど様々な状況への適性
- 型落ちモデルとの比較や選ぶ際のポイント
MOSS「RR」のスペックと特徴を評価
MOSS「RR」(リボルバー・ダブルアール)の性能を理解するために、まずはその基本的なスペックと構造的な特徴を見ていきましょう。
| 項目 | 特徴 | 概要 |
|---|---|---|
| シェイプ | ディレクショナルシェイプ | ターンの導入と直進安定性を重視した、前後非対称の形状。 |
| 形状 | CS2キャンバー | 操作性とグリップ感を両立するMOSS独自の接点移動式キャンバー。 |
| フレックス | ミディアムハード | 高速安定性と反発力を備えた、やや硬めの設定。 |
| 構造 | ウッドコア | 主にポプラなどを使用した、軽量で反発力のあるコア。 |
| ソール | シンタード(グラファイト) | 滑走性が高く、ワックス浸透性に優れたソール素材。 |
RRシリーズの基本コンセプト
MOSS「RR」は、ブランドのフラッグシップモデル「REVOLVER(リボルバー)」から派生した、カービング性能を重視したモデルです。
REVOLVERが持つ高い操作性やオールラウンド性能をベースにしつつ、RRは特にターンの質を高めることに焦点を当てています。
具体的には、ターンの導入をスムーズにし、ターン中のエッジグリップを強化、そしてターン後半の抜けを良くすることを目指して設計されています。
このため、圧雪バーンでのフィーリングを何より重視するライダーや、カービングの技術を向上させたいと考える中級者から上級者まで、幅広く支持されています。
ディレクショナルシェイプの特性
RRは、進行方向に対してノーズ(先端)がテール(後端)よりも長く、スタンス(足を置く位置)もテール寄りに設定されている「ディレクショナルシェイプ」を採用しています。
この形状は、カービングターンにおいて多くのメリットをもたらします。 まず、ターンの始動時にノーズが雪面を捉えやすく、スムーズにターンに入ることが可能です。
ターン中は、重心がボードのセンターよりもやや後ろにあるため、テール側のエッジにしっかりと体重を乗せやすく、安定したエッジグリップが得られます。
一方で、デメリットというか、注意点もあります。スイッチスタンス(利き足と逆の足を前にして滑る)は、ノーズとテールの形状が非対称であるため、やや難しくなります。
フリースタイルで求められるような、前後対称の操作性とは異なる特性を持っているため要注意!
キャンバー構造とレスポンス
RRは、MOSS独自の「CS2 CAMBER (CAMBER SHIFT CONTACT SYSTEM)」と呼ばれるキャンバー構造を採用していることが特徴です。
これは、ボードの最大幅よりもキャンバー(弓なりの反り)の長さを意図的に短く設定した構造です。この設計により、ボードをフラット(平ら)にしている状態では雪面に接する部分が短くなり、取り回しが非常に軽快になります。
しかし、ひとたびボードを傾けてターンに入ると、キャンバーの接点が移動し、有効エッジ(滑走中に雪面に接するエッジ部分)を最大限に活用できます。
結果として、低いスピードでの操作性と、高速カービング時の高いエッジホールドという、相反する要素を両立させています。この構造が、RRの素早いレスポンスと粘り強いグリップ感を生み出す源泉の一つとなっています。
独自のフレックスとトーション設定
RRのフレックス(ボード全体の反発力・しなり)は、ミディアムハード(やや硬め)に設定されていることが一般的です。
この硬さは、高速で滑走する際の安定性に直結します。スピードが出ている状況でターンを行っても、ボードがばたついたり、ターン弧が不安定になったりするのを防ぎます。
また、トーション(ボードのねじれ)も適度にコントロールされています。トーションが柔らかすぎるとエッジの切り替えは楽になりますが、高速域でのグリップが甘くなる傾向があります。
RRは、ライダーの力を確実にエッジに伝えることができるよう、しっかりとしたねじれ剛性を持たせています。
ただし、この硬さは脚力を必要とします。ボードをしっかりと踏み込み、しならせることができる技術がなければ、RRの真価を発揮させるのは難しいかもしれませんね。
推奨スタンスとセッティング幅
前述の通り、RRはディレクショナルシェイプを採用しており、メーカーによって推奨されるスタンス(足の幅)とセットバック(後ろ足がどれだけテール寄りか)が決められています。
多くのモデルで10mm程度のセットバックが標準となっています。このセッティングは、カービングターン時に最適なポジションを取りやすくするためのものです。
もちろん、セッティングの幅(インサートホールの数)は十分に確保されているため、個人の好みや滑るコンディションに合わせて調整は可能です。
例えば、よりパウダーでの浮力を求める日は、スタンスをさらに後ろに下げる(セットバックを増やす)といった対応もできます。
MOSS「RR」の得意ジャンルを評価
RRのスペックが分かったところで、次に気になるのは「実際にどんな滑りに向いているのか?」ということですよね。ここでは、代表的なジャンル別にRRの適性を評価します。
| 評価項目 | 評価 (5.0満点) | 概要 |
|---|---|---|
| カービング | 最も得意とする領域。ターンの導入、グリップ、抜け、全てが高水準。 | |
| パウダー | ディレクショナル形状で一定の浮力はあるが、専用機には及ばない。 | |
| レース | テクニカル(技術選)では強力な武器になる。アルペン競技は専用機が優位。 | |
| 操作性 (大回り) | 高速域での安定性が抜群。ターン弧の調整もしやすい。 | |
| 操作性 (小回り) | レスポンスは良いが、硬さがあるため相応の脚力と技術が必要。 | |
| 衝撃吸収性 | 適度な硬さが振動を抑え、荒れたバーンでも安定感がある。 |
カービングターンにおける性能
RRの評価において、カービング性能は外せません。結論から言えば、このボードはカービングのために設計されたと言っても過言ではないでしょう。
セミハンマーヘッド形状とCS2キャンバー構造が、ターンの始動を驚くほどスムーズにします。少しボードを傾けるだけで、ノーズが自然に雪面を捉え、ターン内へと導いてくれます。
ターン中盤では、ミディアムハードのフレックスと適度なトーションが、アイスバーンであってもエッジが抜ける感覚を最小限に抑え込みます。
そして、ターン後半はテールがしっかりと粘り、次のターンへの推進力(反発)を生み出します。この一連の流れが非常にスムーズで、まさに「切れる」ターンを体感できるはずです。
圧雪バーンでの高速安定性
カービング性能と密接に関連しますが、圧雪された朝一番のゲレンデ(グルーミングバーン)での高速安定性は抜群です。
ボードの硬さが振動をしっかりと吸収し、スピードが上がってもノーズがばたつくことが少なくなっています。
ディレクショナルシェイプによる直進安定性も高く、ライダーは安心してハイスピードでの滑走に集中できます。
特に、大きなターン弧(大回り)を描く際には、その真価を発揮します。ボードがたわんでから戻る力(反発)が強いため、リズミカルにターンを繋ぎながら、スピードを落とさずに滑り降りることが可能です。
パウダーランでの操作性
RRはカービングボードであり、パウダー専用機ではありません。この点は明確にしておく必要があります。
とはいえ、ディレクショナルシェイプであり、ノーズが長く、セットバックも入っているため、新雪が降った日のゲレンデ脇(ゲレ脇パウダー)程度であれば十分に対応可能です。ノーズが雪に刺さりにくく、一定の浮力は得られます。
しかし、ウエスト幅は標準的であり、キャンバー構造が基本です。そのため、深いパウダー(ディープパウダー)や、浮力が強く求められるコンディションでは、操作が難しくなる場面も出てきます。パウダーをメインに楽しみたい場合は、専用のパウダーボードを選ぶ方が合理的です。
地形遊びやツリーラン適性
地形遊びやツリーラン(林の中を滑る)に関しても、パウダーランと同様の評価になります。
CS2キャンバーによるフラット時の操作性の良さは、狭い場所での細かい動きに有利に働きます。レスポンスが良いため、障害物を避けたり、地形の起伏に合わせてボードを操作したりすることは可能です。
ただし、ボード自体に硬さがあるため、柔らかいボードのように簡単にしならせて遊ぶ、というスタイルには向きません。
どちらかというと、地形の壁をバンク(斜面)として使い、カービングターンで駆け上がるといった、スピードを活かした遊び方に向いています。
フリースタイルへの対応力
フリースタイル(ジャンプ、ジブ、グラトリなど)への対応力は、残念ながら低いと言わざるを得ません。
まず、ディレクショナルシェイプであるため、スイッチスタンスでの滑走やトリックが非常にやりにくいです。また、フレックスが硬いため、低速でプレス(ボードをしならせる)系のグラトリを行うのも困難です。
もちろん、キッカー(ジャンプ台)でのストレートジャンプ(オーリー)の反発は強く、安定した着地も可能ですが、スピン(回転)系のトリックには向きません。
RRは、あくまで「滑り」を追求するボードであり、フリースタイルを楽しむためのものではない、と割り切る必要があります。
レース・競技シーンでの可能性
「レース」と言っても、アルペン競技(GS/SL)のような、純粋な速さを競うレースには専用のメタル入りハンマーヘッドボードが適しています。
一方で、MOSS RRが活躍するのは「テクニカル選手権(技術選)」のような、ターンの質や美しさを競う競技シーンです。
RRの持つ、ターンの導入のスムーズさ、ターン中の安定感、表現力豊かなターン弧は、まさにテクニカル系の競技で求められる要素です。
実際に、多くのデモンストレーターや上位入賞者がMOSSのボード(RRやその上位機種であるTiモデルを含む)を使用していることからも、その性能の高さがうかがえます。
総括:MOSS「RR」の評価ポイント
これまでの情報をまとめ、MOSS「RR」を評価する上での重要なポイントを箇条書きで整理します。
- MOSS RRはカービング性能を追求したモデルである
- REVOLVERシリーズから派生し、ターンの質に焦点を当てている
- 形状はディレクショナルシェイプを採用
- スタンスはテール寄りのセットバックが基本
- ターンの導入がスムーズで、谷回りがしやすい
- 構造はCS2キャンバーが多く、操作性とグリップを両立
- フレックスはミディアムハードで高速安定性が高い
- トーションも適度に硬く、エッジへの伝達力が良い
- 圧雪バーンでのカービングが最も得意なジャンル
- 高速での大回りは抜群の安定感を誇る
- 小回りも可能だが、相応の脚力と技術が求められる
- パウダーランは対応可能だが、専用機には及ばない
- 地形遊びはスピードを活かした滑りに向く
- フリースタイルやグラトリには不向きである
- テクニカル系の競技シーンで高く評価されている
この他にもMOSSにはさまざまなボードがあります。紹介したモデルも含め、MOSSでカービングにおすすめなモデルをまとめた記事もあるため参考になれば幸いです。