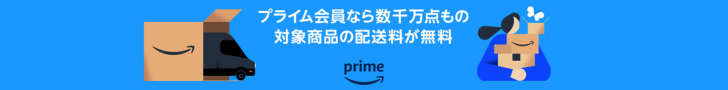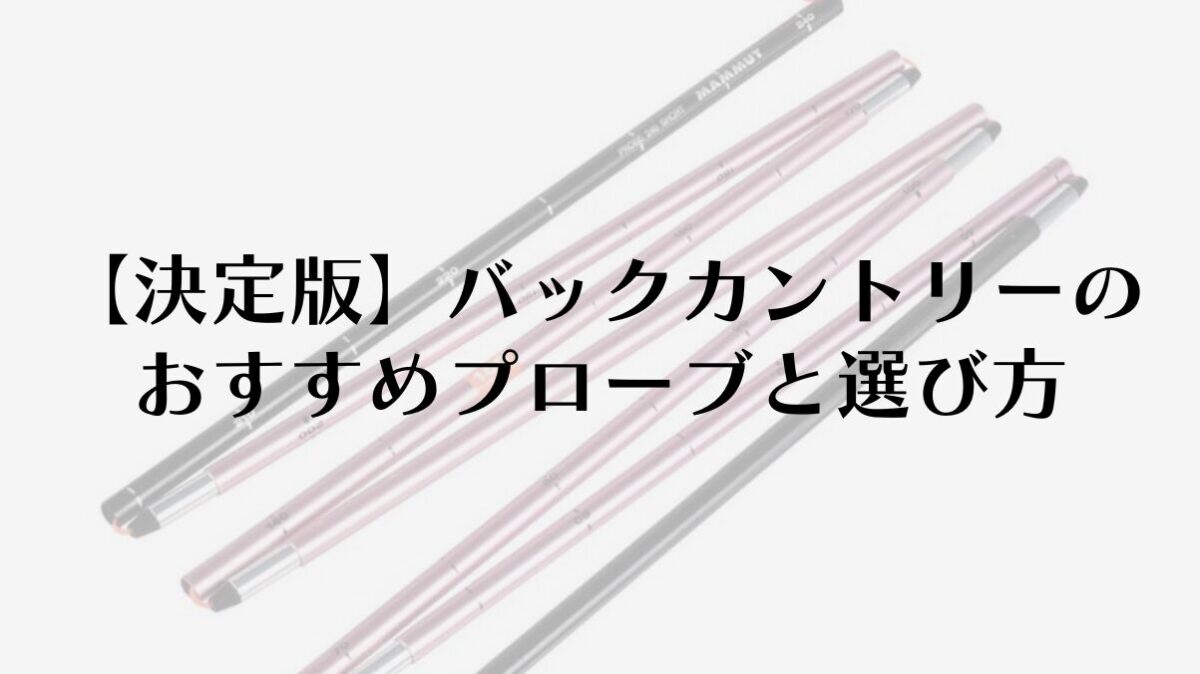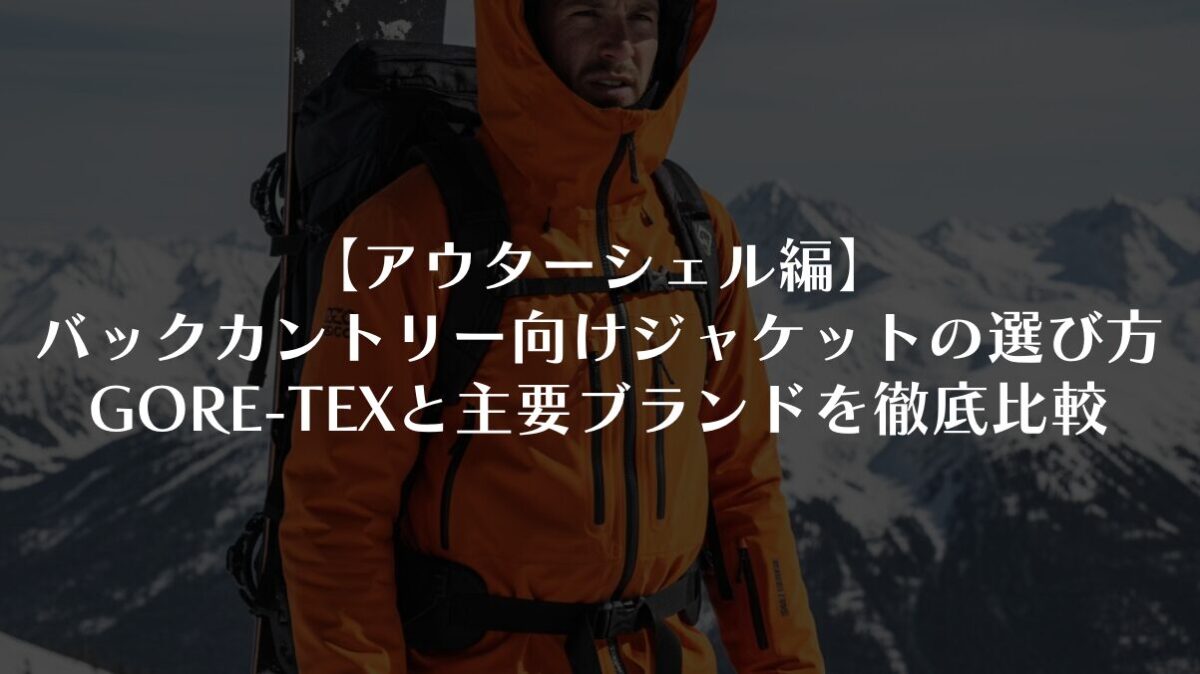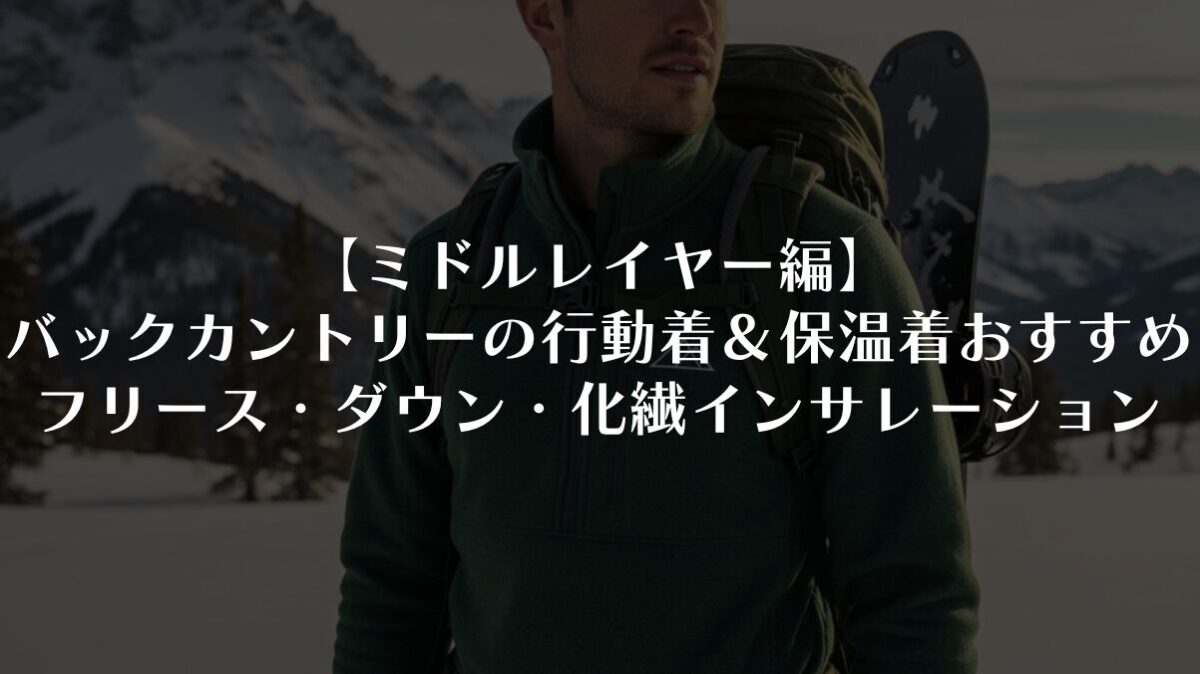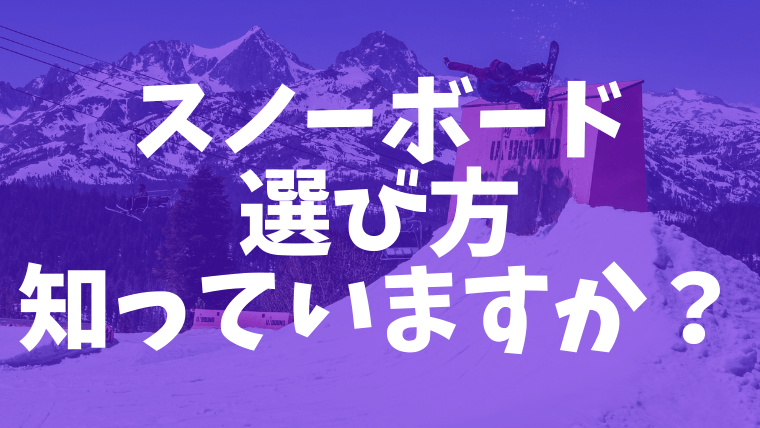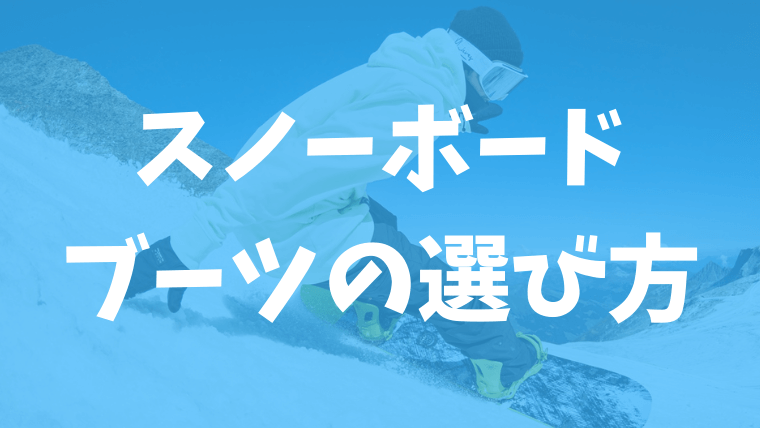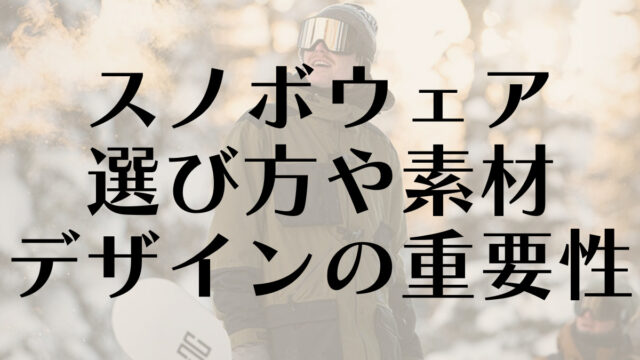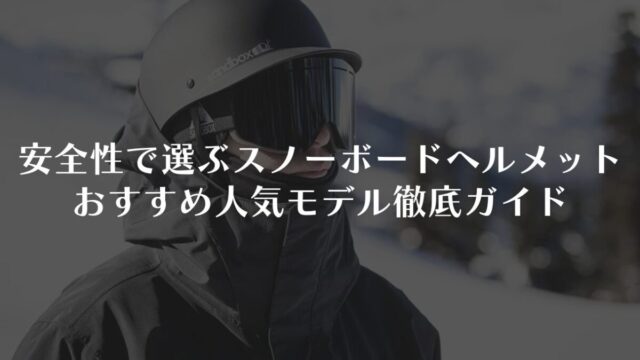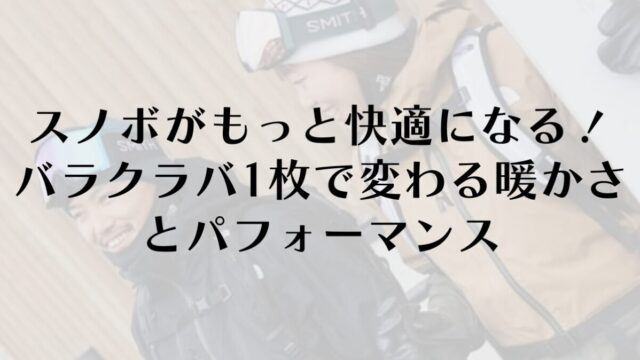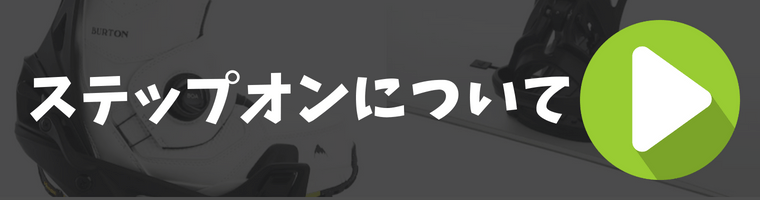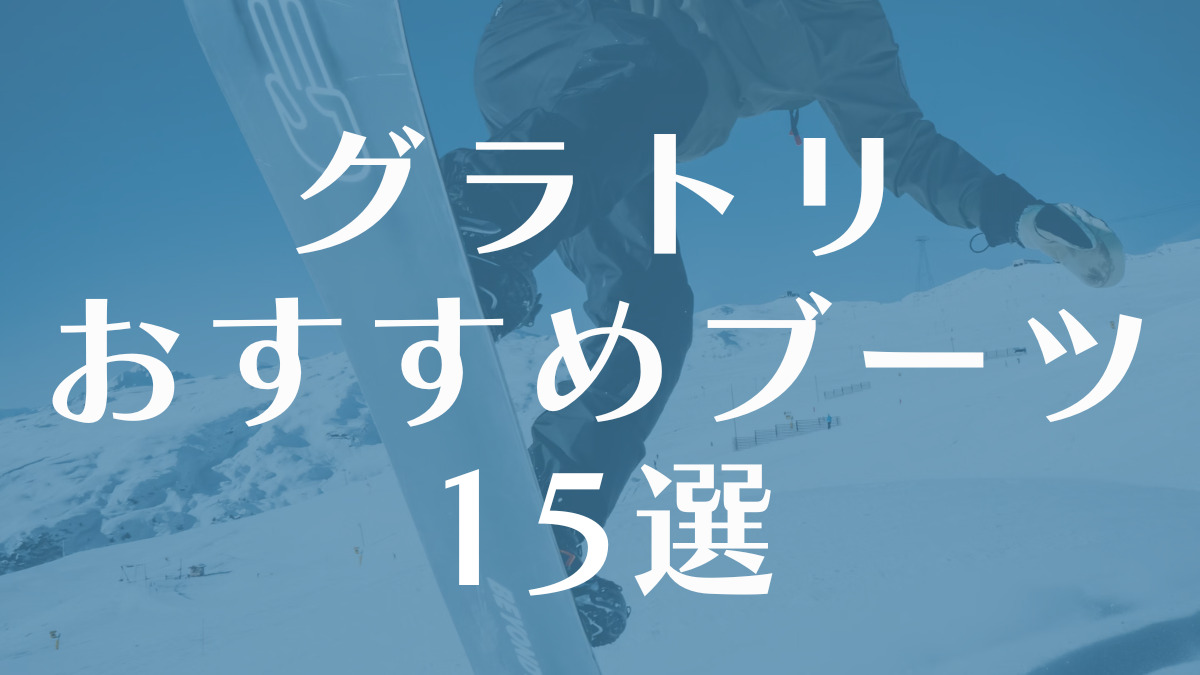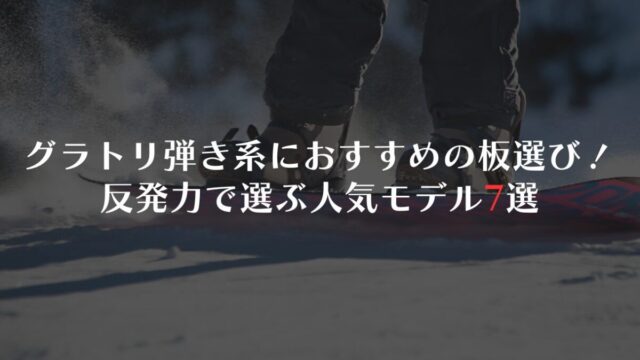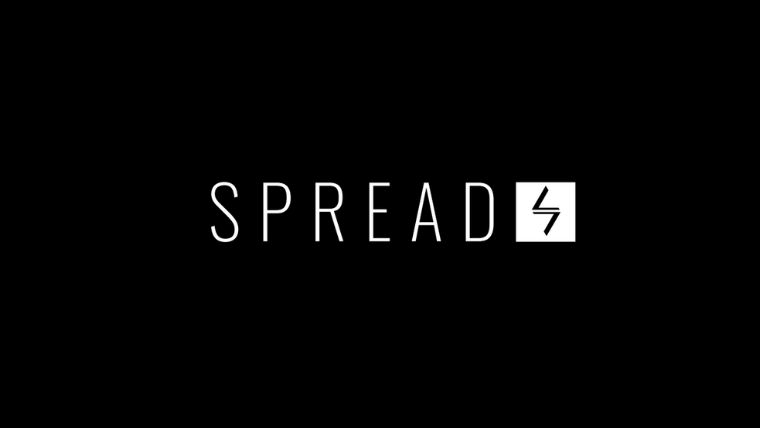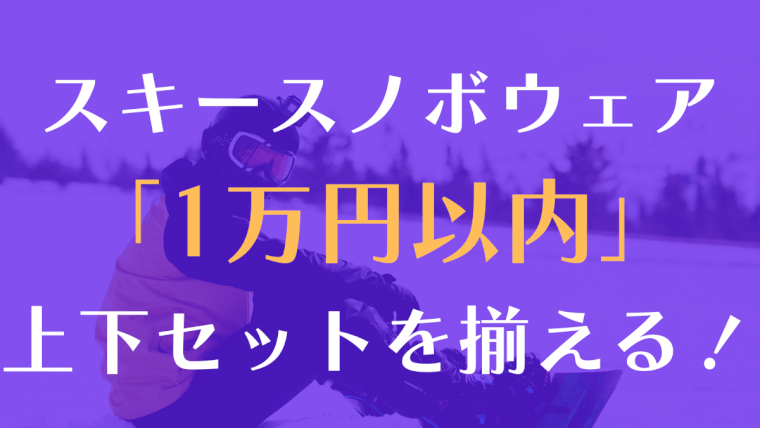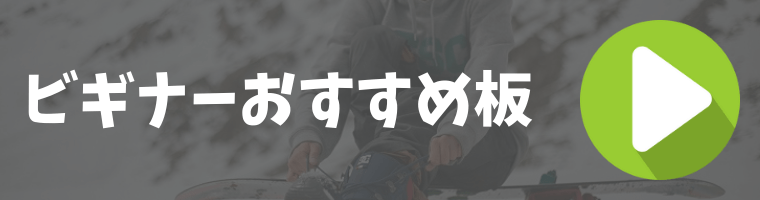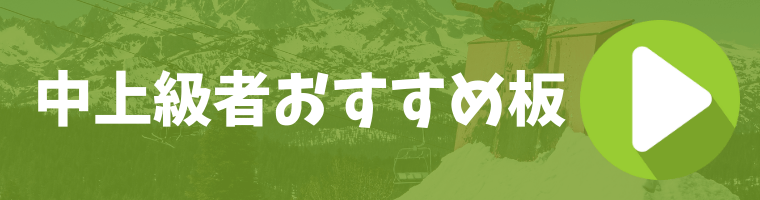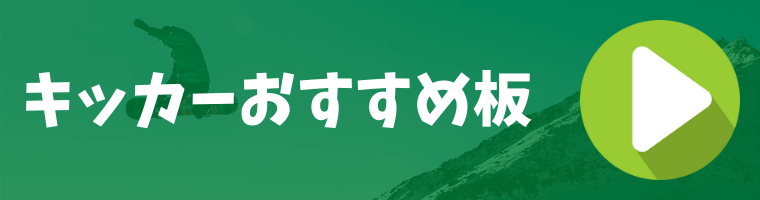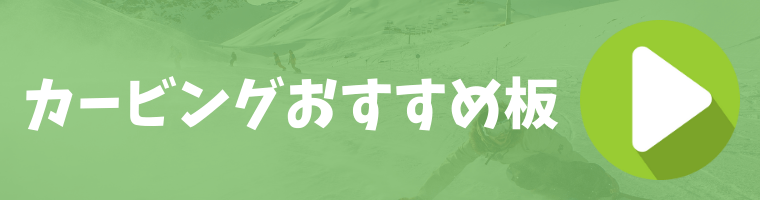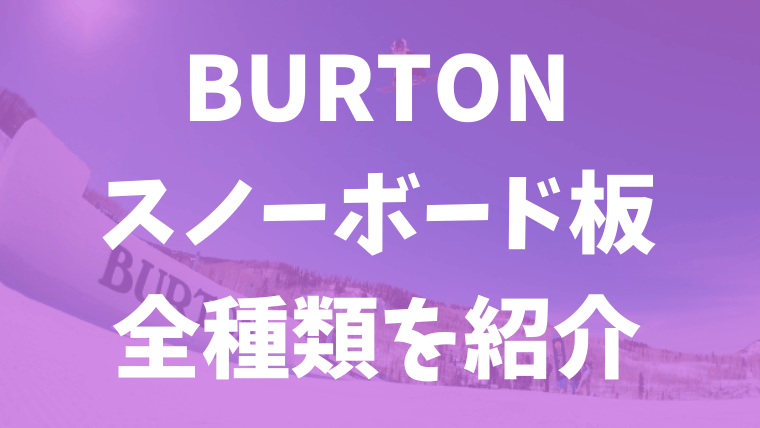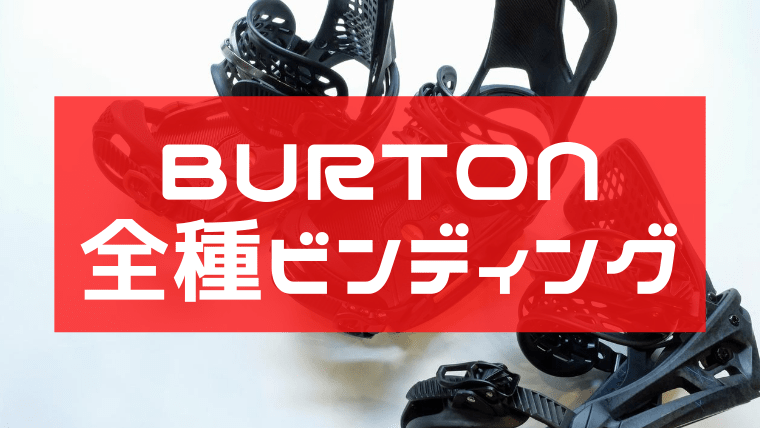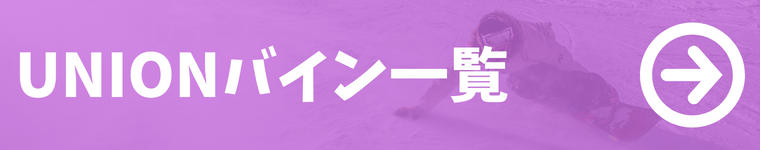【ベースレイヤー編】バックカントリーにおすすめの素材と人気モデル|メリノvs化繊
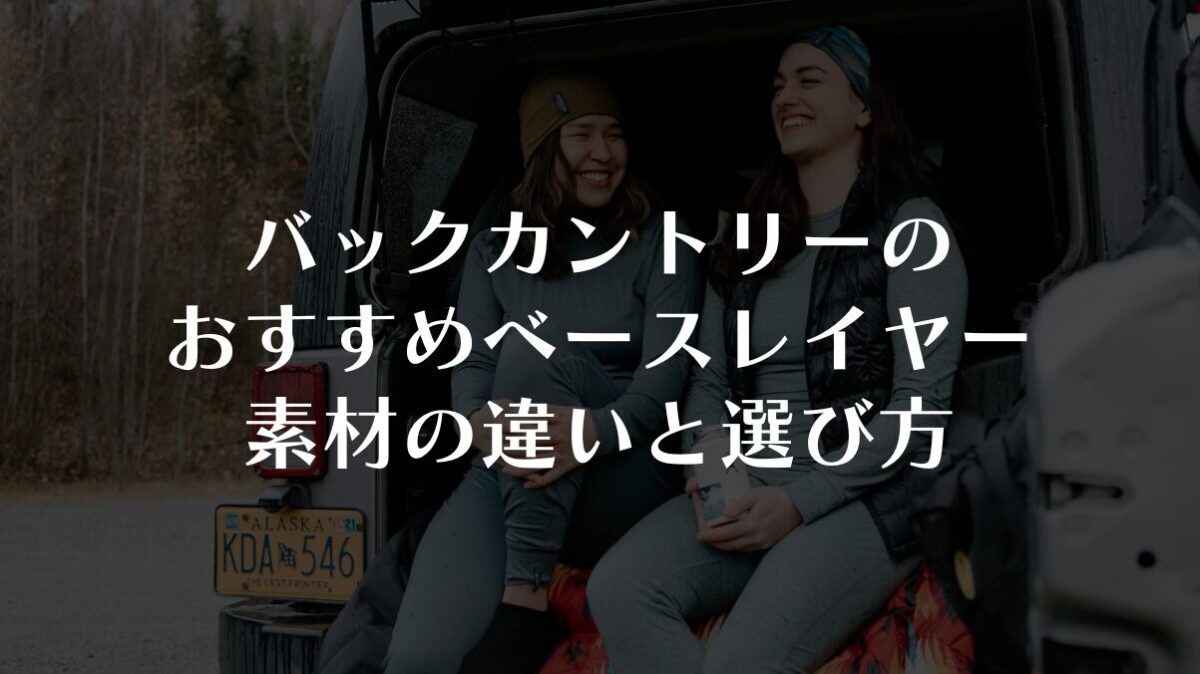
バックカントリー環境において、ウェアの選択はパフォーマンスだけでなく、時に安全性をも左右します。
特に肌に直接触れるベースレイヤーは、汗処理と体温調整という重要な役割を担っており、その選択を誤ると深刻な汗冷えを引き起こす原因ともなり得ます。
しかし、天然素材であるメリノウールから高機能な化学繊維まで、多種多様な製品が存在するため、どれを選べば良いか迷う方も少なくないでしょう。
素材ごとの保温性や速乾性、そして防臭性といった特性を正しく理解し、自身の活動スタイルに合った一着を選ぶことが、快適な山行への第一歩です。
この記事では、バックカントリーにおけるベースレイヤーの重要性から、素材ごとの特徴、具体的な人気モデル、そして効果を最大化するレイヤリングの考え方まで、網羅的に解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について深く理解できます。
- ベースレイヤーの素材ごとのメリットとデメリット
- バックカントリーのシーン別におすすめの生地の厚さ
- パフォーマンスを高める正しいレイヤリングの知識
- 自分に最適なベースレイヤーを見つけるための具体的な選び方
バックカントリーのベースレイヤーおすすめの基本

天然素材メリノウールの特徴とは
バックカントリー愛好者から絶大な支持を得ている素材が、天然素材であるメリノウールです。これは、羊毛の中でも最高級とされるメリノ種の羊から採れるウールで、その機能性の高さが多くの人々を惹きつけています。
メリノウールのメリット
最大のメリットは、優れた保温性と吸湿性にあります。メリノウールの繊維はクリンプと呼ばれる縮れがあり、多くの空気を含むことで高い断熱性を発揮します。これにより、寒い環境でも体温を維持しやすくなります。
また、繊維の表面は水を弾き、内部は湿気を吸収する性質を持っています。汗をかいても肌面をドライに保ちやすく、湿気が気化する際の熱を緩やかに放出するため、急激な体温低下、つまり汗冷えが起こりにくいのが特徴です。
さらに、天然の抗菌防臭効果も備わっており、数日間の山行でも臭いが気になりにくい点は、他の素材にはない大きな利点と考えられます。
メリノウールのデメリット
一方で、デメリットも存在します。化学繊維と比較すると、速乾性は劣る傾向にあります。一度に大量の汗をかいた場合、乾くまでに時間がかかることがあります。
また、天然素材であるため、摩擦に対する耐久性がやや低く、価格も高価になることが一般的です。デリケートな素材なので、洗濯の際には専用の洗剤を使用するなど、手入れに少し気を使う必要もあります。
代表的なメリノウール製品
メリノウールを使用したベースレイヤーの代表格としては、ニュージーランド発のブランドicebreaker(アイスブレーカー)の「200 オアシス」シリーズが挙げられます。
1平方メートルあたり200gという生地の厚さは、適度な保温性と通気性を両立しており、汎用性の高さから多くのユーザーに支持されています。
また、Smartwool(スマートウール)の「クラシックオールシーズンメリノベースレイヤー」も定番の一つです。体にフィットするスリムな裁断で、レイヤリングしやすいのが特徴です。
汗処理に優れた化学繊維のメリット
ポリエステルやポリプロピレンに代表される化学繊維は、メリノウールとは異なるアプローチで快適性を実現する素材です。特に、汗を多量にかくことが想定される場面で、その真価を発揮します。
化学繊維のメリット
化学繊維の最大の強みは、その卓越した速乾性です。繊維自体が水分をほとんど吸収しないため、汗を素早く吸い上げて生地の外側へ拡散させ、スピーディーに蒸発させます。
これにより、肌面は常にドライな状態が保たれ、汗による濡れ戻りやベタつきを効果的に防ぎます。
耐久性が高く、繰り返し洗濯しても性能が劣化しにくい点もメリットです。メリノウールに比べて手入れが簡単で、価格も比較的安価な製品が多く、初めてベースレイヤーを購入する方でも手に取りやすいでしょう。
撥水加工が施されたものや、異なる繊維を組み合わせることで機能性を高めた製品も数多く開発されています。
化学繊維のデメリット
ただし、保温性の面ではメリノウールに一歩譲る場合があります。繊維が空気を含む量が少ないため、特に停滞時の保温力はやや劣る傾向が見られます。
また、素材の特性上、皮脂や汗を栄養源とするバクテリアが繁殖しやすく、防臭加工が施されていない製品は、使用後に臭いが発生しやすいという欠点があります。
このため、数日間にわたる山行では使いにくいと感じるかもしれません。
代表的な化学繊維製品
化学繊維ベースレイヤーの中でも独自の地位を築いているのが、finetrack(ファイントラック)の「ドライレイヤー」シリーズです。これは肌の上に直接着用し、その上に吸汗速乾性のベースレイヤーを重ね着するという新しい考え方を提案した製品です。
肌から汗を素早く引き離し、濡れ戻りを徹底的に防ぐことに特化しており、汗冷え対策として非常に高い評価を得ています。
また、Patagonia(パタゴニア)の「キャプリーン・ミッドウェイト・クルー」も長年愛され続けている定番モデルです。リサイクルポリエステルを100%使用し、優れた吸湿発散性と防臭加工を備え、機能性と環境配慮を両立しています。
両方の利点を持つハイブリッド素材
天然素材のメリノウールと化学繊維、それぞれが持つメリットを両立させるために開発されたのが、ハイブリッド素材です。これは、二つの異なる素材を組み合わせることで、それぞれの長所を引き出し、短所を補い合うことを目的としています。
ハイブリッド素材には、主に二つのタイプが存在します。一つは、メリノウールと化学繊維の糸を混ぜて紡績する混紡タイプです。これにより、ウールの保温性や防臭性と、化繊の速乾性や耐久性をバランス良く両立させることができます。
もう一つのタイプは、肌に触れる面と外気に触れる面で異なる素材を配置する二層構造タイプです。
例えば、肌面には水分を素早く吸い上げるポリプロピレンを、外側には吸い上げた水分を拡散・蒸発させるポリエステルや、保温性を担うメリノウールを配置する、といった構造が挙げられます。これにより、各素材の機能を最大限に活かし、より高度な快適性を実現します。
もちろん、製品によって素材の組み合わせや比率が異なるため、保温性を重視するのか、速乾性を重視するのかなど、自分の求める性能に応じてモデルを選ぶことが大切です。
代表的なハイブリッド製品
二層構造タイプの代表例として、Teton Bros.(ティートンブロス)の「PPP(Power Wool Grid L/S)」が挙げられます。肌面に速乾性に優れたポリエステル、外側に保温性と調湿性に優れたメリノウールを配置したPolartec Power Woolを採用し、それぞれの素材の長所を最大限に引き出しています。
また、Arc’teryx(アークテリクス)の「Rho Hybrid Crew Neck」も人気の高いモデルです。
保温性と透湿性が求められる胴体部分には起毛フリース素材を、汗をかきやすい脇下にはストレッチ性と速乾性に優れた素材を配置するなど、部位によって素材を使い分けることで、快適な着心地を実現しています。
機能で比較するバックカントリーのベースレイヤーおすすめ
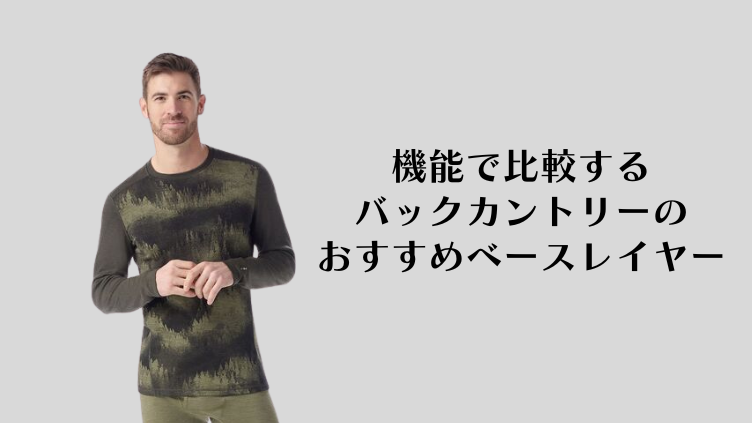
厳冬期向けの厚手モデルの選び方
気温が氷点下になることが常である厳冬期のバックカントリーでは、高い保温性を備えた厚手のベースレイヤーが不可欠です。一般的に「ヘビーウェイト」や「エクスペディションウェイト」と呼ばれるカテゴリーの製品がこれに該当します。
これらのモデルは、生地が厚く、起毛処理が施されていることが多く、デッドエアを豊富に溜め込むことで優れた断熱性を発揮します。
素材としては、保温力に定評のあるメリノウール100%のモデルや、保温性を維持しつつ汗処理能力を高めたメリノウールと化繊のハイブリッド素材が主流です。
例えば、icebreakerの「260 テック」シリーズやSmartwoolの「クラシックサーマルメリノベースレイヤー」などが代表的な製品です。
選ぶ際のポイントは、保温性だけでなく、ハイクアップ時の汗抜けも考慮することです。生地が厚すぎると、行動中に熱がこもりすぎてしまい、かえって大量の汗をかく原因にもなりかねません。
そのため、グリッド状のフリース構造を採用するなどして、保温性と通気性のバランスを追求したモデルがおすすめです。自身の寒さの感じ方や、行動強度に合わせて最適な厚さを選ぶことが大切になります。
最も汎用性が高い中厚手モデル
シーズンを通して最も活躍の機会が多いのが、「ミッドウェイト」と呼ばれる中厚手のベースレイヤーです。厳冬期から残雪期まで、幅広いシーズンとコンディションに対応できるバランスの良さが最大の魅力です。
中厚手モデルは、適度な保温性と優れた汗処理能力を兼ね備えています。これにより、行動中のオーバーヒートを防ぎつつ、休憩中の汗冷えを効果的に抑制します。
素材もメリノウール、化学繊維、ハイブリッドとバリエーションが豊富で、それぞれの特性を活かした多様な製品が展開されています。
前述したPatagoniaの「キャプリーン・ミッドウェイト」や、icebreakerの「200 オアシス」シリーズは、このカテゴリーの代表格と言えるでしょう。
どのような状況でも平均点以上のパフォーマンスを発揮してくれるため、最初に購入する一枚としても、この中厚手モデルを選ぶことをおすすめします。ミドルレイヤーとの組み合わせ次第で、体温調整の幅が大きく広がるのも利点です。
春スキーで活躍する薄手モデル
気温が上昇し、日差しも強くなる春先のバックカントリーシーズンでは、「ライトウェイト」や「シルクウェイト」に分類される薄手のベースレイヤーが快適です。この時期は、ハイクアップ中に大量の汗をかくことが予想されるため、保温性よりも汗を素早く処理する能力が優先されます。
薄手モデルの役割は、汗を素早く吸い上げて肌から遠ざけ、気化を促進することにあります。素材としては、速乾性に特化したポリエステルやポリプロピレンなどの化学繊維が最適です。
finetrackの「ドライレイヤーベーシック」のような肌をドライに保つことに特化した製品やArc’teryxの「Motus Crew Neck」のような通気性と速乾性に優れたモデルが選択肢になります。
ただし、薄手であるため保温性はほとんど期待できません。滑走中や稜線上で風に吹かれると肌寒く感じることがあるため、防風性のあるミドルレイヤーやシェルを必ず携行し、こまめに着脱して体温を調整することが重要です。
あくまで「汗を処理するためのアンダーウェア」と割り切り、保温は他のレイヤーで担うという考え方が求められます。
動きやすさを左右するフィット感
ベースレイヤーの性能を最大限に引き出すためには、体に合ったフィット感の製品を選ぶことが非常に大切です。ベースレイヤーは、肌と生地の間に隙間ができてしまうと、汗を効率的に吸い上げることができなくなってしまいます。
理想的なのは、体にぴったりと沿うようにフィットしつつも、動きを妨げない「スキンフィット」や「アスレチックフィット」と呼ばれるサイズ感です。生地が肌に密着することで、毛細管現象によって汗がスムーズに吸い上げられ、生地全体へと拡散していきます。
一方で、締め付けが強すぎると、血行を妨げたり、窮屈で不快に感じたりすることがあります。特に肩周りや腕の付け根、股関節など、可動域の大きい部分の動きやすさは入念に確認する必要があります。
多くのメーカーは、立体裁断やストレッチ性の高い素材を採用することで、フィット感と動きやすさを両立させています。可能であれば試着をして、腕を上げたり体をひねったりといった基本的な動作を行い、ストレスがないかを確認することをおすすめします。
効果を最大化するレイヤリング術
ベースレイヤーの性能は、それ単体で完結するものではなく、ミドルレイヤーやアウターシェルとの組み合わせ、つまりレイヤリングによってその効果が最大化されます。
レイヤリングの基本は、それぞれのウェアが持つ役割を正しく理解し、状況に応じて適切に組み合わせることです。
- ベースレイヤー(吸湿・速乾層): 肌に直接触れ、汗を吸い上げて拡散させる役割を担います。
- ミドルレイヤー(保温・通気層): ベースレイヤーが吸い上げた汗をさらに外へ逃がしつつ、デッドエアを溜め込んで体温を保持する役割です。フリースや化繊インサレーションなどがこれにあたります。
- アウターシェル(防風・防水層): 雨や雪、風から体を守る最も外側の層です。内側の湿気を外に逃がす透湿性も重要となります。
バックカントリーでは、行動中はベースレイヤーとシェルだけ、あるいはミドルレイヤーまで着用し、休憩中や気温が低い時には保温着を着込む、というように、こまめにウェアを着脱することが体温調整の基本です。
ベースレイヤーで吸い上げた汗を、ミドルレイヤーやシェルが効率的に外へ排出できなければ、結局ウェアの内側が濡れてしまいます。それぞれの層で透湿性や速乾性に優れたアイテムを選ぶことが、システム全体として機能させるための鍵となります。
まとめ:自分に合うバックカントリーのベースレイヤーおすすめを見つけよう
この記事では、バックカントリーにおけるベースレイヤーの選び方について、素材や機能の観点から詳しく解説してきました。最後に、最適な一枚を見つけるための重要なポイントをまとめます。
- ベースレイヤーの最も重要な役割は汗処理と体温調整
- 汗冷えはバックカントリーにおける深刻なリスクの一つ
- 素材は主にメリノウール、化学繊維、ハイブリッドの3種類
- メリノウールは優れた保温性と天然の防臭性が魅力
- メリノウールは濡れても急激に冷えにくい特性を持つ
- 化学繊維は卓越した速乾性と高い耐久性が長所
- 化学繊維は比較的安価で手入れがしやすい
- ハイブリッド素材は両者の長所をバランス良く兼ね備える
- 厳冬期には保温性を重視した厚手モデルが適している
- 幅広いシーズンで使える中厚手は最も汎用性が高い
- 春先の汗をかく時期には速乾性に優れた薄手モデルを選ぶ
- 性能を引き出すには体にフィットするサイズ感が不可欠
- レイヤリングシステム全体で汗処理を考えることが重要
- 活動強度や個人の汗のかきやすさを考慮して選ぶ
- 最終的には自分のスタイルに合ったものが最適解となる