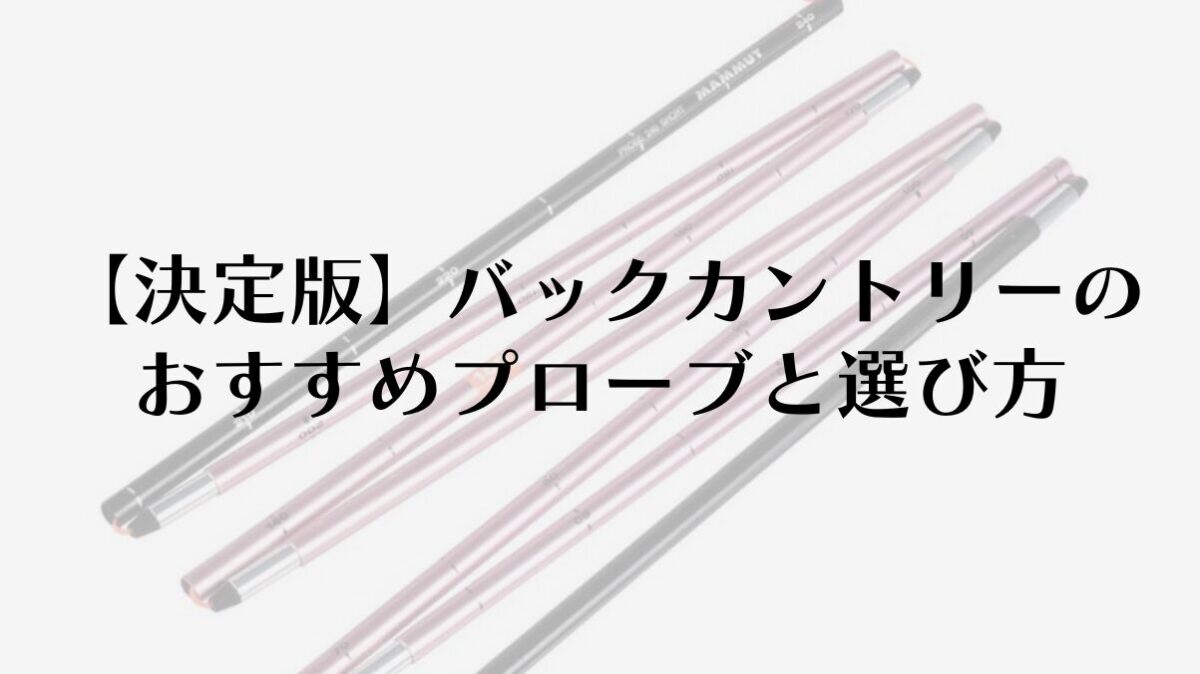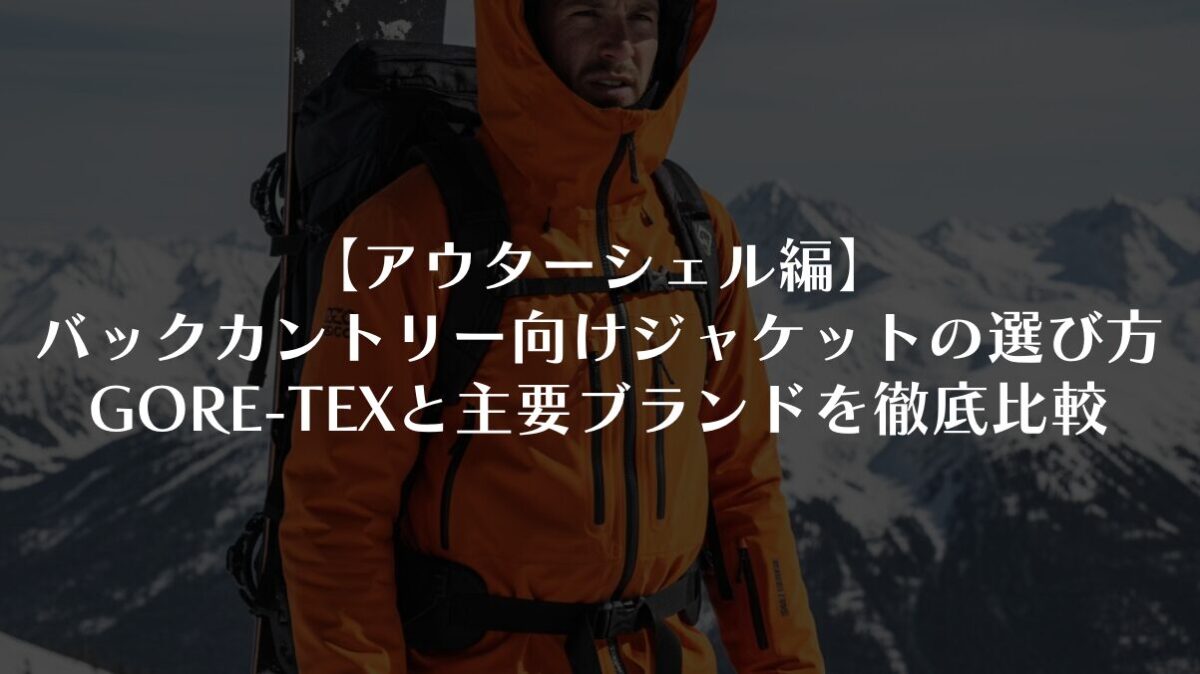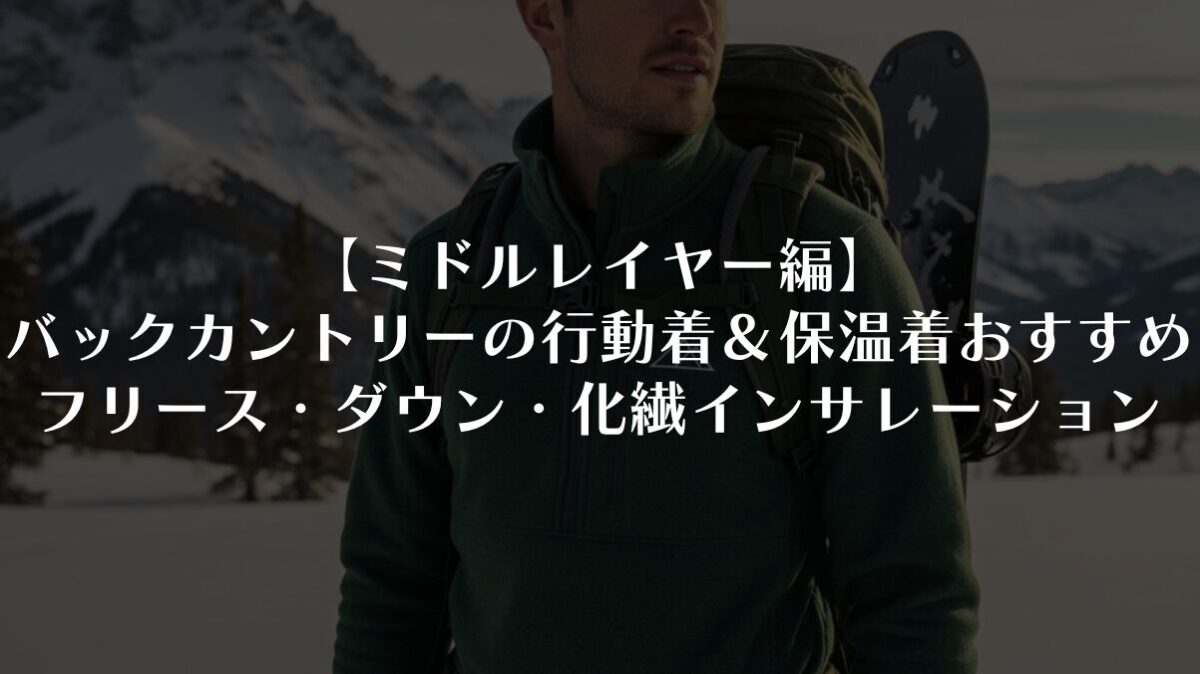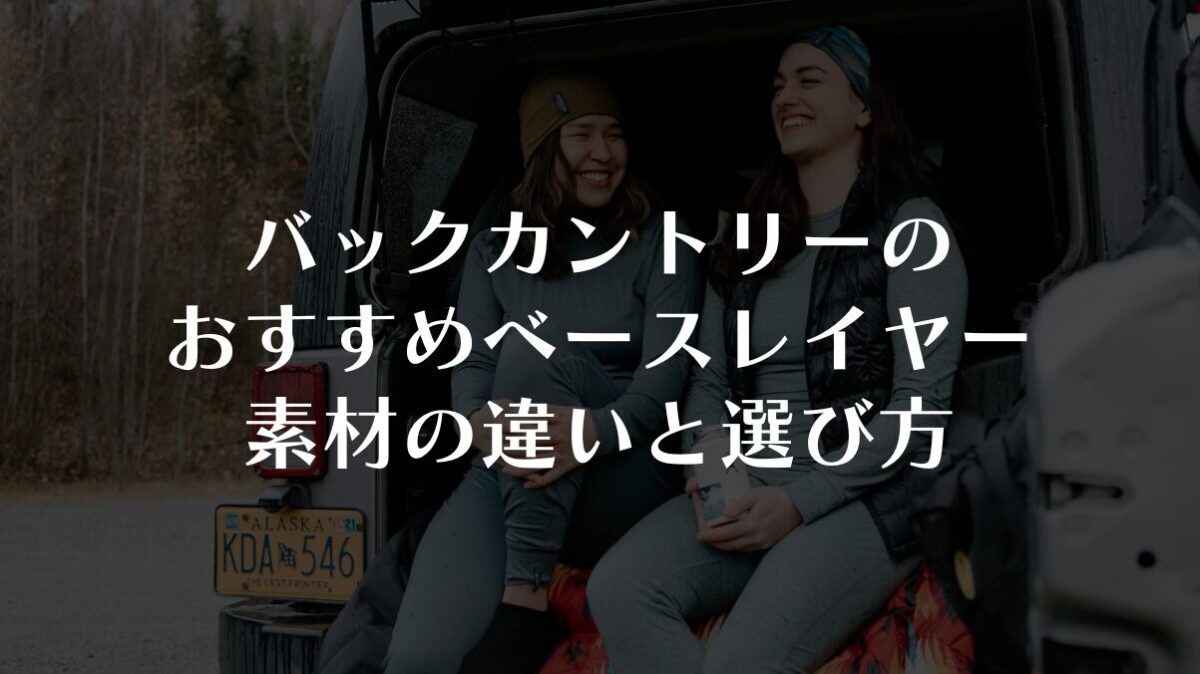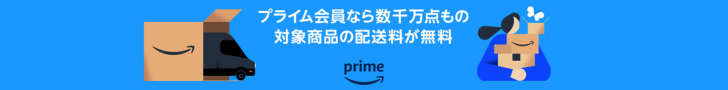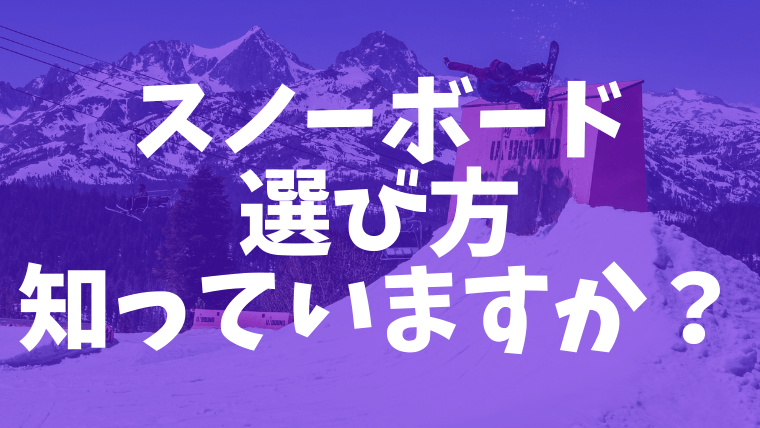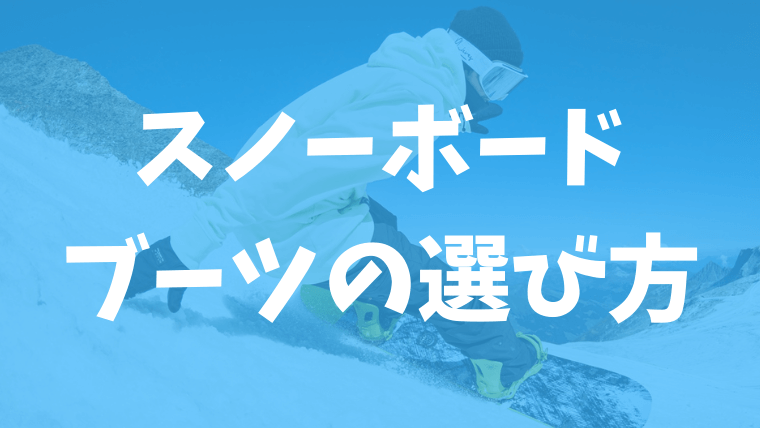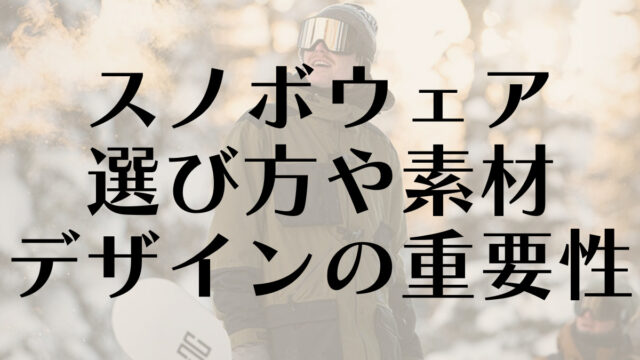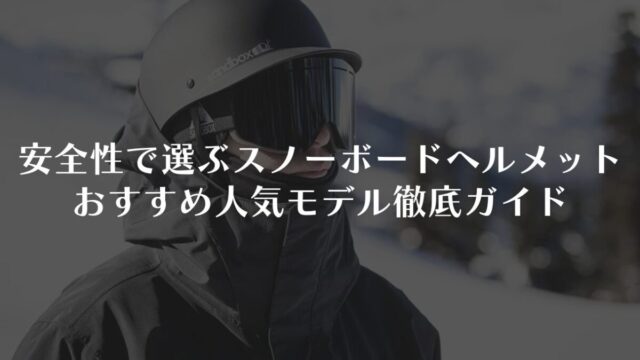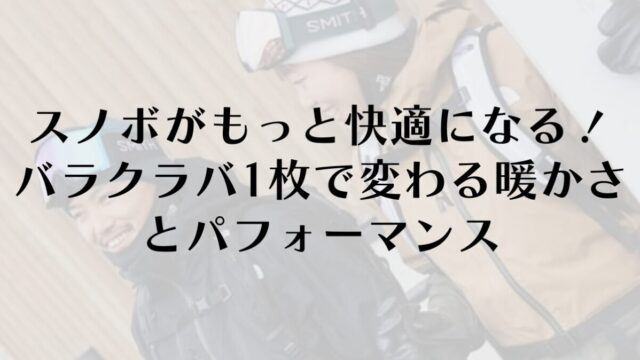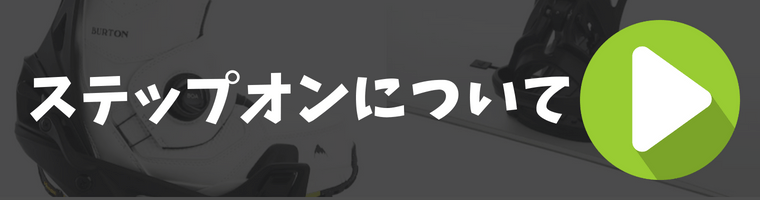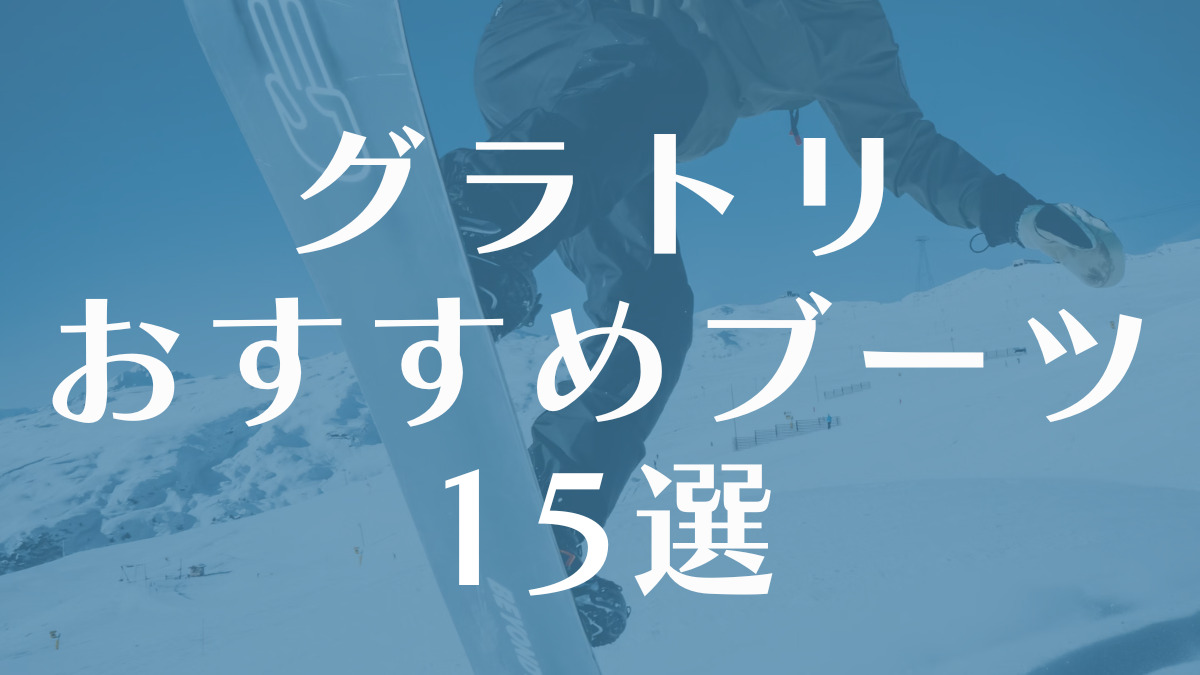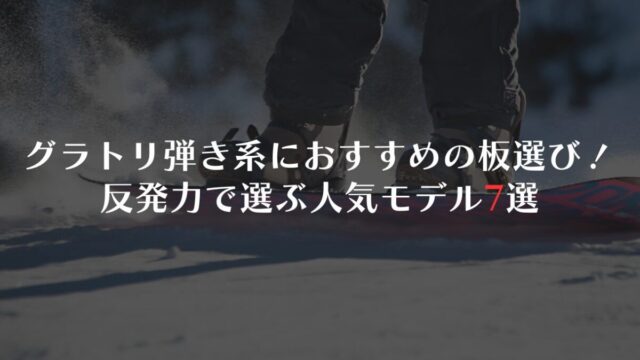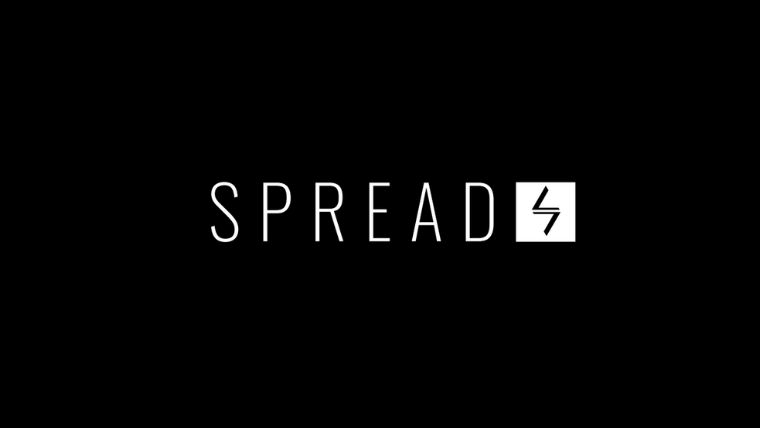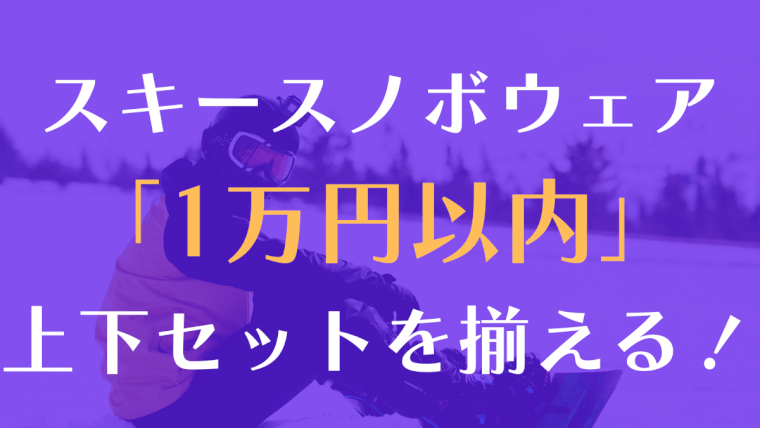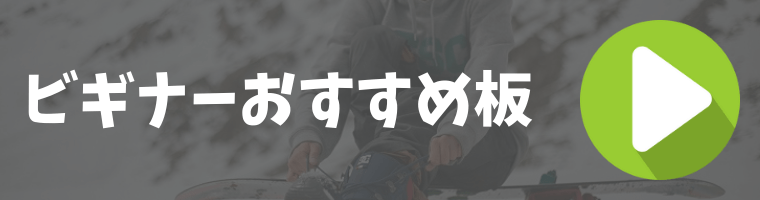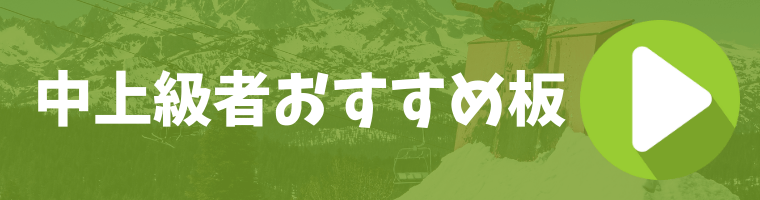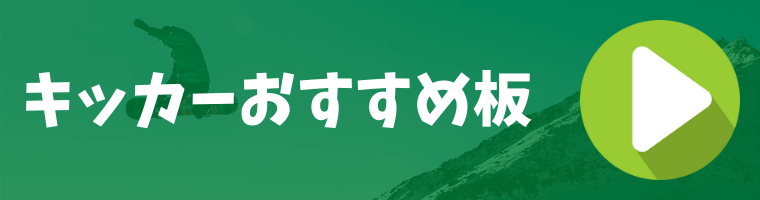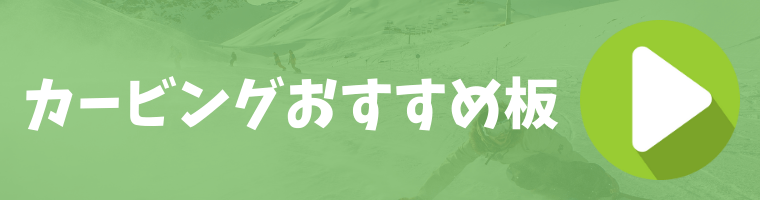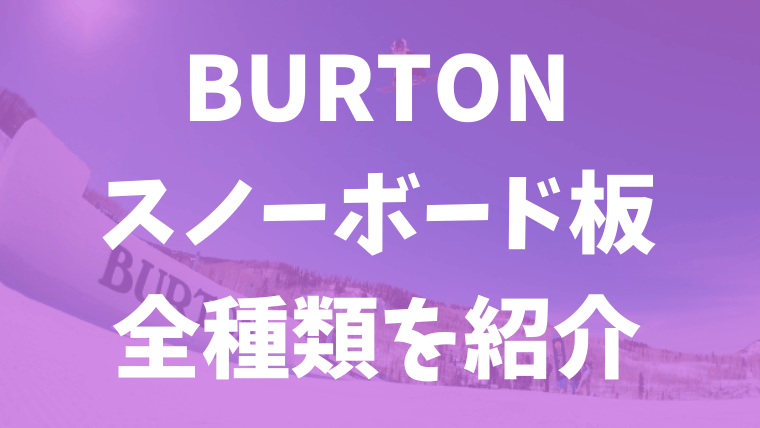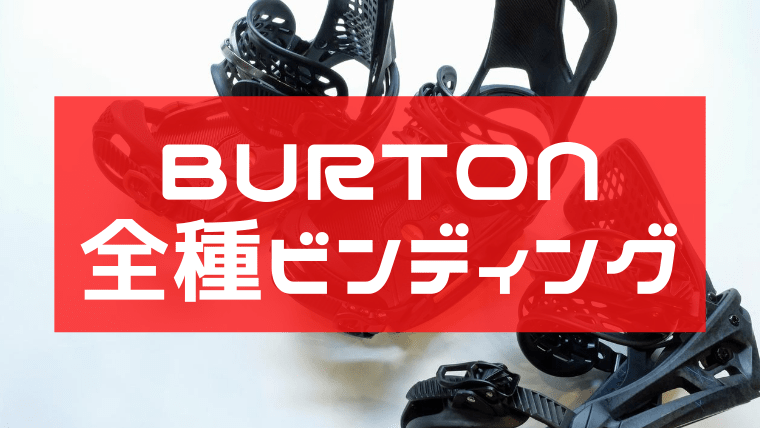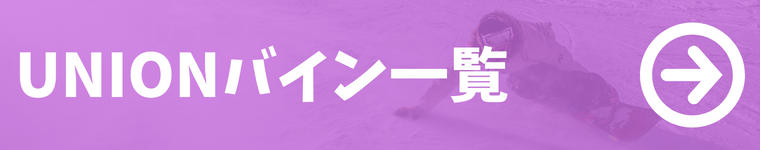【ウェア編】バックカントリーのレイヤリング術|汗冷えを防ぐ服装の基本

バックカントリーの広大な雪山を安全に楽しむためには、適切な準備が欠かせません。中でも、ウェアのレイヤリングは、快適性や安全性を直接左右する極めて重要な要素です。
ハイクアップでは大量の汗をかき、一方で滑走時や休憩中には急激に体温が奪われる環境下で、適切な体温調整を行うことが求められます。天候変化が激しい自然の中で、この服装の知識は汗冷えを防ぎ、パフォーマンスを維持するための生命線とも言えます。
この記事では、バックカントリー初心者の方にも分かりやすく、レイヤリングの基本的な考え方から実践的なテクニックまで、専門的な内容を丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。
- レイヤリングを構成する各層(ベース、ミドル、アウター)の具体的な役割
- メリノウールや化繊といった主要な素材の特性と選び方
- 行動中や休憩時など、状況に応じたウェア調整の実践的な方法
- 汗冷えを効果的に防ぎ、安全性を高めるための服装のポイント
なぜ重要?バックカントリーのウェアレイヤリングの基本

バックカントリー環境におけるレイヤリングは、単なる重ね着ではありません。それは、刻一刻と変化する気象条件や運動量に対応し、常に体をドライで快適な状態に保つための科学的なシステムです。ここでは、その基本となる各レイヤーの役割と、素材選びの考え方について掘り下げていきます。
- 汗冷えを防ぐベースレイヤーの役割
- 体温を保つミドルレイヤーの重要性
- 天候から身を守るアウターシェルの機能
- 天然の機能素材メリノウールの特徴
- 濡れに強い化繊素材のメリットとは
汗冷えを防ぐベースレイヤーの役割
バックカントリーで最も危険なことの一つが「汗冷え」です。ハイクアップ中に大量にかいた汗が肌面に残っていると、休憩中や滑走時に外気で冷やされ、急激に体温を奪います。これを防ぐのが、肌に直接触れるベースレイヤーの最も重要な役割です。
ベースレイヤーの主目的は保温ではなく、汗を素早く肌から吸い上げ、外側のミドルレイヤーへと透過させる「吸湿速乾性」にあります。
コットン(綿)のTシャツは汗を吸うと乾きにくく、濡れたまま肌に張り付いて体温を奪うため、バックカントリーでの使用は絶対に避けるべきです。
ベースレイヤーの素材選び
ベースレイヤーに使われる主な素材は「メリノウール」と「化繊」の2種類です。メリノウールは保温性と吸湿性に優れ、濡れてもある程度の暖かさを保ち、防臭効果が高いのが特徴です。
一方、化繊(ポリエステルなど)は汗を吸い上げるスピードと乾きの速さが非常に優れており、耐久性も高いという利点があります。
さらに、より安全性を追求する方には、これらの吸湿速乾性ベースレイヤーの下に「ドライ系アンダーウェア」を着用することも推奨されます。
ファイントラック社の「ドライレイヤー」に代表されるこの種のウェアは、汗を透過させることに特化しており、肌面を常にドライに保つ効果をさらに高めてくれます。
体温を保つミドルレイヤーの重要性
ミドルレイヤーは、ベースレイヤーが吸い上げた汗をさらに外へ逃がしつつ、体から発せられる熱を空気の層として蓄えることで「保温」の役割を担います。
デッドエア(動かない空気の層)をいかに効率良く作り出すかが、ミドルレイヤーの性能の鍵となります。
ミドルレイヤーには様々な種類があり、状況に応じて使い分けることが大切です。主な素材としては、フリース、ダウン、化繊インサレーションが挙げられます。
ミドルレイヤーの種類と特徴
- フリース: 通気性と速乾性に優れ、行動中に着続けるミドルレイヤーとして非常に優秀です。パタゴニア社の「R1エア」シリーズのように、適度な保温性と高い通気性を両立したモデルは、ハイクアップ時の行動着として定番となっています。
- ダウン: 軽量でコンパクトに収納でき、重量に対する保温性が最も高い素材です。ただし、水濡れに弱く、濡れると保温力が著しく低下するという弱点があります。そのため、主に休憩中や滑走時にアウターシェルの上から羽織る「保温着」として使用するのが一般的です。
- 化繊インサレーション: ダウンの弱点である水濡れに強く、濡れても保温性を維持しやすいのが最大の特徴です。アークテリクス社の「アトム フーディ」などが代表的で、ダウンほどの軽さやコンパクトさはありませんが、汗や湿気で濡れる可能性がある状況でも安心して使用できる信頼性があります。
天候から身を守るアウターシェルの機能
アウターシェルは、レイヤリングシステムの最も外側に位置し、雪・風・雨といった外部の厳しい天候から体を守る「防護壁」の役割を果たします。
防水性や防風性が高いことはもちろんですが、同時に、内側からの汗や湿気を外に排出する「透湿性」を兼ね備えていることが極めて重要です。
アウターシェルには大きく分けて「ハードシェル」と「ソフトシェル」の2種類があります。
ハードシェルとソフトシェルの使い分け
- ハードシェル: ゴアテックス(GORE-TEX)に代表される防水透湿素材を使用しており、完全な防水性と高い防風性を誇ります。降雪や強風が予想される厳しいコンディションでは必須の装備です。アークテリクス社の「ベータ ジャケット」など、耐久性と機能性を両立したモデルが人気です。
- ソフトシェル: 優れたストレッチ性とハードシェルを上回る高い通気性が特徴です。完全防水ではありませんが、ある程度の撥水性と防風性を備えています。汗を大量にかくハイクアップ時には、蒸れを効果的に排出し、快適な行動をサポートしてくれます。晴天時や降雪の少ない日の行動着として非常に適しています。
天然の機能素材メリノウールの特徴
メリノウールは、メリノ種という羊から採れる天然の高機能素材であり、特にベースレイヤーやソックスの素材として絶大な人気を誇ります。その最大の理由は、優れた機能性と快適な着心地にあります。
メリノウールのメリットとデメリット
メリノウールが持つ主な長所は、高い保温性、優れた吸湿性、そして天然の防臭効果です。ウール繊維は湿気を吸収する際に「吸着熱」を発生させるため、汗をかいても冷たさを感じにくく、濡れた状態でもある程度の保温性を維持します。
また、繊維の構造がバクテリアの繁殖を抑制するため、長期間の山行でも臭いが発生しにくいのが大きなメリットです。
一方で、デメリットも存在します。化繊素材と比較すると、汗を吸った後の乾燥速度はやや遅く、摩擦に対する耐久性も劣る傾向があります。価格も比較的高価になることが多いです。
これらの特性から、発汗量がそこまで多くない方や、着心地、防臭性を重視する方に特に適している素材と言えるでしょう。代表的なブランドには「スマートウール」や「アイスブレーカー」があります。
濡れに強い化繊素材のメリットとは
化繊(化学繊維)、特にポリエステルやポリプロピレンは、バックカントリーウェアにおいてメリノウールと並ぶもう一つの主要な素材です。その最大のメリットは、水との相性の良さ、つまり「疎水性」の高さにあります。
化繊素材のメリットとデメリット
化繊の繊維は、水分をほとんど吸収しません。そのため、肌から吸い上げた汗を素早く次のレイヤーへと受け渡し、生地自体も驚くほど速く乾きます。
この速乾性は、大量に汗をかく状況での汗冷えリスクを大幅に軽減してくれます。また、非常に丈夫で摩擦に強く、繰り返し洗濯しても性能が劣化しにくい点や、比較的手頃な価格である点も大きな魅力です。
デメリットとしては、汗に含まれる皮脂などを栄養源にバクテリアが繁殖しやすく、メリノウールに比べて臭いが発生しやすい点が挙げられます。
ただし、近年では銀イオンなどを練り込む防臭加工が施された製品も増えており、この弱点は改善されつつあります。大量の汗をかくことが予想される場合や、速乾性と耐久性を最優先したい場合には、化繊素材が最適な選択肢となります。
素材比較:メリノウール vs 化繊
| 特性 | メリノウール | 化繊(ポリエステルなど) |
|---|---|---|
| 保温性 | 高い(濡れても保温性を維持) | 中程度(濡れると低下しやすい) |
| 吸湿性 | 非常に高い | 低い(吸湿はしない) |
| 速乾性 | やや遅い | 非常に速い |
| 防臭性 | 非常に高い(天然の効果) | 低い(防臭加工で対応) |
| 耐久性 | やや低い | 高い |
| 価格 | 高価 | 比較的安価 |
| 着心地 | 柔らかく、肌触りが良い | 製品によるが、一般的に滑らか |
実践的なバックカントリーウェアレイヤリングの調整術

レイヤリングの基本を理解したら、次はそれを実際のフィールドでいかに運用するかが重要になります。運動量や天候がめまぐるしく変わるバックカントリーでは、「面倒くさがらずに、こまめにウェアを調整すること」が、快適性と安全性を保つ最大の秘訣です。
- ハイクアップで快適な行動着の組み合わせ
- 休憩・滑走時に追加する保温着の選び方
- 衣服内の蒸れを逃がす通気性の確保
- 汗を素早く乾かす速乾性の必要性
- バックパックに収納する予備ウェア
ハイクアップで快適な行動着の組み合わせ
ハイクアップ(登高)中は、バックカントリーで最も運動量が多く、大量の汗をかく時間帯です。ここでの目標は「オーバーヒート(暑くなりすぎ)しないこと」です。少し肌寒いと感じるくらいの服装で歩き始めるのが、結果的に最も快適な状態を維持できるコツです。
一般的な晴天時のハイクアップでは、「ドライ系アンダー+吸湿速乾性ベースレイヤー」の上に、通気性の高いソフトシェルジャケットを羽織る、あるいは薄手のフリースを着る、といった組み合わせが基本となります。
風が弱い場合や気温が高い場合は、ベースレイヤー1枚で行動することも少なくありません。
重要なのは、汗でウェアが濡れ切ってしまう前に、ジッパーを開けたり、アウターを脱いだりして積極的に換気を行うことです。暑さを我慢して汗をかきすぎると、その後の汗冷えのリスクが格段に高まります。
休憩・滑走時に追加する保温着の選び方
ハイクアップを終え、休憩に入ったり滑走の準備を始めたりすると、運動量が急激に低下し、体が冷え始めます。
特に汗で濡れたウェアを着ている場合は、風に吹かれるとあっという間に体温が奪われます。このタイミングで、バックパックから保温着を取り出して素早く羽織ることが非常に大切です。
この時に使用する保温着は、軽量でコンパクトに収納でき、かつ高い保温力を持つダウンジャケットや化繊インサレーションジャケットが最適です。
パタゴニア社の「ダウン・セーター」やアークテリクス社の「セリウム フーディ」のように、ザックの隅にコンパクトに収まるモデルが重宝します。
ポイントは、行動着の上からそのまま羽織ることです。一度アウターを脱いでから着るのではなく、シェルの上からでも着られる少し大きめのサイズを用意しておくと、素早く体を保温でき、熱を逃がしません。
衣服内の蒸れを逃がす通気性の確保
ウェア内部の蒸れ、つまり湿気をいかに効率よく外に排出するかは、レイヤリングの成否を分ける重要な要素です。この「通気性(ベンチレーション)」を確保することで、ウェア内をドライに保ち、結露や汗冷えを防ぐことができます。
最も効果的なのは、ウェアに備わっているベンチレーション機能を積極的に活用することです。多くのシェルジャケットには、脇の下に「ピットジップ」と呼ばれる大きなジッパーが付いています。これを全開にするだけで、衣服内の熱気と湿気を劇的に排出することが可能です。
また、フロントジッパーの開閉や、パンツのサイドジッパーなども有効なベンチレーション手段です。さらに、フリースやソフトシェルのように、素材自体が高い通気性を持つウェアを行動着として選ぶことも、蒸れを防ぐ上で非常に効果的なアプローチとなります。
汗を素早く乾かす速乾性の必要性
前述の通り、ベースレイヤーやミドルレイヤーには、汗を素早く乾かす「速乾性」が強く求められます。どれだけ通気性を確保しても、ある程度の発汗は避けられません。その汗がウェアに留まり続けると、不快なだけでなく、汗冷えの直接的な原因となってしまいます。
特に、大量に汗をかく体質の方や、運動強度の高い行動を予定している場合は、メリノウールよりも速乾性に優れる化繊素材のベースレイヤーを選択する方が、より安全で快適な状態を維持しやすくなります。
また、速乾性はウェア内部の環境を快適に保つだけでなく、万が一濡れてしまった際のリカバリーにも繋がります。
例えば、山小屋での休憩中や、晴れ間が出た短い時間でも、速乾性の高いウェアは素早く乾き、次の行動に備えることができます。この性能は、数日間にわたるツアーなどでは特に重要性を増します。
バックパックに収納する予備ウェア
万全の準備をしても、予期せぬ天候の悪化や転倒などでウェアが完全に濡れてしまう可能性はゼロではありません。
そのような不測の事態に備えて、バックパックには最低限の予備ウェアを必ず収納しておくべきです。これは、安全を確保するための重要な保険となります。
最低限持っていくべき予備ウェアは以下の通りです。
- 予備のベースレイヤー: 汗や雪で濡れた際に着替えることで、低体温症のリスクを大幅に減らせます。
- 予備のグローブ: グローブは最も濡れやすく、また手がかじかむとあらゆる作業が困難になります。薄手のライナーと厚手のオーバーグローブをそれぞれ1セットずつ予備として持っていくと安心です。
- 予備のビーニー(帽子)やバラクラバ: 頭部からの放熱は非常に大きいため、濡れた帽子を乾いたものに交換するだけで体感温度は大きく変わります。
これらの予備ウェアは、防水性のあるスタッフサックなどに入れて、ザックの中で濡れないようにパッキングしておくことが重要です。
最後に:最適なバックカントリーウェアレイヤリングで安全に
この記事では、バックカントリーにおけるウェアレイヤリングの基本から実践までを解説しました。最後に、安全で快適な山行を実現するための重要なポイントを改めてまとめます。
- レイヤリングの目的は体温調整と汗の管理
- ベースレイヤーは汗を肌から遠ざける役割
- ミドルレイヤーは空気を蓄え保温する役割
- アウターシェルは雪や風から体を守る防護壁
- 汗冷えは低体温症に繋がる最も危険な状態の一つ
- 綿(コットン)素材の着用は絶対に避ける
- メリノウールは保温性と防臭性に優れる
- 化繊素材は速乾性と耐久性が高い
- ハイクアップ中は少し寒いくらいの服装で始める
- 暑さを感じたら我慢せず、こまめに換気する
- ピットジップなどのベンチレーションを積極的に活用する
- 休憩中はすぐに保温着を追加して体を冷やさない
- 保温着は行動着の上から羽織るのが効率的
- 状況に応じてレイヤーを脱ぎ着することを面倒くさがらない
- 予備のベースレイヤーやグローブを必ず携行する