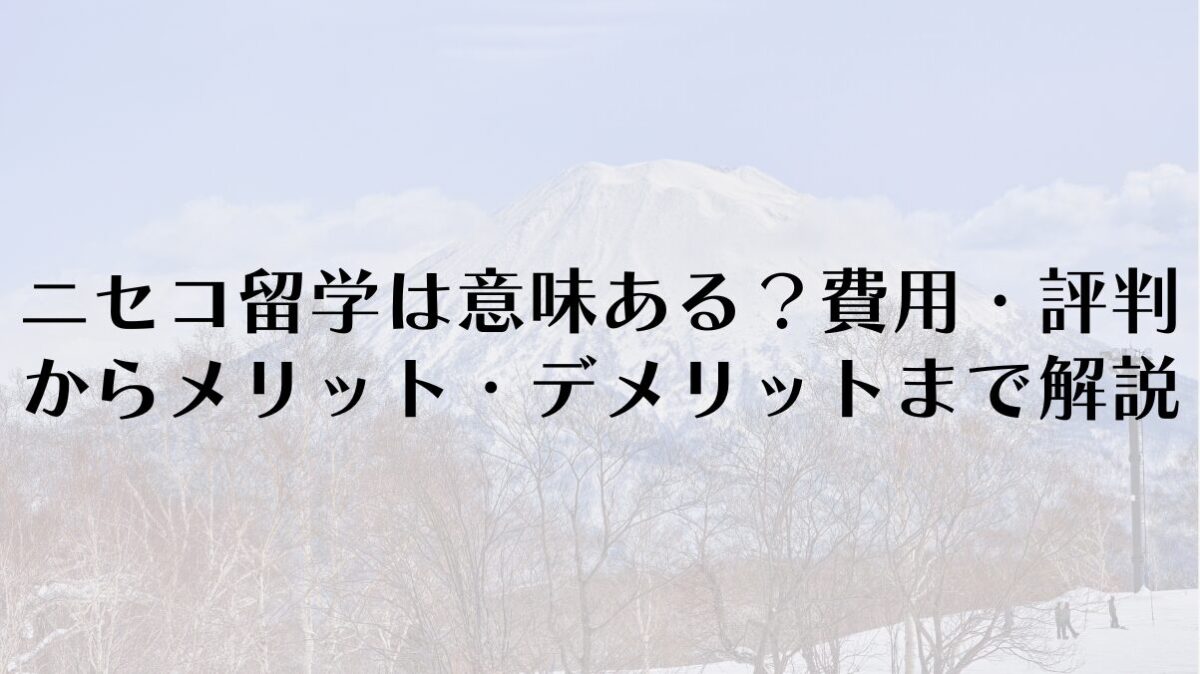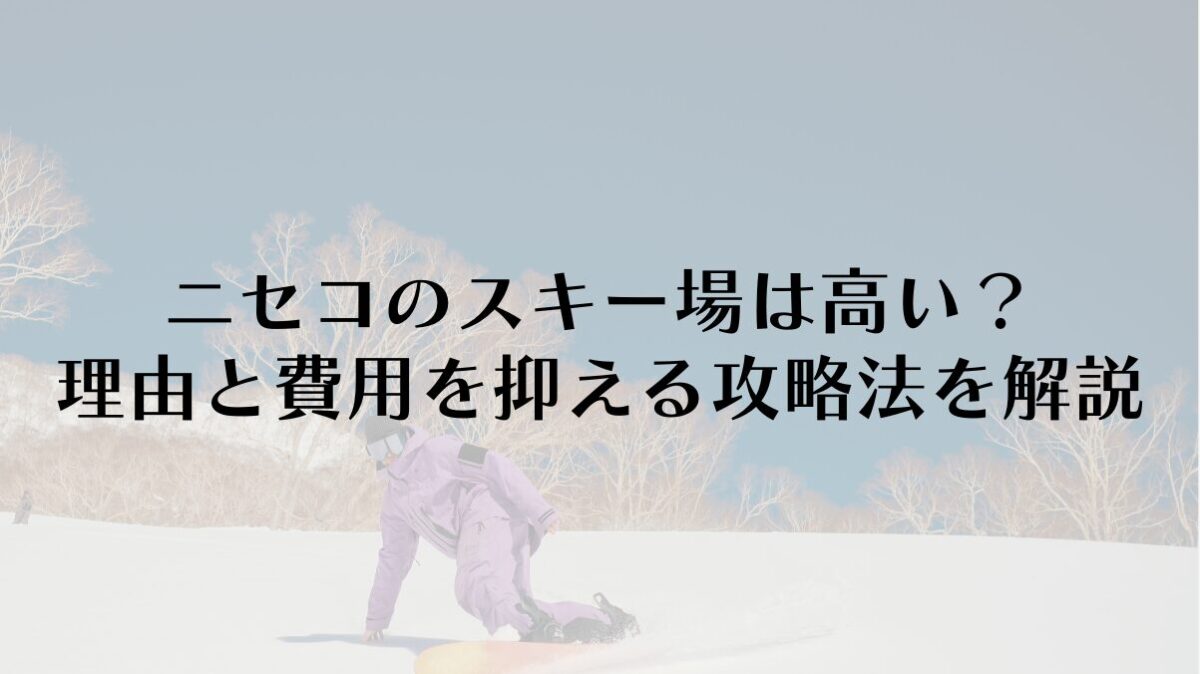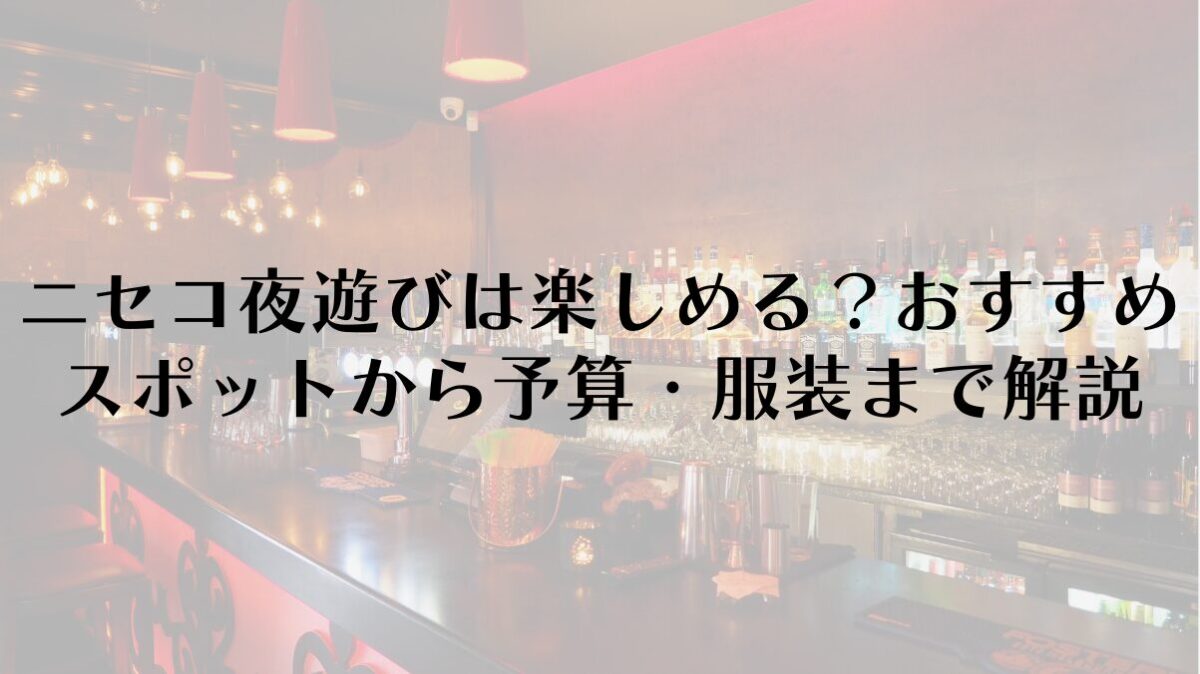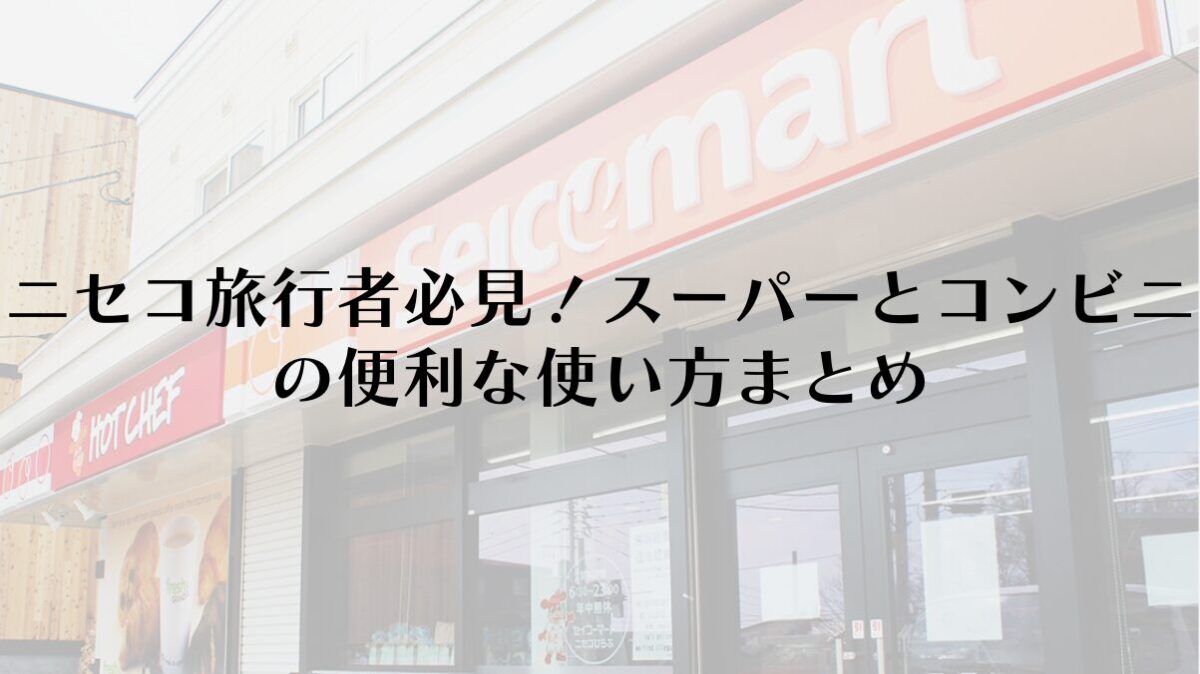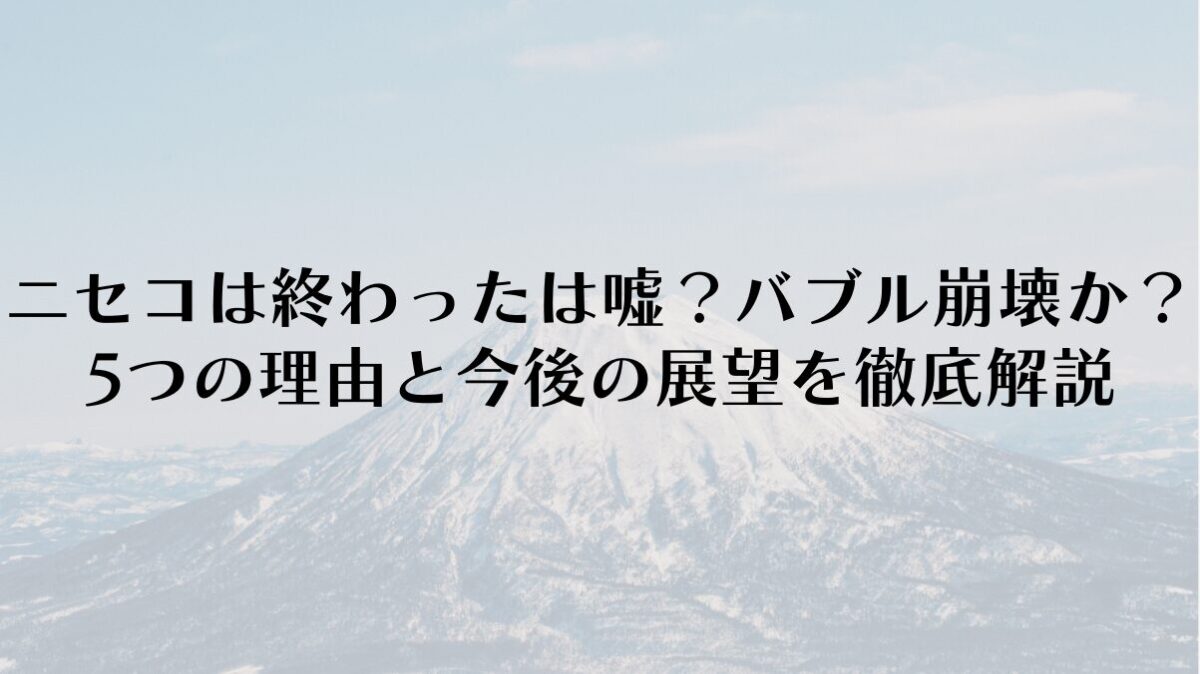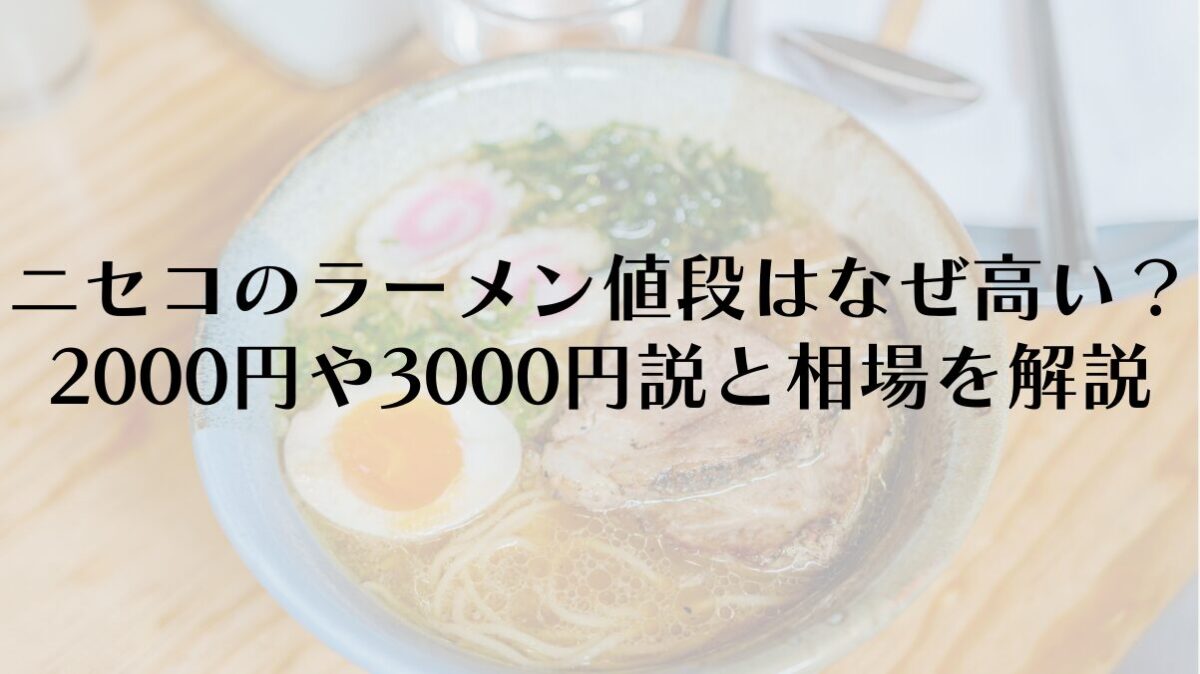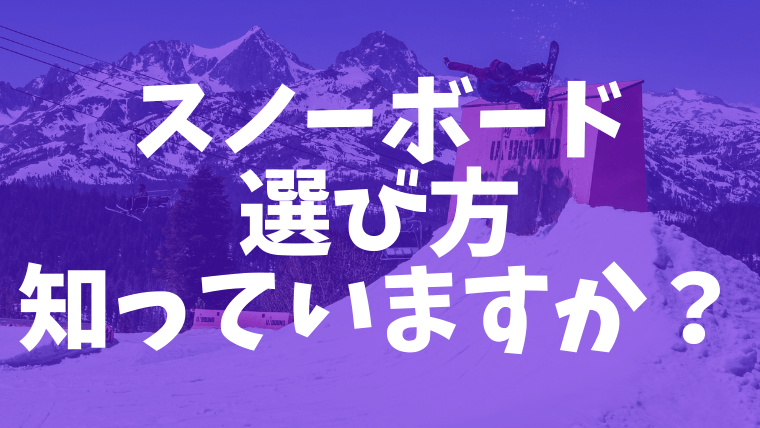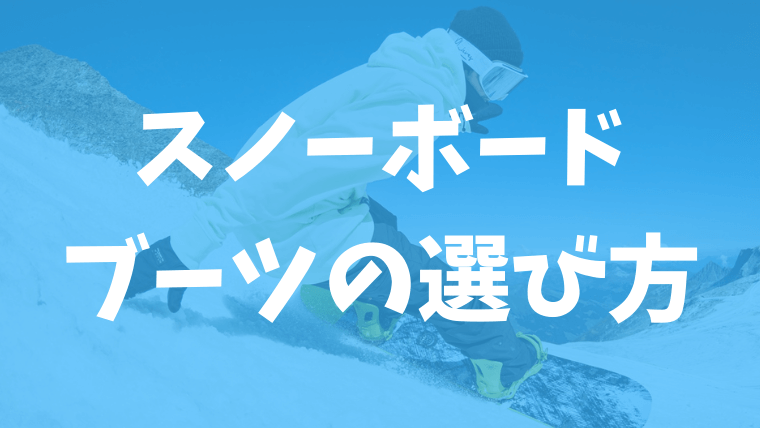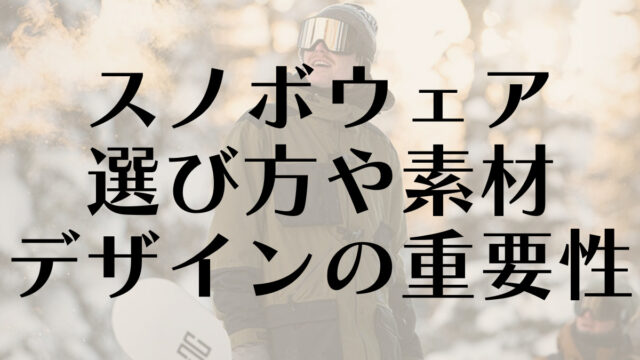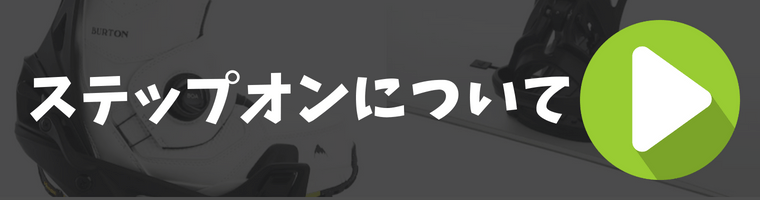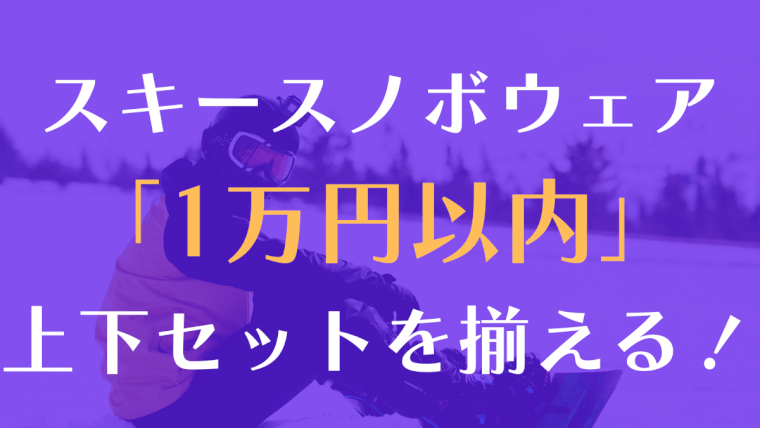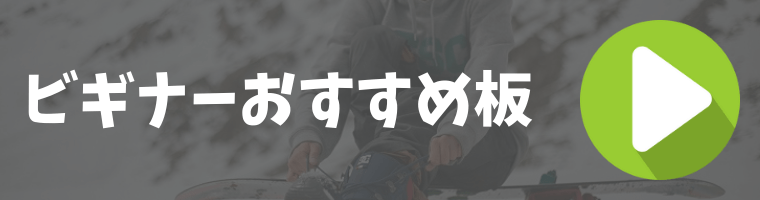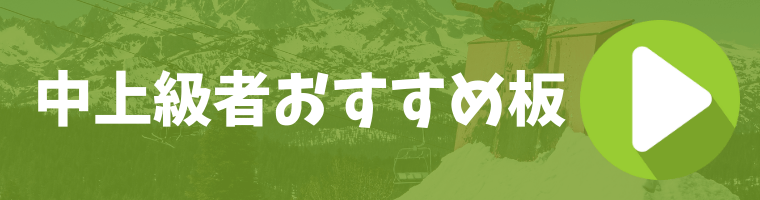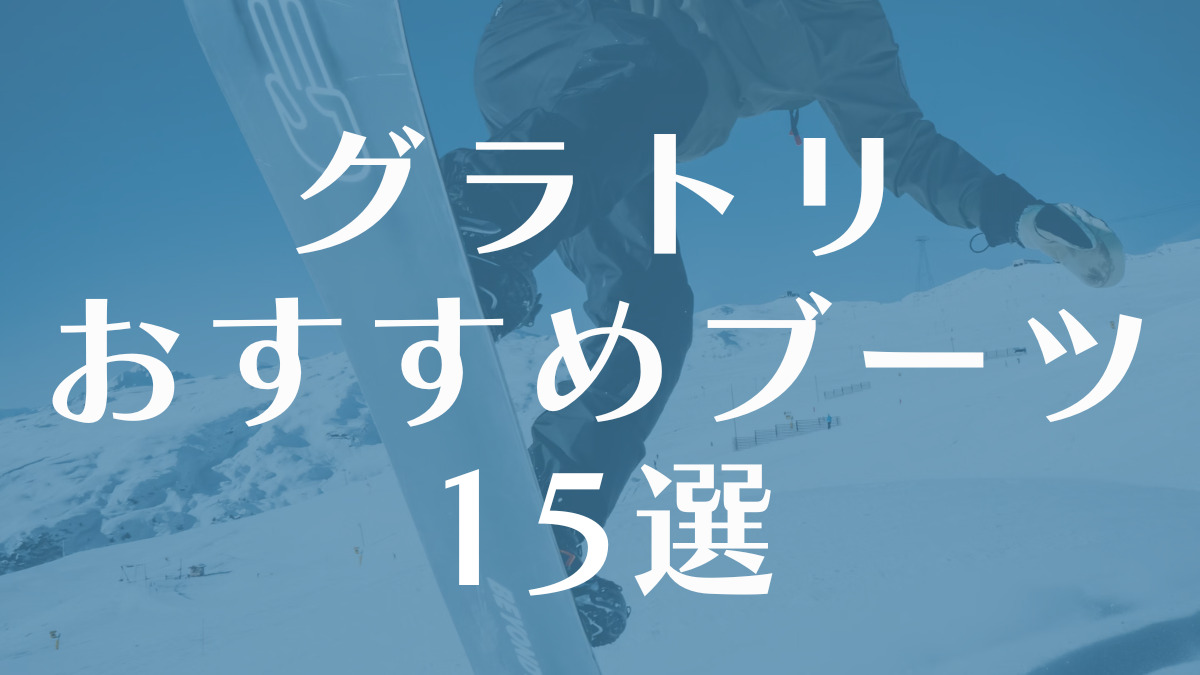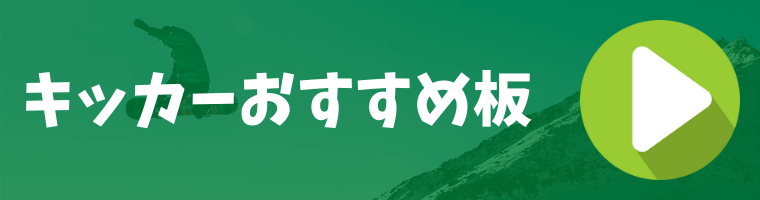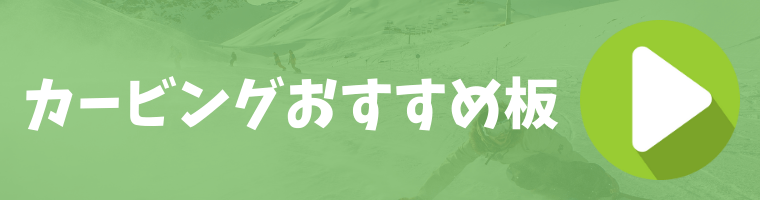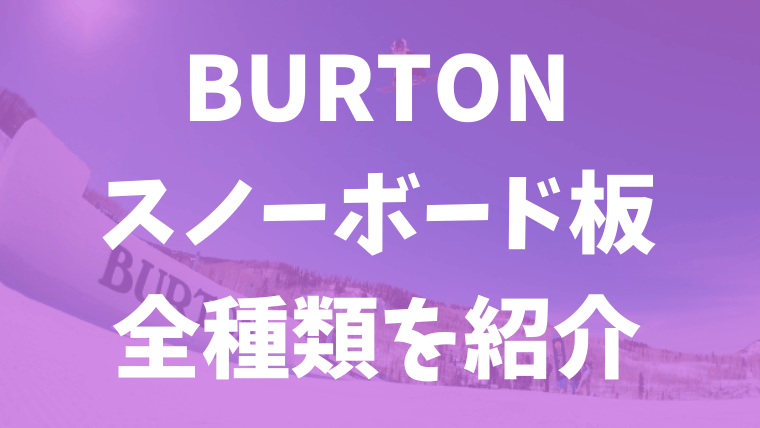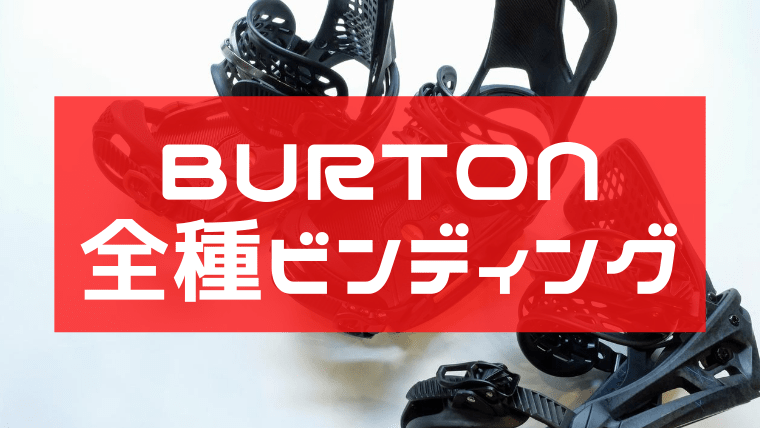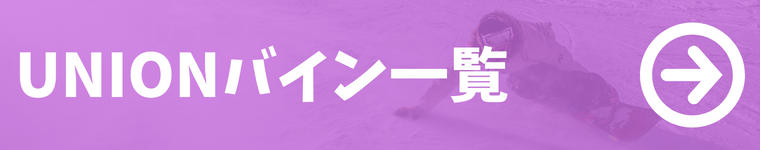ニセコは終わったは嘘?バブル崩壊か?5つの理由と今後の展望を徹底解説
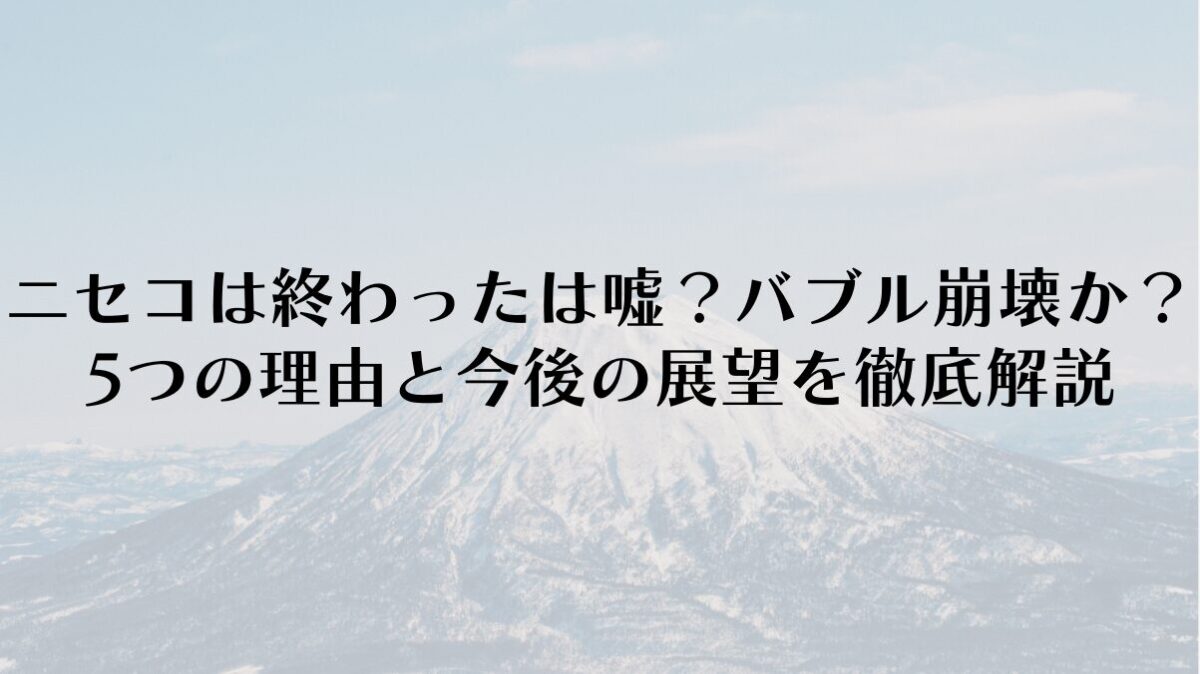
近年、ニセコではホテル廃業や観光客減少のニュースが報じられ、長期化したコロナ禍影響も相まって、一時期の勢いを支えた不動産バブルの崩壊や地価下落が囁かれています。
しかし一方で、インバウンド回復への大きな期待も寄せられており、「ニセコは本当に終わってしまったのか」と疑問に思う方も少なくありません。この記事では、現状を多角的な視点から分析し、今後の展望までを詳しく解説します。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
- 「ニセコ 終わった」と言われる具体的な背景
- 不動産や地価に関する客観的なデータ
- 観光客数の現状と今後の回復見込み
- ニセコが抱える課題と将来の可能性
「ニセコは終わった」と言われる5つの背景

ニセコの不動産バブル崩壊は現実か
ニセコが「終わった」と言われる一因に、不動産バブルの崩壊が挙げられます。結論から言うと、一部価格の調整は見られるものの、全面的なバブル崩壊には至っていないのが現状です。
なぜなら、これまでニセコの不動産市場は、海外の富裕層による旺盛な投資需要に支えられ、異常とも言える高騰を続けてきました。特に倶知安町ヒラフ地区のコンドミニアムなどは、都心の一等地をもしのぐ価格で取引されていたのです。
しかし、世界的な金融情勢の変化や、コロナ禍による投資意欲の一時的な減退が、この加熱した市場に冷や水を浴びせた形になりました。
例えば、これまで強気な価格設定で売りに出されていた物件が、価格を見直したり、売れ残ったりするケースが散見されるようになりました。
これは、市場が過熱状態から冷静さを取り戻し、より現実的な価格帯へと調整されつつある過程と捉えることができます。
したがって、これを「バブル崩壊」と断定するのは早計であり、むしろ市場の健全化に向けた動きと見ることも可能です。
ただし、今後の世界経済の動向次第では、さらなる価格下落のリスクも依然として残されている点には注意が必要でしょう。
データで見る観光客減少の深刻度
ニセコエリアの観光客数、特に外国人観光客が大幅に減少したことは、データ上も明らかです。この事態が、「ニセコは終わった」という印象を強める大きな要因となっています。
最大の理由は、言うまでもなく新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う国際的な渡航制限です。
ニセコの経済は、冬のパウダースノーを求めて訪れる海外からのスキー客に大きく依存していたため、国境が閉ざされたことによる打撃は計り知れないものでした。
倶知安町が公表している入込客数データを見ると、パンデミック以前の2018年度には延べ約175万人の外国人宿泊客が訪れていましたが、2021年度には数万人規模にまで激減しました。
これは、地域の宿泊施設や飲食店、アクティビティ事業者にとって、死活問題であったと言えます。日本人観光客だけでは、この大きな穴を埋めることは到底不可能でした。
この観光客の蒸発が、地域の活気を失わせ、「ニセコのブームは去った」というイメージを植え付ける結果につながったと考えられます。
相次ぐホテル廃業のニュースの真相
「ニセコでホテルの廃業が相次いでいる」というニュースも、ブーム終焉説を後押ししています。しかし、この背景を詳しく見ると、必ずしもネガティブな側面だけではないことが分かります。
確かに、前述の通り、コロナ禍による観光客の激減は、多くの宿泊施設の経営を直撃しました。
運転資金の確保が困難になったり、将来を悲観したりして、事業継続を断念した小規模なペンションやホテルがあったのは事実です。
これらのニュースは、ニセコの苦境を象徴するものとして大きく報じられました。一方で、注目すべきは、廃業した施設がその後どうなっているかという点です。
実は、廃業した施設の多くは、国内外の新しい資本によって買収され、より大規模で現代的な宿泊施設へと生まれ変わるための準備期間に入っているケースが少なくありません。
例えば、古いロッジが取り壊され、高級コンドミニアムや外資系のラグジュアリーホテルの建設予定地となっている事例が複数見られます。
つまり、一連の廃業は、単なる衰退ではなく、地域の新陳代謝や施設のアップグレードが進む過程で起きている現象と捉えることもできるのです。
ピークアウトか?ニセコの地価下落
ニセコエリアの地価は、全国でもトップクラスの上昇率を誇ってきましたが、近年その勢いに陰りが見え始めています。これも「ピークアウトした」と言われる理由の一つです。
国土交通省が発表する公示地価において、倶知安町の商業地は長年、全国一の上昇率を記録してきました。
しかし、最新のデータでは上昇率が鈍化、あるいはごくわずかに下落する地点も現れました。これは、過熱し続けた地価が、ついに天井に達したのではないかという見方を広める要因になっています。
近年の地価変動率の推移(倶知安町の商業地)
| 公表年 | 変動率 | 備考 |
|---|---|---|
| 2020年 | +57.5% | 5年連続で全国1位 |
| 2021年 | +25.0% | 上昇率は鈍化 |
| 2022年 | +8.1% | さらに上昇率は低下 |
| 2023年 | +11.8% | 再び上昇に転じる |
| 2024年 | +19.7% | 回復傾向が鮮明に |
上の表が示すように、上昇率は確かに一時鈍化しましたが、再び回復基調にあります。
地価の伸びが緩やかになった背景には、これまでの急騰に対する警戒感や、前述の不動産市場の調整、そしてコロナ禍による先行きの不透明感が複合的に影響していると考えられます。
ただ、依然として全国的に見れば高い水準の上昇を維持しており、地価が暴落しているわけではありません。市場が新たな局面に入った可能性はありますが、これを以て「ニセコの価値が終わった」と結論付けるのは時期尚早と言えるでしょう。
長期化したコロナ禍影響の爪痕
ニセコ経済が受けたコロナ禍の影響は、観光客の減少だけに留まりません。地域社会の隅々にまで及んだ爪痕が、現在の閉塞感につながっています。
最も深刻な問題の一つが、労働力不足です。インバウンド観光客と共に、ニセコの冬を支えていたのは、ワーキングホリデーなどで訪れる多くの外国人材でした。
しかし、渡航制限によって彼らがいなくなり、多くの宿泊施設や飲食店が深刻な人手不足に陥ったのです。
この問題は、観光客が戻りつつある現在も解消されておらず、受け入れ態勢の大きな足かせとなっています。
また、地域イベントの中止や縮小も、町の活気を削ぐ一因となりました。多くの人々が集まる祭りがなくなり、住民や観光客同士の交流の機会が失われたことは、数字には表れないマイナス影響と言えます。
さらに、一部の事業者は、コロナ禍で受けた経済的ダメージから立ち直れずにいます。これらの複合的な要因が、地域全体の雰囲気に影を落とし、「ニセコは以前のような輝きを失った」という印象を与えているのです。
「ニセコが終わった」というにはまだ早い?今後の展望

今なお続くコンドミニアム建設ラッシュ
「ニセコは終わった」という声とは裏腹に、現地では大規模な開発が今なお続いています。これが、ニセコの未来が悲観的なだけではないことを示す強力な証拠です。
コロナ禍で一時的に停滞したプロジェクトもありましたが、ヒラフ地区を中心に、高級コンドミニアムやホテルの建設クレーンが林立している光景は変わりません。
これらの開発の多くは、国内外の大手デベロッパーや有名ホテルブランドが手掛けており、数年先を見据えた巨額の投資が行われています。
例えば、リッツ・カールトンやアマンといった世界的なラグジュアリーブランドが、ニセコエリアに新たなリゾートの開業を計画しています。
これらのプロジェクトは、パンデミック以前から計画されていたものですが、計画が中止されることなく着実に進行しているのです。
投資家たちは、ニセコが持つブランド価値や、パウダースノーという唯一無二の資源が、長期的に見て依然として高いポテンシャルを秘めていると判断しています。
この絶え間ない投資と開発の動きは、ニセコがまだ成長の途上にあることを物語っていると言えるでしょう。
期待されるインバウンド回復の兆し
ニセコの今後を占う上で最大の鍵となるのが、インバウンド観光客の回復です。そして、その兆しは着実に現れ始めています。
水際対策の大幅な緩和以降、オーストラリアやアジア各国を中心に、外国人観光客がニセコに戻ってきました。
特に、円安は海外の旅行者にとって大きな魅力となっています。以前よりも割安な費用で、世界最高品質のパウダースノーや日本の食文化を楽しめるため、ニセコは旅行先としての競争力をさらに高めているのです。
実際に、スキー場のリフト待ちの列には、再び多言語が飛び交うようになりました。ホテルやコンドミニアムの予約状況も好調に推移しており、パンデミック以前の水準に近づきつつあるという声も聞かれます。
もちろん、世界経済の動向や国際情勢といった不確定要素は存在します。しかし、一度ニセコの魅力を知ったリピーターや、口コミで評判を聞きつけた新規の旅行者が、今後も安定して訪れる可能性は非常に高いと考えられます。
このインバウンド需要の力強い回復が、ニセコ経済を再び活性化させる原動力となることは間違いありません。
再燃するオーバーツーリズム懸念への対策
観光客が戻ってくることは喜ばしい一方、新たな課題も浮上しています。それが、コロナ禍以前から問題となっていたオーバーツーリズムへの懸念です。
オーバーツーリズムとは、観光客が過度に集中することで、地域住民の生活や自然環境に悪影響が及ぶ状態を指します。
ニセコでは、交通渋滞、ゴミ問題、騒音、そして何より地域住民が利用するサービスの混雑といった形で、問題が顕在化していました。
観光客が回復しつつある今、これらの問題にどう対処していくかが、ニセコの持続可能な発展のために極めて大切になります。
この課題に対し、地域ではすでに対策が始まっています。例えば、公共交通機関の充実を図るための実証実験や、ゴミの分別を多言語で呼びかける啓発活動、観光客が集中する時期や場所を分散させるための情報発信などです。
また、宿泊税の導入なども検討されており、得られた財源をインフラ整備や環境保全に充てることで、観光客と住民の双方が快適に過ごせる町づくりを目指しています。これらの対策がうまく機能するかどうかが、今後のニセコの評価を左右するでしょう。
解決が急務の交通インフラ課題
ニセコの長期的な発展を見据えたとき、避けては通れないのが交通インフラの問題です。特に、夏場の二次交通の脆弱性は、長年の課題として指摘されています。
冬のスキーシーズン中は、各リゾートや主要な宿泊施設を結ぶシャトルバスが頻繁に運行されており、比較的移動には困りません。
しかし、スキーシーズンが終わると、バスの運行本数が激減し、レンタカーがなければ移動が非常に困難になるのが実情です。
これにより、グリーンシーズンに訪れた観光客の満足度を下げてしまうだけでなく、多様な滞在スタイルの提案を阻害する要因にもなっています。
この問題の解決に向けて、北海道新幹線の札幌延伸と、それに伴う倶知安駅の再開発は大きな希望です。新幹線が開業すれば、新千歳空港や札幌からのアクセスが飛躍的に向上します。
この機会を捉え、駅から各エリアへのバス路線網を再整備したり、シェアサイクルやデマンド交通といった新しい移動手段を導入したりすることが求められます。
冬だけでなく、一年を通して観光客が快適に周遊できる環境を整えることが、ニセコが通年型リゾートへと進化するための不可欠なステップとなります。
地域経済を揺るがす人材不足問題
前述の通り、コロナ禍を経て、ニセコエリアの人材不足はさらに深刻化しました。この問題は、地域経済の回復と成長を根本から揺るがしかねない、喫緊の課題です。
インバウンド観光客が戻り、宿泊施設や飲食店の需要が回復しても、サービスを提供するスタッフがいなければ、質の高いおもてなしは実現できません。
実際、人手が足りないために、客室の稼働率を制限したり、営業時間を短縮したりせざるを得ない事業者が後を絶ちません。これは、地域全体にとって大きな機会損失です。
この問題の背景には、季節雇用の多さや、高騰する家賃、そして地域コミュニティとの関わりの希薄さなど、複合的な要因があります。
対策として、通年雇用の創出や、従業員寮の整備、地域住民との交流を促すプログラムの実施などが考えられます。
また、省力化のためのDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進も有効な手段でしょう。
例えば、ホテルのチェックイン業務を自動化したり、飲食店の注文をタブレット端末で行ったりすることで、限られた人員でも効率的に運営することが可能になります。
ニセコが今後も選ばれ続ける観光地であるためには、働き手にとっても魅力的で、持続可能な労働環境を構築することが不可欠です。
総括:「ニセコ 終わった」論の結論
この記事で解説してきた内容を踏まえ、「ニセコ 終わった」という言説について総括します。
- 「終わった」と言われる背景には根拠がある
- 不動産価格や地価の上昇は一時的に鈍化した
- コロナ禍で観光客が激減したのは事実
- 一部ホテルが廃業に追い込まれた
- 一方で開発投資は継続している
- 世界的なホテルブランドの進出計画が進行中
- インバウンド観光客は着実に回復している
- 円安が海外からの旅行者を惹きつけている
- 地価も再び上昇基調に戻っている
- ただし課題も山積している
- オーバーツーリズムへの対策は急務
- 交通インフラ、特に夏場の二次交通が弱い
- 地域経済は深刻な人材不足に直面している
- これらの課題解決が今後の成長の鍵を握る
- 「終わった」のではなく「変革期」にあるのが実情