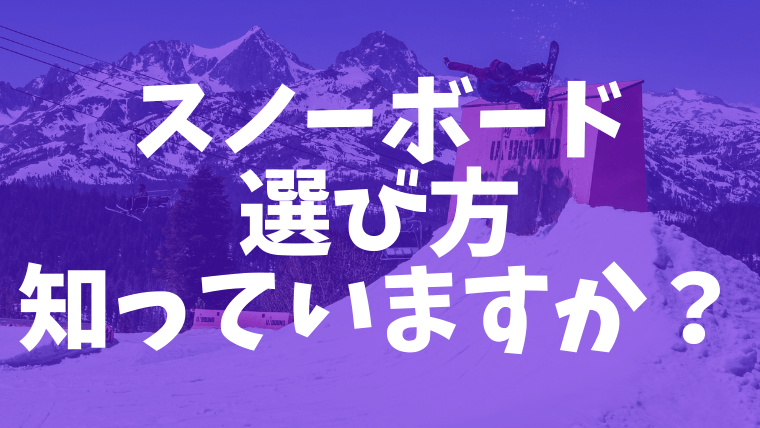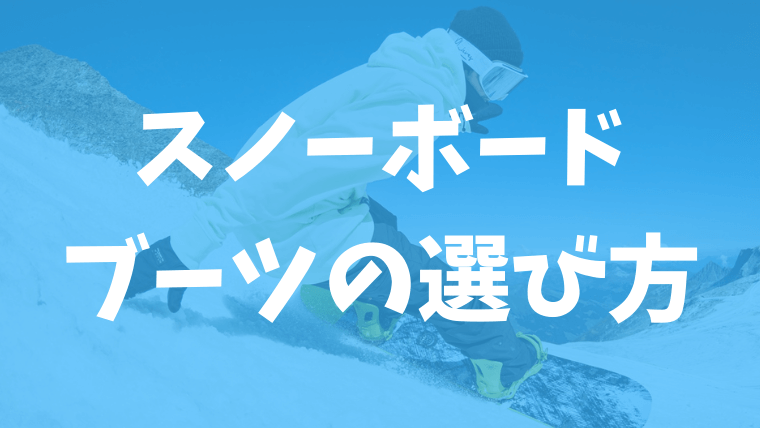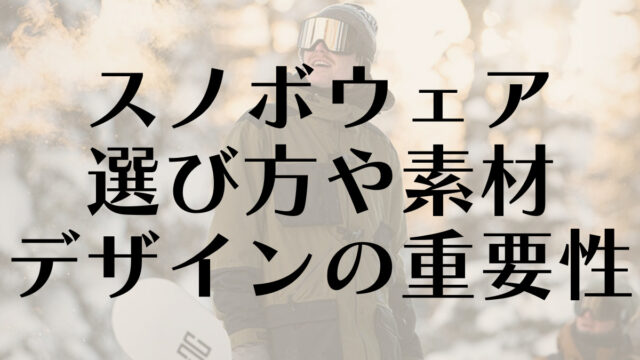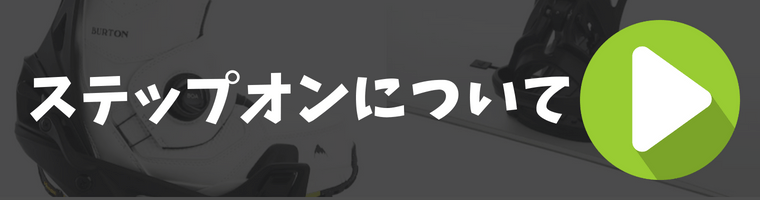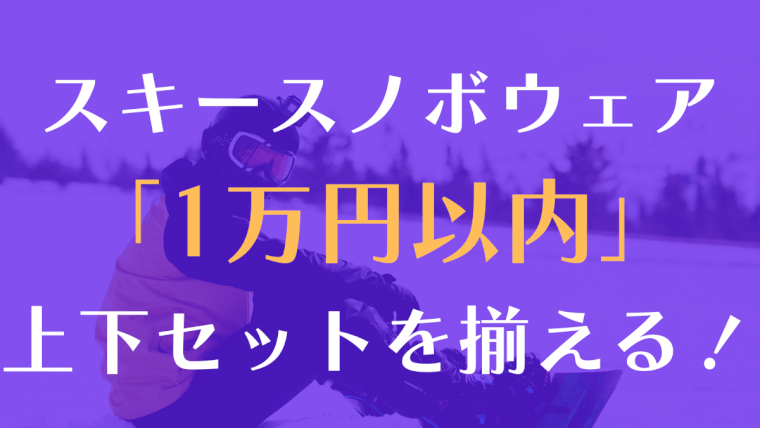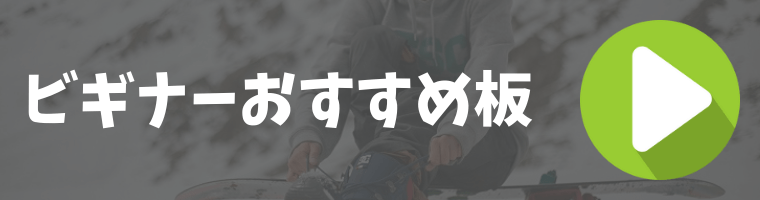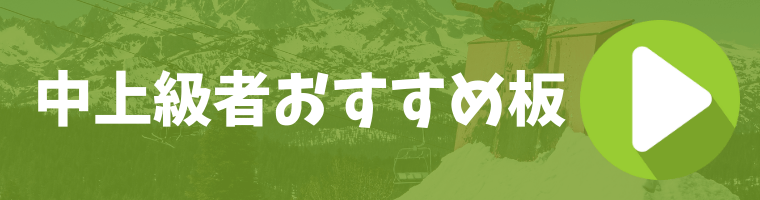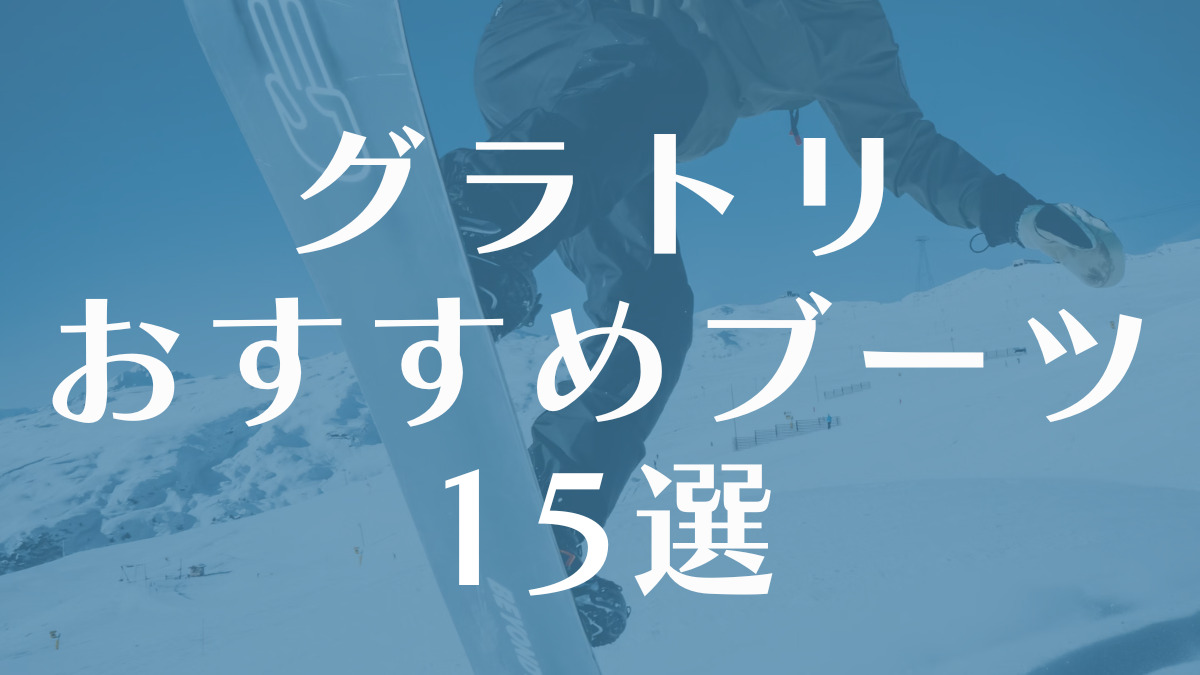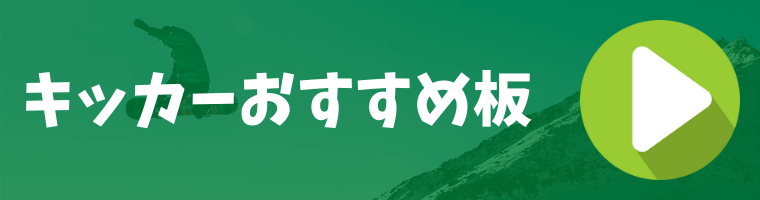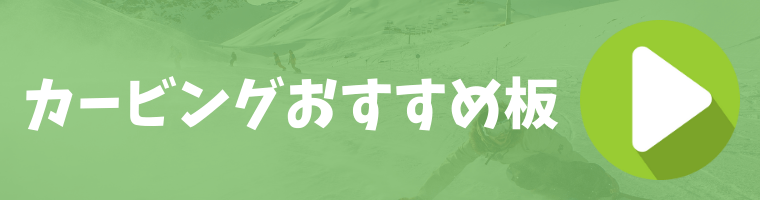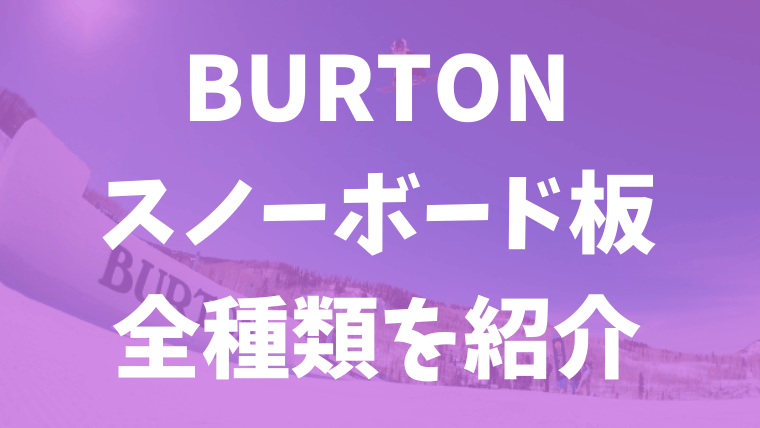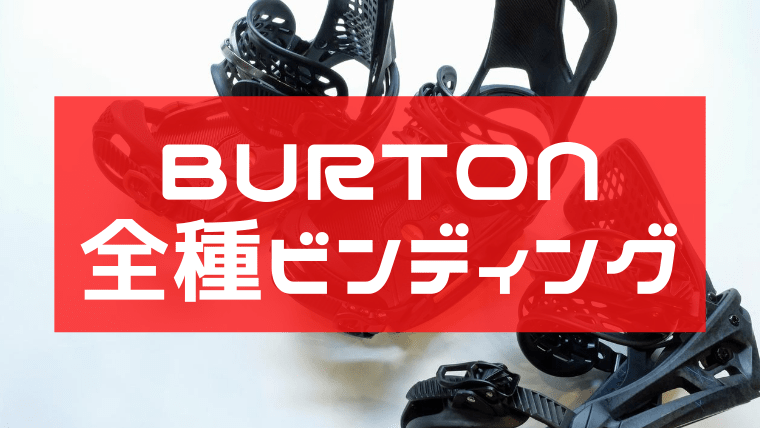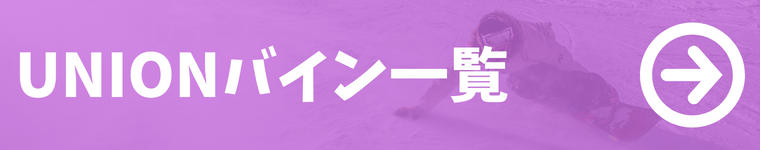大山スキー場「閉鎖」の噂を徹底解説!運営撤退の経緯と今後の展望
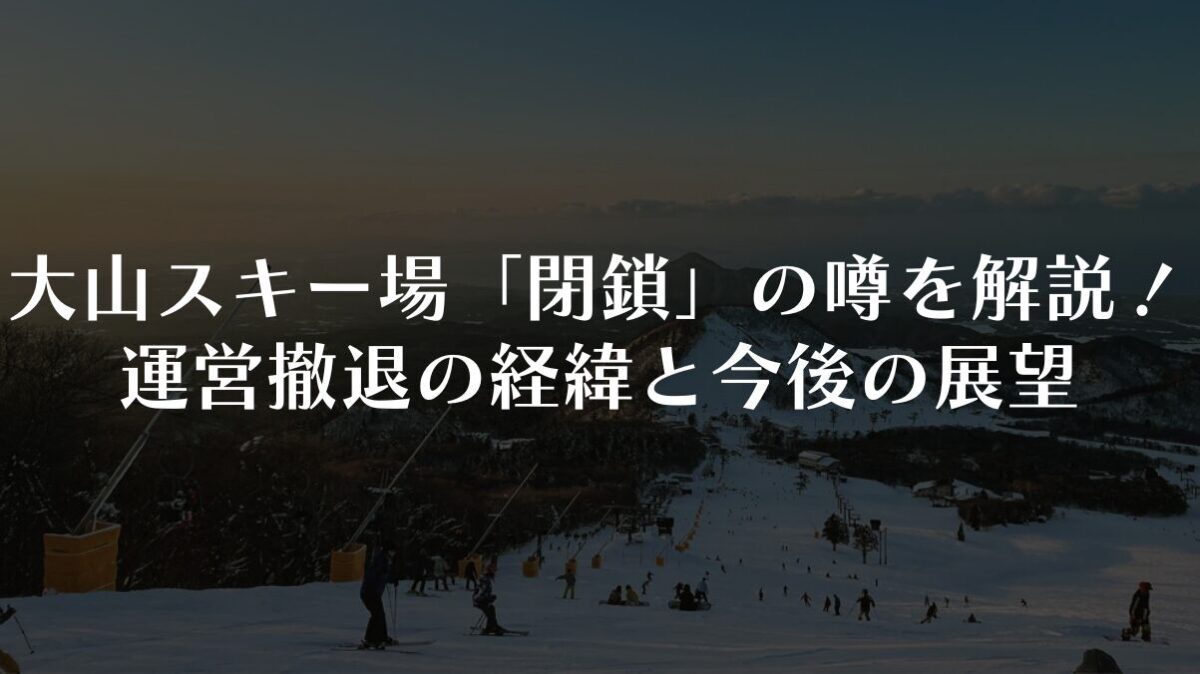
「大山スキー場が閉鎖されるかもしれない」という情報を耳にして、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。西日本最大級の規模を誇るスキー場だけに、その動向は多くのスキーヤーやスノーボーダー、そして地元経済にとって大きな関心事です。
この記事では、大山スキー場の閉鎖というキーワードで検索されている方々が最も知りたい情報、すなわち日交グループの撤退という事実、そして3エリアの譲渡や7500万円の寄付といった具体的な動き、さらには2025-26シーズンの運営が未定である現状と、今後の展望について、客観的な情報を基に詳しく解説していきます。
この記事を読むことで「大山スキー場 閉鎖」と検索した読者が具体的に何について理解を深められるか
- 「閉鎖」の噂と「運営撤退」という事実の違い
- 運営会社が撤退を決断した背景にある複数の課題
- スキー場が抱える施設老朽化や雪不足の深刻さ
- 2025-26シーズン以降の運営に関する今後の可能性
大山スキー場「閉鎖」の噂を徹底解説
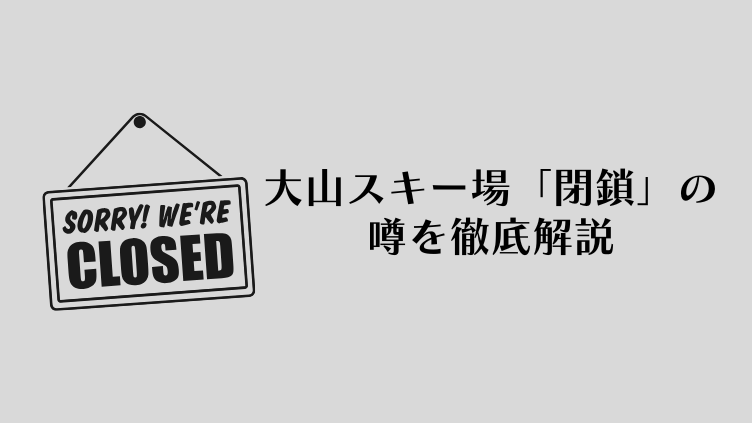
- 「閉鎖」ではなく「運営撤退」が事実
- 日交グループがスキー場運営から撤退
- 3エリアを大山町へ譲渡した経緯
- 7500万円の寄付金が持つ意味
- なぜ閉鎖の噂が広まったのか?
- 2025-26シーズンの運営は未定
「閉鎖」ではなく「運営撤退」が事実
現在広まっている「大山スキー場 閉鎖」という情報は、正確には「即時・恒久的な閉鎖」を意味するものではありません。
今回起きた事態の核心は、長年にわたり「だいせんホワイトリゾート」としてスキー場を運営してきた大手事業者、日交グループがスキー場運営事業から手を引く、すなわち「運営撤退」を決定したことです。
スキー場そのものが即座になくなるわけではなく、運営の主体が変わる(あるいは、変わるための移行期間に入る)というのが現状の正しい理解となります。
ただし、運営者が不在となれば、当然ながら営業はできなくなります。このため、多くの人が「事実上の閉鎖」と受け取り、情報が拡散しているものと考えられます。
日交グループがスキー場運営から撤退
前述の通り、今回の事態の発端は、日交グループがスキー場運営からの撤退を表明したことです。日交グループは、だいせんホワイトリゾートが管理していた豪円山、中の原、上の原、国際の4エリアのうち、もともと町営であった「中の原エリア」を除く3エリアの施設を大山町へ譲渡する意向を示しました。
中の原エリアに関しては、以前から指定管理者として運営を受託していましたが、この指定管理者の公募にも今後は応募しない方針を伝えています。
これにより、日交グループはスキー場運営から完全に撤退することになります。長年にわたる運営実績があっただけに、この決定は地域に大きな衝撃を与えました。
3エリアを大山町へ譲渡した経緯
日交グループは、運営からの撤退にあたり、国際エリア、上の原エリア、豪円山エリアの3エリアの索道(リフト)施設や関連施設を、大山町へ無償で譲渡する手続きを進めました。
民間企業が運営していた施設を、行政である町が引き継ぐ形になります。これは、日交グループが単独で運営を継続することが困難になった一方で、大山町としてもスキー場が地域の観光や経済において極めて重要な施設であると認識しているためです。
仮に町が譲渡を受け入れなければ、施設がそのまま放棄され、スキー場が即時閉鎖となる可能性もありました。町が譲渡を受け入れたことは、スキー場存続に向けた第一歩と捉えられます。
7500万円の寄付金が持つ意味
施設の無償譲渡に加え、日交グループは大山町に対して7500万円を寄付しました。この寄付金は、主に老朽化した施設の修繕や当面の維持管理費用に充てられるものと見られます。
スキー場の運営、特にリフトなどの索道施設を安全に維持管理するには、莫大なコストがかかります。例えば、リフトのワイヤーロープ(索条)の交換には1基あたり数千万円規模の費用が必要とされる場合があります。
したがって、7500万円という金額は、複数のリフトを抱えるスキー場全体の根本的なリニューアル(架け替えなど)を行うには全く足りません。しかし、喫緊の課題である安全対策や修繕を行い、次の運営体制へ引き継ぐための「つなぎ資金」として、非常に重要な意味を持つ寄付であると言えます。
なぜ閉鎖の噂が広まったのか?
「運営撤退」が「閉鎖」という噂として広まった背景には、スキー場運営の「空白期間」に対する強い懸念があります。
長年運営を担ってきた日交グループが撤退した後、次の運営者が即座に決まる保証はどこにもありません。特に、スキーシーズンの直前になっても新しい運営体制が発表されなければ、「今シーズンは営業できないのではないか」「このまま廃止されるのではないか」という不安が広がるのは当然の流れです。
また、後述するようなスキー場が抱える根本的な課題(雪不足、老朽化など)を多くの人が認識しているため、引き受け手が見つからないのではないか、という悲観的な見方が「閉鎖」の噂を加速させたと推測されます。
2025-26シーズンの運営は未定
(※本記事執筆時点)
最も懸念される2025-26シーズン(今冬)の運営については、残念ながら「未定」というのが実情です。
大山町が施設を引き継いだものの、町が直接スキー場を運営する「町営」に戻すのか、あるいは新しい指定管理者(運営を委託する民間事業者)を公募するのか、その方針はまだ明確に示されていません。
仮に指定管理者を公募するとしても、応募する事業者が現れるか、選定や引き継ぎがシーズン開始までに間に合うかなど、多くのハードルが存在します。この不透明な状況こそが、利用者や地元関係者が最も不安を感じている点です。
大山スキー場の閉鎖の危機と今後の展望

- 運営撤退の背景にある3つの課題
- 課題①:深刻な雪不足と暖冬
- 課題②:リフトなど施設の老朽化
- 課題③:スキー・スノボ人口の減少
- 町の譲受は「存続」の意思表示か
- 今後の運営体制はどうなる?
- 新たな指定管理者を公募する可能性
運営撤退の背景にある3つの課題
日交グループが運営撤退という苦渋の決断に至った背景には、単一の理由ではなく、日本の多くのスキー場が直面している複合的な課題が存在します。
主に「気候変動」「施設の老朽化」「市場の変化」という3つの大きな課題が、民間企業としての運営継続を困難にしたと考えられます。これらは、だいせんホワイトリゾートに限った話ではなく、地方の中小スキー場にとっては死活問題となっています。
これらの課題を抜きにして、今後の展望を語ることはできません。次のセクションから、それぞれの課題について具体的に掘り下げていきます。
課題①:深刻な雪不足と暖冬
第一の課題は、気候変動に伴う深刻な「雪不足」と「暖冬」です。特に西日本のスキー場にとって、これは最も深刻な経営リスクとなっています。
安定した積雪が見込めなければ、営業日数は大幅に減少し、収益は直接的な打撃を受けます。近年、12月のオープンが遅れたり、シーズン終了が早まったりするケースが全国的に増加しています。
また、気温が高いと人工降雪機(スノーマシン)も稼働できず、雪不足対策すらままならない状況も発生します。十分な雪がないスキー場に客足が向かないのは当然であり、収益の悪化に直結します。
課題②:リフトなど施設の老朽化
第二の課題は、リフト(索道)をはじめとする「施設の老朽化」です。
日本のスキー場の多くは、1980年代から90年代初頭のスキーブーム時代に建設されました。だいせんホワイトリゾートの施設も例外ではなく、建設から数十年が経過しているものが少なくありません。
安全に運行を続けるためには、毎年の徹底した分解整備(オーバーホール)に加え、定期的な大規模修繕(ワイヤーロープの交換など)や、最終的にはリフト自体の「架け替え」が必要になります。前述の通り、これらの費用は数千万から、高速リフトの架け替えとなれば十数億円規模に達することもあり、雪不足で収益が不安定な中、この莫大な投資コストを民間企業が負担し続けるのは極めて困難です。
課題③:スキー・スノボ人口の減少
第三の課題は、国内の「スキー・スノーボード人口の減少」です。
1990年代をピークに、日本のスノースポーツ人口は長期的な減少傾向にあります。レジャーの多様化や少子化、若者の車離れなどが要因とされています。
顧客の絶対数が減れば、当然ながらスキー場間の競争は激化します。インバウンド(訪日外国人客)の取り込みに成功している一部の大型リゾートを除き、多くの中小スキー場は集客に苦戦しているのが実情です。
運営会社にとっては、雪不足や老朽化対策でコストが増大する一方で、売上の基盤となる客数が減少するという、非常に厳しい経営環境に置かれていたことがうかがえます。
町の譲受は「存続」の意思表示か
このような厳しい状況下で、大山町が日交グループからの施設譲渡と寄付を受け入れたという事実は、非常に重要な意味を持ちます。
もし町がスキー場を「不要な施設」と判断していれば、譲渡を受け入れず、そのまま閉鎖・廃止の道を選択した可能性もあります。
あえて施設を引き受けたということは、大山町がスキー場を「町の観光振興の拠点」として重要視しており、何らかの形で「存続させたい」という意思表示であると考えることができます。地域のシンボルであり、冬の観光・経済に与える影響が計り知れないため、行政として存続の道を探る姿勢を見せたものと受け取れます。
今後の運営体制はどうなる?
今後の運営体制については、いくつかの可能性が考えられますが、現時点では不透明です。
考えられる選択肢は、大きく分けて「町による直接運営(町営)」か、「新たな指定管理者による運営」の2つです。
町営の可能性
町が直接運営する「町営スキー場」として再スタートする可能性です。しかし、スキー場の運営には高度な専門知識や技術(リフトのメンテナンス、ゲレンデ整備、パトロールなど)が必要であり、多くのスタッフも雇用しなくてはなりません。財政的な負担も大きく、行政が直営で担うハードルは非常に高いのが実情です。
指定管理者制度の可能性
そこで、より現実的な選択肢として、次のセクションで解説する「指定管理者制度」の活用が挙げられます。
新たな指定管理者を公募する可能性
最も現実的なシナリオは、大山町が施設を所有したまま、運営ノウハウを持つ民間事業者を「指定管理者」として公募し、運営を委託する方式です。
すでに「中の原エリア」で採用されていた手法であり、全国の多くの公設スキー場で導入されています。町は募集要項を作成し、運営を希望する事業者を審査して選定します。
ただし、最大の懸念は「応募者が現れるか」という点です。前述した3つの大きな課題(雪不足、老朽化、人口減)を抱える赤字リスクの高い事業に、手を挙げる民間企業がすぐに見つかるかは未知数です。
運営条件(町からの支援額、修繕費用の分担など)をいかに設定し、事業者にとって魅力ある公募にできるかが、今後の存続の鍵となります。
大山スキー場 閉鎖の回避に期待
- 「大山スキー場 閉鎖」は決定事項ではなく「運営撤退」が発端
- 日交グループが3エリアの施設を大山町に無償譲渡
- 同時に7500万円の寄付も実施
- 寄付金は主に老朽化対策や当面の維持費に充てられる見込み
- 2025-26シーズンの運営体制は本記事執筆時点で未定
- 運営者が決まらないことへの不安が「閉鎖」の噂につながった
- 運営撤退の背景には深刻な3つの課題がある
- 課題1は気候変動による雪不足と暖冬
- 課題2はリフトなど施設の老朽化に伴う莫大な修繕コスト
- 課題3はスキー・スノボ人口の長期的な減少
- 大山町が施設を譲受したことは「存続の意思表示」と受け取れる
- 今後の運営は「町営」または「指定管理者の公募」が考えられる
- 専門性や財政負担を考慮すると指定管理者の公募が現実的
- ただし厳しい経営環境の中で応募事業者が現れるかが最大の焦点
- 西日本のスノーシーンを守るためにも閉鎖の回避が強く望まれる